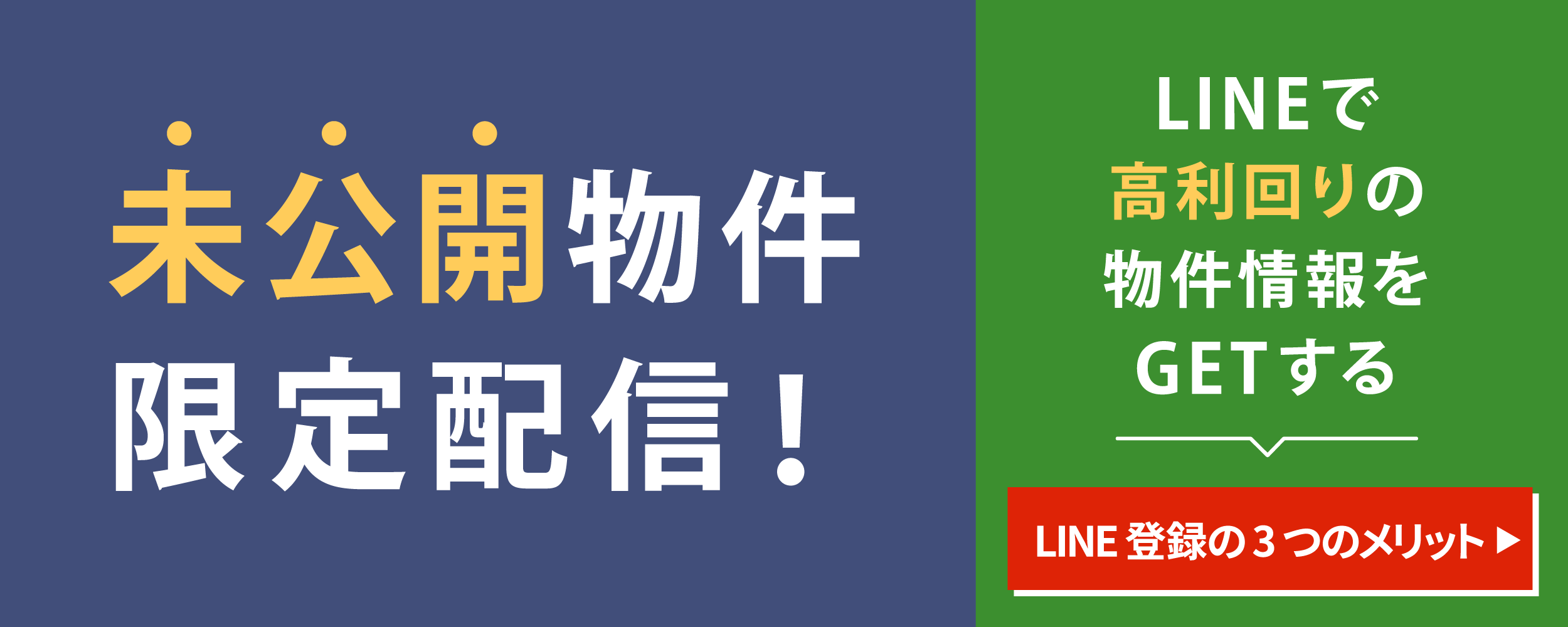強制退去の断行日までのスケジュールと当日の流れを解説!よくあるトラブルも紹介
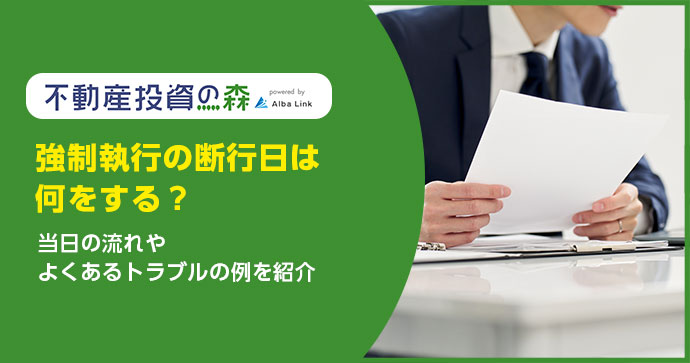
「強制退去の断行日が近づいているけど、何から準備すればいいのかわからない…」そんな不安を抱えていませんか?
所有する物件に入居者が居座り続け、明け渡しの手段として強制執行を選んだものの、実際に「断行日」とは何をする日なのか、どんな流れで進むのか、費用やトラブルのリスクが見えずに踏み出せない方も多いでしょう。
実は、強制退去の断行日までには、法律に基づいた明確な手続きとスケジュールが存在します。
スケジュールを正しく理解し、適切に準備することで、余計なトラブルや費用負担を避けることができます。
ただし、断行日には入居者との感情的な対立や、残置物の処理・費用回収の問題など、いくつかの注意点があるのも事実です。
そこで本記事では、以下のようなポイントを詳しく解説します。
最後まで読むことで、断行日を迎えるまでの不安や疑問を解消し、トラブルを最小限に抑えたうえでスムーズに物件を回収するための道筋が見えてきます。
こうした状況を経て、物件を再生・運用していくことも一つの選択肢です。
訳あり物件でも、見方を変えれば高利回りが狙える投資対象になることもあります。
私たちAlbalink(アルバリンク)は、収益性の高い物件の情報をLINEで無料提供しています。
弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。
強制退去に限らず、不安や悩みを抱えている方は、ぜひLINE登録して最新情報をチェックしてみてください。
目次
強制退去の断行日までの全体スケジュール
強制退去の断行日までのスケジュールを把握することは、スムーズに手続きを進めるうえでとても重要です。
ここでは、強制退去の断行備までの全体スケジュールについて、以下のようなことを解説します。
催告日から断行日までの一般的な期間の目安
催告日から断行日までの期間は、賃借人に退去の猶予を与えるため、2週間から1ヶ月程度が目安とされています。
- 催告日
- 裁判所が建物の強制執行を決定した際、執行官が借主に対して任意に物件を明け渡すよう告げ、実際に強制執行を行う期日を伝える日
- 断行日
- 強制執行において、執行官が実際に建物の明け渡しを行う日
実際の期間は、催告日から断行日を指定するまでの間に、債務者の対応状況や不動産の状態などを見て、総合的に判断されます。
たとえば、部屋に荷物が多く残っていたり、明渡しに対して強い拒否姿勢が見られたりする場合は、準備に時間を要することを見越して、期間を長めに設定する場合もあります。
断行日が確定するまでに必要な手続き
断行日が確定するまでに必要な手続きの流れは、次のとおりです。
- 賃貸借契約の解除が正当と判断された場合、貸主が訴訟を提起する
- 訴訟の判決を得る
- 執行文の付与や債務名義の確保を行う
- 裁判所に強制執行の申立てを行う
判決後すぐに執行官へ依頼しても、執行官のスケジュールや平日の対応制限により、実施までに時間がかかるケースもあります。
裁判所への申立て以外に、借主の荷物の搬出・保管、補助者の手配なども進めなければなりません。
断行日を確定させるには、法律に基づいた正確な手順を踏むことが求められます。
弁護士や専門業者との打ち合わせをしながら、全体のスケジュールを管理しましょう。
断行日前に行われる「催告」とは
「催告」とは、断行日前に執行官が債務者に対して退去を促す正式な通知行為のことです。
賃借人に最後の自発的な明渡しの機会を与えることを目的としており、強制退去の手続き上、とても重要なステップです。
催告時に執行官が借主のもとを訪問し、断行日が指定された文書を提示することで、借主が自主的に退去する可能性も高まります。
催告をするときに誠実な対応をすることで、後々の追加費用の発生やトラブルを避けることにもつながります。
強制退去の断行日当日の3つの流れ
強制退去の断行日は、裁判所の手続きを経て確定し、執行官の指揮のもとで厳格に進行します。
当日の基本的な流れは、以下の3ステップです。
STEP1:執行官・執行補助者・鍵業者などが集合して借主に説明を行う
断行日の最初に行われるのが、執行官・執行補助者・鍵業者などの関係者の集合と、借主への説明です。
- 執行官
- 裁判所の決定を実現する公務員のこと
- 執行補助者
- 強制執行の際、執行官の指揮の下で業務を行う業者のこと
執行前に現場の状況を確認し、債務者である借主に対して正式に明渡命令の内容を伝えることで、強制執行に対する理解と対応を促します。
現場では執行官が訪問時に賃借人と直接話し、物件内の荷物や生活状況を把握した上で、退去を促す説明をするのが基本的な流れです。
場合によっては、弁護士や大家が立ち会うこともあります。
説明の段階で誠実な対応をすることで、トラブルを回避し、予定通りに手続きを進めやすくなります。
STEP2:残置物の運び出しと保管手続きをする
説明を終えたら、室内に残された荷物(残置物)の搬出と保管を行います。
強制退去は明渡しの実現を目的としているため、部屋の中に荷物が残っていては、退去が完了したとは言えません。
そのため、執行官の立会いのもと、業者が部屋にある家具や家電などを丁寧に運び出します。
食器棚のような大型の家財道具がある場合は、事前にトラックや作業員を複数用意するなどの準備も必要です。
運び出された荷物は、一定期間、定められた場所で保管され、売却や処分の対象になることもあります。
残置物の運び出しと保管は費用や手順が複雑なので、裁判所への申立ての内容や状況によって、負担の大きさが異なります。
貸主は弁護士と連携しながら、適切に対応しましょう。
STEP3:鍵を交換して物件を引き渡す
最後に、鍵の交換と物件の引き渡しを行えば、強制退去の全行程が完了し、貸主側への明渡しが実現されます。
鍵の交換は、再度の不法侵入を防ぐために必要な対応で、通常は鍵業者がその場で新しい鍵を取り付け、以前使っていた鍵は無効にされます。
鍵の交換を怠ると、借主が再度侵入するトラブルが発生するリスクがあるため、強制退去の断行日当日に鍵の交換も済ませておくことが重要です。
鍵の交換とともに、執行官が物件の現状を確認し、原状回復の有無や建物の損傷状況などを記録することで、引き渡しが完了します。
引き渡しが完了すれば、貸主は新たな入居者の募集をはじめ、次の準備に取り掛かることができます。
強制退去の断行日までにかかる費用負担
強制退去を実施するためには、裁判や執行手続きに関連する多くの費用が発生します。
ここでは、強制退去の断行日までにかかる費用負担に関する、以下の3つのことを解説します。
予納金・執行補助者費用の内訳
強制執行における費用のうち、大きな割合を占めるのが、予納金と執行補助者への報酬です。
両者とも手続きの初期段階で必要になるため、事前の準備が欠かせません。
- 予納金
- 執行官の交通費や郵送費など、裁判所に支払う実費のこと。強制退去の場合は、相場は3万〜5万円。
- 執行補助者への報酬
- 断行日に立ち会って荷物の搬出や立ち退き作業を行ってもらうため、10万円前後の報酬がかかる。
物件の階数が高かったり、荷物が多かったりする場合には、補助者の人数も増えるため、さらに費用がかさむと考えて良いでしょう。
加えて、鍵業者やトラック業者への依頼も必要となることもあります。
内訳を正確に把握し、法律事務所や執行官と打ち合わせを重ねて、予算超過を防ぎましょう。
残置物処分や保管料等の追加費用が発生する場合がある
強制退去の現場では、賃借人の荷物が残されたままになることが多く、これに伴う処分費用や保管料が追加で発生することがあります。
たとえば、家具や家電などの大型の残置物があった場合、搬出費用として5万〜10万円、保管料として1ヶ月あたり数万円かかることもあります。
残置物は一定期間保管した後に売却や処分をするのが基本のため、貸主にとっては予想外の出費になるかもしれません。
残置物に関する費用の負担を抑えるには、断行日前の催告の段階で、借主に自発的な撤去を促すことが効果的です。
残置物の処理は強制退去の中でも特に手間と費用がかかる工程なので、事前の準備と打ち合わせが欠かせません。
費用回収の可否と注意点
強制退去にかかった費用を賃借人から回収できるかどうかは、判決の内容とその後の執行によって異なります。
必ずしも費用の全額を回収できるとは限らない点に、注意が必要です。
判決で家賃滞納分や強制執行費用の負担が認められても、債務者に支払い能力がない場合、実際に回収できる保証はありません。
とくに、賃料滞納が6ヶ月以上に及ぶような状況では、すでに借主が経済的に困窮しており、回収に時間や手間がかかることがあります。
競売や給料差押えを申し立てる際にも、追加の手続きと費用が必要です。
費用回収は、法的には可能でも、実際は難しい場面が多いため、初めから「費用は貸主側が負担する可能性が高い」と想定して手続きを進めることが現実的です。
入居者の心理的な不安や感情的な対立への備え
強制退去の現場では、法的な手続きだけでなく、入居者との対立も発生しやすいため、気持ちの準備も重要です。
断行日は、貸主だけでなく借主にとっても大きなストレスがかかる状況であり、感情的な反発や抗議が起こることも珍しくありません。
たとえば、執行官の訪問時に入居者が泣き出したり、怒鳴ったりして、対応を誤るとトラブルに発展することがあるのです。
不安や対立に備えるには、弁護士や補助者と共に、現場対応の方針を事前に打ち合わせておくことが有効です。
強制退去は強制的な措置ですが、可能な限り人道的かつ法的に適切な形で手続きを進めましょう。
強制退去の断行日の延期・中止が発生する3つのケース
強制退去の断行日は、原則として裁判所により指定された期日に実施されますが、状況によって延期または中止されることがあります。
強制退去の断行日の延期・中止が発生する主なケースは、以下の3つです。
入居者との和解が成立して強制退去が中止になる
強制退去の断行日であっても、直前で入居者との和解が成立した場合には、退去手続きが中止されることがあります。
賃料滞納の支払いや退去日程について両者が合意し、裁判所を通じて訴訟を終了させることで、断行を避ける方法
たとえば、借主が退去する意思を示し、数日以内の明渡しを約束する代わりに、強制執行を取り下げることがあるのです。
断行にかかる費用や心理的負担を軽減できるため、貸主としても和解の道を常に念頭に置いておくと良いでしょう。
天候・体調不良・法的手続きの遅れ等で延期される
強制退去の断行日は、予定されていても、天候や体調不良、法的手続きの遅れなどが理由で延期されることがあります。
なぜなら、断行作業は執行官や補助者、業者など多くの人員が関わり、荷物の搬出や建物の立ち退きといった作業が伴うため、安全な環境での実施が必要不可欠だからです。
たとえば、悪天候による道路の封鎖や、補助者がインフルエンザで出勤できないといった状況では、強制退去の実施が困難になります。
また、申立て書類に不備がある場合や送達が完了していない場合も、法的に手続きが進行できず延期されることがあります。
裁判所の判断で延期される
強制退去の断行日が延期されるケースのなかには、裁判所の判断によるものもあります。
たとえば、借主側が異議申し立てや仮処分の申請を行い、それが裁判所に受理された場合、一時的に断行が停止されることがあるのです。
裁判所の判断は、手続きの適正性を担保するために設けられており、すべての強制執行が機械的に進むわけではありません。
貸主としては、必要な提出書類の正確性を確保し、弁護士と相談しながら迅速な対応を取ることが、不要な延期を回避するカギになります。
強制退去の断行日に発生しやすい3つのトラブル
強制退去の断行日は、手続き上の最終局面です。
その一方で、予期せぬトラブルが発生しやすいタイミングでもあります。
ここでは、強制退去の断行日に発生しやすいトラブルとして、以下の3つを紹介します。
入居者が抵抗したり居座ったりする
強制退去の断行日に発生しやすいトラブルのひとつが、入居者による居座りや抵抗です。
断行とは法的に確定した明渡命令に基づく手続きですが、債務者が納得していない場合、執行官に対して激しく反発するケースがあるのです。
たとえば、断行当日になって突然「まだ部屋を明け渡したくない」「退去に同意していない」と主張され、執行が一時中断することがあります。
状況によっては、警察の立ち合いを求めることになるでしょう。
入居者の抵抗に関するトラブルを防ぐには、事前の催告や連絡で入居者の意思を丁寧に確認し、弁護士や執行補助者との連携を強化することが重要です。
賃貸物件の立ち退き拒否や居座りについては、こちらの記事でも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

残置物処理を巡って後日紛争に発展する
室内に残された荷物、いわゆる「残置物」の取り扱いを巡って、後でトラブルや訴訟に発展するケースも少なくありません。
なぜなら、荷物の処分には債務者の財産権が関係するため、強制的な撤去・売却・廃棄は正当な手続きを経なければならないからです。
もしかすると、断行後に処分した家具について、借主から「勝手に処分された」と損害賠償を請求されるかもしれません。
高額な物や思い出の品が含まれていた場合は、より深刻な争いに発展しやすいでしょう。
残置物に関するトラブルを回避するには、執行官の指示に基づいて残置物を適切に保管し、処分前に所定の期間を設けることが重要です。
法律事務所と相談したり、処分通知の発送時期をよく検討したりして、正確に手続きを進めることを心掛けましょう。
動物や危険物が部屋に放置されている
強制退去の現場では、想定外のものが残されていることもあります。
特に注意が必要なのは、動物や危険物の放置です。
借主が動物を飼育していた場合、退去後の部屋に犬や猫、鳥などが放置されていることがあり、衛生面や動物愛護の観点から問題が生じます。
また、スプレー缶や薬品などの危険物が放置されていた場合は、安全確保のために断行の延期を余儀なくされることもあります。
動物や危険物の放置を避けるには、事前に現場の状況を可能な範囲で把握し、必要に応じて専門機関と連携することが大切です。
強制退去の断行日までにオーナーが準備すべき3つのこと
強制退去の断行日までに、賃貸人やオーナーが適切に準備しておくことは、明渡しをスムーズに進めるためにとても重要です。
強制退去の断行日までにオーナーが準備すべきこととしては、以下の3つが挙げられます。
証拠や書類を整理・提出する
断行日までに必要な書類や証拠を整理し、裁判所や弁護士に提出しておくことは、強制退去の流れを円滑にするための基本です。
裁判所は執行文の付与や債務名義の有効性を確認するために、契約書や家賃滞納の記録などの詳細な資料を必要とするからです。
明け渡しに関連する次のような書類が不足していた場合、断行そのものが差し止められる可能性もあります。
- 家賃請求の通知書
- 賃貸借契約書
- 催告書
- 訴訟の判決文
- 送達報告書な
弁護士や法律事務所と相談しながら、提出すべき証拠を時系列で整理しておきましょう。
弁護士や執行業者と事前に打ち合わせる
強制退去の断行を成功させるには、弁護士や執行補助者、業者との綿密な打ち合わせが欠かせません。
事前に話し合いをしておくことで、想定外の事態への対応力を高めることができます。
特に執行官による訪問時には、部屋の状況や賃借人の態度、荷物の量など、現場ごとの細かな対応が求められます。
もし搬出作業を担当する業者が鍵業者と連携できていないと、作業が大幅に遅れるかもしれません。
打ち合わせ不足が、費用や時間のロスにつながるのです。
断行日当日の作業をスムーズに進めるため、事前に担当者同士で役割分担・連絡方法・当日の手順を事前に共有しておきましょう。
費用・日程・残置物への対応を明確にする
強制退去にはさまざまな費用や手間が発生するため、あらかじめ予算・日程・残置物への対応方針を明確にしておく必要があります。
準備不足や判断の遅れが、追加費用の発生や日程の再調整といった、さらなる負担を招くからです。
残置物の量が多くて処分業者を急きょ増員した場合、当初予定していた費用を大幅に超過してしまいます。
準備不足を防ぐため、費用の内訳を弁護士と確認したり、搬出・保管・処分の業者と具体的な契約を事前に結んだりしておきましょう。
まとめ
強制退去の断行日は、住民への説明や残置物の運び出しなど、さまざまな作業を実施します。
事前準備をしっかりしていれば、ある程度スムーズに作業を進められますが、「本当にスムーズにいくのか」「トラブルにならないか」といった不安を感じることはあるでしょう。
不動産投資をする際は、強制退去に関連するリスクに直面する前に、物件選びの段階で、トラブルが起こりにくく利回りの高い物件を見つけるのもひとつの方法です。
訳あり物件を専門に扱う買取業者AlbaLink(アルバリンク)では、リスクを抑えつつ高利回りが期待できる物件を紹介しています。
物件の情報は公式LINEで配信しているので、気になる方はぜひ登録してみてください。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!