相続した土地を兄弟で分ける方法と注意点!揉めないための対策も解説
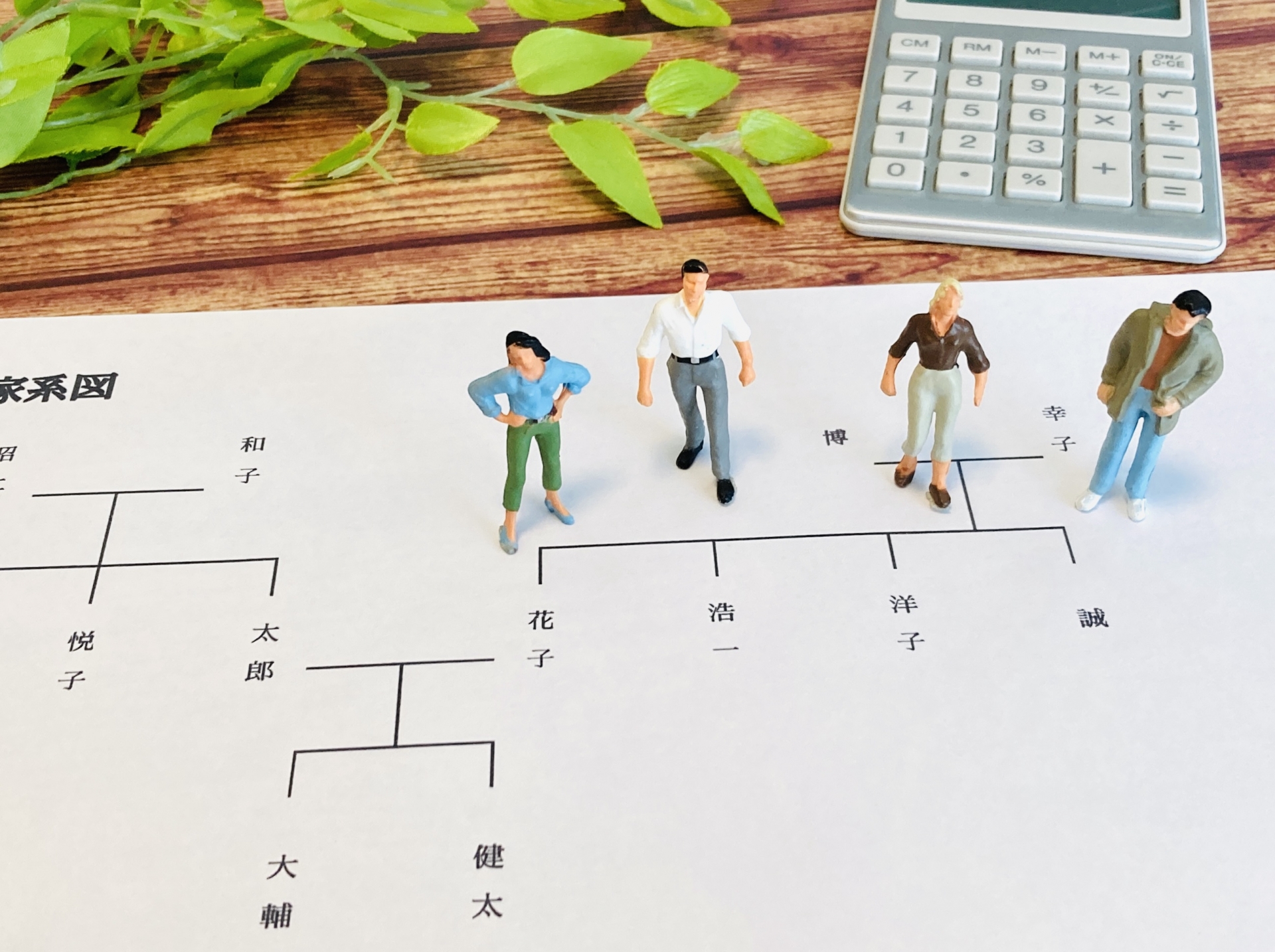
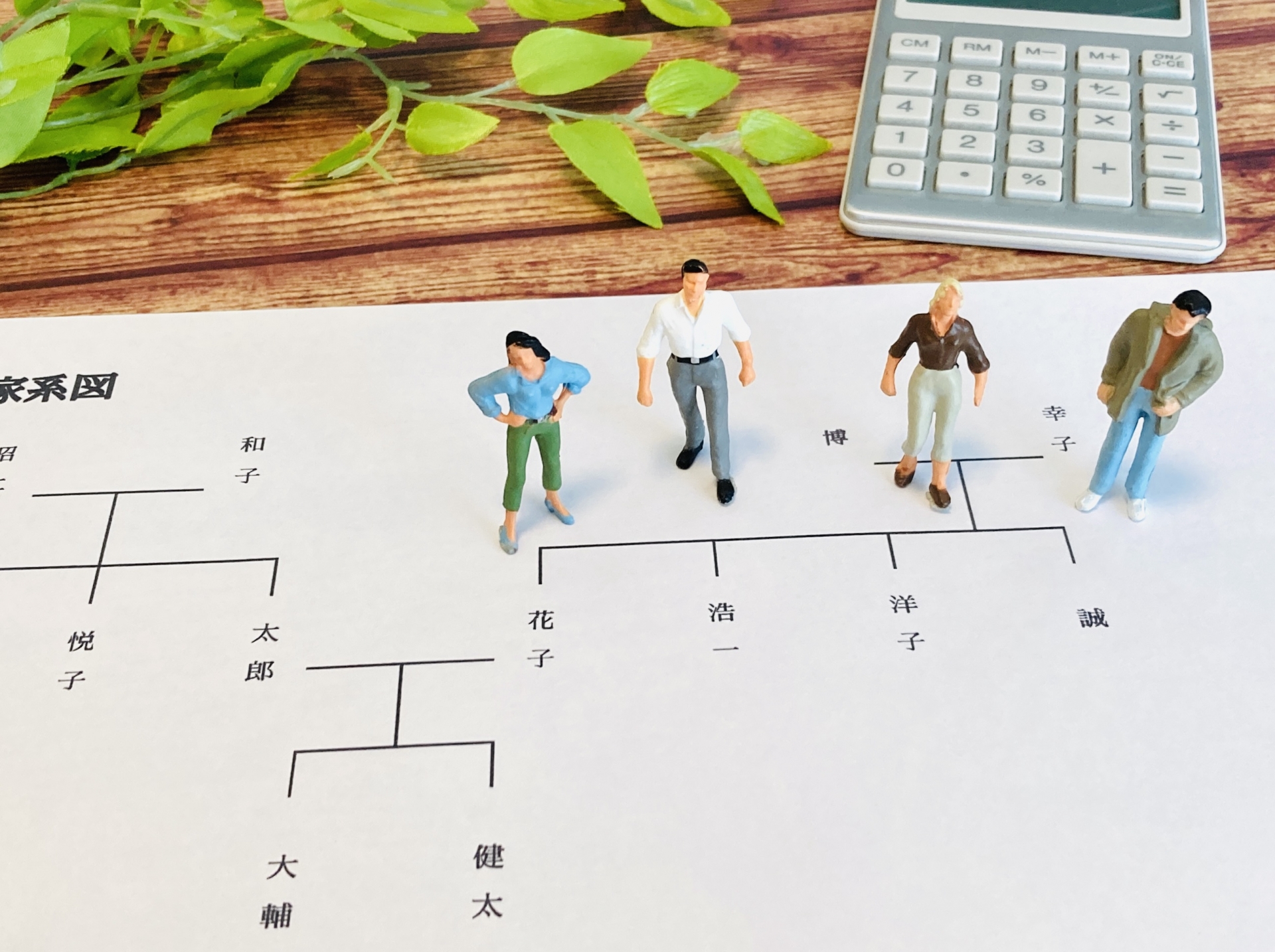
両親から土地を相続したけれど、不動産のままでは兄弟で分けられない…
兄弟間でトラブルなく売却するには、どうすればいいのだろうか…
売却のトラブルを避けるには、最低売却価格や税に関する話し合いを兄弟間でしておくとよいでしょう。
なぜなら、認識の違いや意見の食い違いが、後々大きなトラブルに発展する可能性があるからです。
そうならないため、事前に価格や税について兄弟間で話し合っておく必要があります。
この記事では、兄弟がもめずに土地を相続する方法や共有分割で土地を相続した場合の対処法、売却する際の注意点、トラブル回避のために生前にできることを紹介しています。
最後まで読んでいただければ、自分の状況にあわせて、トラブルなく遺産の土地を売却することができるでしょう。
目次
兄弟で土地を相続する際の心構えと事前準備
・相続開始前
兄弟間で円満に相続を行うには、ご両親が健在な頃から相続に関する話し合いをしておくことです。
「縁起でもない」と敬遠して話し合いを嫌がる人もいるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるために、ぜひ話し合っておきましょう。
たとえば、お盆や法事など、兄弟全員が揃う際などがよい機会です。
相続することになる財産の状況、特に、土地の権利について両親から具体的に聞いておきましょう。
また、ご両親の戸籍情報(出生から現在までの本籍地など)なども聞いておくと役立ちます。
資産が多い場合や特別な意向があって遺言書を作成する必要がある場合は、早くから司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
・相続開始後
遺言書がある場合は、家庭裁判所に届け出て検認を受けます。
この手続きに通常1〜2ヶ月かかります。(公正証書遺言書や法務局に保管された自筆証書遺言書の場合はこの手続きは不要です)
負債が多く、相続放棄を検討している場合は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要なので、四十九日の法要を目安に兄弟で相続について具体的に話し合う必要があるでしょう。
相続税の申告、納税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
いずれも期限内に手続きをしないと申告ができなくなったり過料が課せられる場合があります。
仕事が忙しく、期限内までに兄弟で集まる機会が持てそうにない場合など、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
相続前に確認しておくべき重要書類リスト
相続前に確認しておくべき重要書類には、以下のようなものがあります。
・登記簿謄本
・家の権利書
・固定資産税の評価証明書
・測量図
・境界線確認書
まずは、相続不動産が実際にどのように登記されているか確認しましょう。
自宅の敷地だと思っていた場所が、登記簿上は他人の名義であったというケースもないわけではありません。
何筆かに分けて登記されている場合もあります。
登記の状況は、登記簿謄本や権利書、固定資産税の評価証明書などで確認できます。
また、家を新築改築した際の測量図や境界線確認書があれば、登記簿謄本等と照らし合わせて間違いがないかどうか確認するとよいでしょう。
登記簿謄本を確認することで、抵当権の有無もわかります。
ローンが残っていたり、債務の抵当に当てられている場合はそのままでは売却できません。
このような重要書類は自宅の金庫や仏壇の引き出し、銀行の貸金庫に預けられている場合もあります。
心当たりの場所を必ず確認しましょう。
兄弟間のコミュニケーションを円滑にするコツ
相続手続きには時間も手間もかかり、家族を亡くした後の心労も加わって、些細な行き違いから感情的なトラブルに発展しかねません。
心がけて兄弟間の不公平感が募らないように工夫をしましょう。
相続に関する情報はどんなことでも共有し、「そんな話は聞いていない」という揉め事が起こらないように、進捗状況を文書化して誰でも見られるように記録しておくとよいでしょう。
場合によっては、公平な立場で意見を聞ける専門家を交えて話し合うこともひとつの方法です。
相続した土地を兄弟で分ける方法
相続した土地を兄弟で分ける方法として、以下の5つがあげられます。
- 遺産分割協議で決める
- 現物分割で土地そのものを半分に分ける
- 代償分割で相続財産の差額を現金調整する
- 換価分割で売却金を公平に分配する
- 相続放棄で債務を免れる
遺産分割協議で決める
遺産分割協議とは、遺言書がなかったり、形式や内容が有効でなかった場合に、相続人同士で話し合って遺産を分け合うことです。
相続人全員が合意して、遺産分割協議書を作成しますが、これは司法書士など専門家に依頼することもあります。
遺産分割定規書は相続登記の際に必要になります。
現物分割で土地そのものを半分に分ける
遺産相続した土地を、兄弟で分割して相続します。
相続した土地を活用するのも、売却するのも相続した人の自由であるため、各自の判断で対応できます。
ただし、土地の分割時には接道面積(道路に接している面積)、土地の形などに配慮しなければなりません。
土地は、面積さえ同じなら、価値も同じになるというわけではないからです。
兄弟間で納得できるよう、しっかり話し合う必要があります。
代償分割で相続財産の差額を現金調整する
相続において、一人が土地を受け取り、他の相続人が現金や預貯金などを受け取る場合、その価値の差を現金で調整できます。
たとえば、評価額2,000万円の土地と預貯金1,000万円の遺産を兄弟2人が相続する場合、双方に1,500万円ずつの相続権があります。
土地は分割できないため、兄が土地を相続する代わりに、弟に自分の預貯金から500万円の差額を支払って現金で調整すると両者の相続額は公平になります。
ただし、不動産は高額なため、支払う側の負担が大きくなる可能性があるため、分割払いなどの方法を事前に話し合っておくことが重要です。
換価分割で売却金を公平に分配する
どの兄弟にとっても、相続した土地が不要で、誰も住む予定がない場合は、売却して現金で分割することができます。
売却するには、事前に相続登記をしなければなりません。
はじめに、遺産分割協議を行い、売却後に現金で分割することを決めておきましょう。
現金の分け方は遺産相続会議で決定します。
相続登記による土地の名義は一時的なものなので、相続人全員の共有名義でも、代表者1名の名義でも構いません。
また、ローンの残債などがあり、土地に抵当権がある場合も売却できません。
その場合は換価分割できないので注意しましょう。
相続放棄で債務を免れる
相続財産には負債も含まれます。
相続財産を調べて負債が多い場合は、相続放棄も選択肢のひとつです。
相続放棄は相続人が被相続人の一切の権利や義務の相続を放棄することなので、おやが大きな借金を残して亡くなった場合に子どもに債務が残らないというメリットがあります。
ただし、相続放棄をすると、預貯金、不動産などの相続も一切を放棄することになります。
相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。
注意したいのは、その間3ヶ月の間に、被相続人の遺産を少しでも使ってしまうと相続放棄ができなくなる点です。
相続放棄を検討している場合は十分に注意しましょう。
共有名義で土地を相続した場合の対処法3選
共有名義で土地を相続した場合、先ほど紹介した3つの方法とは違った形で売却を進めなければなりません。
共有名義で売却する際の対処法は以下の3つです。
- 兄弟間で共有持分を売買する
- 共有物分割請求訴訟で分割する
- 共有持分のみを専門の買取業者に売却する
それぞれの内容を見てみましょう。
兄弟間で共有持分を売買する
共有名義で相続した土地に関して、兄弟間で共有持分を売買する方法があります。
たとえば、自分の持ち分を兄弟に買い取ってもらうことで土地を現金化することが可能です。
土地を売却したいと考えているが、兄弟が売却に同意しない場合などに有効な方法で、市場価格よりも高値で買い取ってもらえる可能性があります。
第三者との共有よりも兄弟間で単独名義にした方が、管理や将来の処分がスムーズになるからです。
また、買取業者への売却可能性を示すことで、兄弟の買取意欲を刺激できるかもしれないため、現金化の有力な選択肢となるでしょう。
共有物分割請求訴訟で分割する
相続人同士の話し合いがまとまらない場合、土地の分割方法について裁判で決着をつけるという方法があります。
裁判になると、当事者の意見や土地の状況などを考慮して分割方法が決められます。
判決には強制力があり、覆すことは困難です。
そのため、あくまでも裁判は最終手段と考え、裁判に訴える前に当事者同士で話し合うことが望ましいといえるでしょう。
共有持分のみを専門の買取業者に売却する
自分の共有持分のみを専門の買取業者に売却することで、不動産を現金化できます。
共有持分の売買は専門性が高いため、一般的な不動産会社では取り扱いが難しく、適切な価格で売却できないかもしれません。
しかし、専門買取業者なら、豊富なノウハウと実績を生かして、あなたの大切な資産をスピーディーに、そして高額で買い取ってくれます。
アルバリンクは共有持分に強い専門の買取業者です。
弁護士などの士業との連携があるので、すでにトラブルが発生している共有持分も問題なく買い取ることができます。
共有持分の買取は、アルバリンクにご相談ください。
相続した土地を売却して兄弟で分ける際の4つの注意点
土地を売却してから、売却したお金を兄弟で分ける際、トラブルを避けるために注意すべき点があります。
注意点は以下の4つです。
- 最低売却価格を決めておく
- 譲渡所得が生じた場合は税金を支払う
- 相続から3年を超えると特例が利用できない
- 名義変更しないと売却できない
それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
最低売却価格を決めておく
相続した土地を兄弟で分けるために売却する場合、兄弟間で話し合って最低売却価格を決める必要があります。
なぜなら、売却価格で意見が対立することがあるからです。
売却には、兄弟全員の同意が必要なため、トラブルを避けるには事前に最低売却価格を決めておくことが重要です。
最低売却価格は、複数の不動産会社に査定を依頼し、その結果を参考にすると良いでしょう。
査定を依頼する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。
アルバリンクも、無料査定を365日受け付けていますので、遠慮なくご相談ください。
譲渡所得が生じた場合は税金を支払う
共有名義で相続した土地を売却し、利益が出た場合は注意が必要です。
土地を売却して得た利益は譲渡所得として扱われ、所得税の対象となります。
売却価格から購入時の費用や売却にかかった費用を差し引いた金額に対して課税される税金です。
所有期間は、相続した日ではなく、被相続人が取得した日を基準に計算されるため、注意しましょう。
譲渡所得税は譲渡所得に税率をかけて算出しますが、売却不動産の所有期間によって税率が異なります。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
| 税率 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
| 長期譲渡所得税(5年を超える) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得税(5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
相続から3年を超えると特例が利用できない
相続した家を相続開始から3年以内に売却すると、条件に適合すれば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用され、譲渡所得から最大3,000万円が控除される場合があります。
この特例は、空き家問題の解消のためのものなので、被相続人が一人で暮らしていた家を相続した場合の譲渡に限られます。
また、相続から譲渡まで引き続き空き家であったことや、旧耐震基準であること、価格の上限など諸条件があります。
ただ、相続だけでなく、親の老人ホーム入居などのケースも適用範囲となっています。
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
名義変更しないと売却できない
相続した土地を売却するには、親の名義から相続人の名義に変更する相続登記の手続きが必要です。
相続登記を放置すると、土地売却不可や権利関係の複雑化などのトラブル発生の可能性があります。
また、2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料(10万円以下)が発生するようになりました。
参考:東京法務局
売却時に購入者名義に変更するとしても、相続による名義変更は省略できないため、相続税の申告と合わせて同時並行で名義の変更も行いましょう。
なお、子どものいない親類が亡くなって、気づかないうちに自分が法定相続人になっていて相続登記の義務が発生している場合もあります。
法定相続人は以下のような血縁の範囲です。第1順位から始めて、該当する人がいない場合、第2順位、第3順位に相続人の範囲を広げます。
第1順位に該当する相続人がいる場合は、第2順位や第3順位に属する人に相続権が及ぶことはありません。
また、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
| 第1順位:直径卑属 | 子ども 子どもがいない場合は孫 子どもも孫もいない場合は曽孫 |
| 第2順位:直径尊属 | 父母 父母がいない場合は祖父母 |
| 第3順位:傍系血族 | 兄弟姉妹 兄弟姉妹外兄場合は甥姪 |
相続した土地を売却する際の専門家への相談ポイント
相続した土地の売却に不安を持ち場合も多いことでしょう。
そのような場合は、専門家に相談することでスムーズに売却できる可能性があります。
・不動産会社
土地の売却を考えている場合に、多くの場合、まず相談する窓口になるのが不動産会社です。
多くの案件を扱っているので、必要な手続きなどのノウハウを知っています。
ネットなどで相場価格の概算を教えてくれる場合もあります。
・司法書士
司法書士には、法律上の書類を作成したり手続きの代行の専門家です。
遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記の代行、相続放棄の相談、金融機関での相続の手続きなどを依頼できます。
・税理士
土地や預貯金の相続では、高額な相続税を納税しなければならない可能性があります。
そのような場合は、税理士に節税の工夫を相談しましょう。
煩雑な相続税の申告や、譲渡所得税の確定申告の代行も依頼できます。
・弁護士
相続にあたって、相続人同士で意見が一致しない場合や、遺言書に納得できないときは、弁護士に相談しましょう。
弁護士を立てたからと言って必ず裁判になるわけではありません。
円満に話し合いで解決できるように間に入ってアドバイスもしてくれます。
・不動産コンサルタント
相続にあったって、不動産の適正な価格を見極めることは非常に重要です。
特に評価額に影響を与えるような土地の形状がある場合は、不動産コンサルタントなど、不動産の鑑定の専門家の意見を聞く必要がある場合もあります。
不動産会社の選び方
不動産会社を選ぶ際には、必ず複数の業者から査定を取り、兄弟間で納得できる業者を選びましょう。
兄弟間で、意見が分かれてしまった場合は、よく話し合い、「これだけは」という条件を出し合うとともに、第三者に客観的な意見を求めるのも大切です。
その際には、相続物件の取扱件数が多いか、該当不動産の所在地で実績があるか、スタッフが相続についての知識が豊富か、なども重要なチェックポイントです。
司法書士・税理士との連携
相続した土地を売却するには、まず土地の相続登記を行わなければなりません。
相続登記には、遺産分割協議書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の住民票や印鑑証明などさまざまな書類が必要です。
そのほか、預貯金の名義変更、解約など、相続にまつわる手続きには手間暇がかかります。
このような手続きは、すべて司法書士が相続人に代わって行うことが可能です。
また、相続した土地を売却すると譲渡所得税が発生しますが、事前に税理士に相談することで、売却のタイミングも含めて節税対策を行うことも可能です。
司法書士と税理士が連携することで、必要書類や手続きをよりスムーズに行えるでしょう。
兄弟間の意見調整が難しい場合の専門家活用法
相続にあたって、相続人同士で意見が一致せず、意見調整が難しい場合は、当事者だけではなく中立的な第三者を交えて話し合うことをおすすめします。
弁護士に双方の意見を調整してもらったり、不動産コンサルタントに客観的な資料などを提示してもらい、専門家としての第三者的評価を聞く場を設けることは非常に大切です。
兄弟間で揉めないために生前にできる対策3選
土地を相続する際、考え方の違いなどから兄弟間でトラブルが発生する可能性があります。
どうすれば、相続トラブルを回避できるのでしょうか。
ここでは、トラブルを回避するために相続前の生前にできる3つの対策を解説します。
生前に土地を売却する
1つ目の対策として、生前に土地を売却することがあげられます。
不動産を現金化することで、将来的な相続争いの予防や相続税の納税資金の確保といったメリットがあります。
また、時間に余裕をもって売却できるため、高値で売却したり、有利な条件で売却できたりする可能性が上がるのもメリットです。
親が高齢である場合は、肉体的・精神的負担を軽減するため、書類の取り寄せなどのサポートをした方がよいでしょう。
生前贈与する
2つ目の対策として、生前贈与があります。
生前贈与のメリットは、相続をめぐるトラブルを回避できることや贈与をする人も贈与を受ける人も納得しやすいことです。
土地所有者の存命中に話し合いができるため、贈与の意図を説明できる点もメリットとなります。
また、贈与者の認知症リスクへの対策ともなります。
判断能力が低下してしまう前に贈与することで、相続する人が資産を有効活用しやすくなるでしょう。
ただし、必ずしも節税できるわけではない点や、不動産取得税や登記費用、税理士への報酬などの費用がかかる点に注意が必要です。
遺言書を作成する
3つ目の対策として、遺言書の作成があります。
遺言書の効力はかなり強力であるため、不動産をめぐる相続争いの防止にも役立ちます。
しかし、遺言書を書く際は形式を整えなければなりません。
また、遺言書の内容を確実に実行するには、遺言を実行する人(遺言執行者)を指名すると良いでしょう。
まとめ
この記事では、相続した土地をトラブルなく売却する方法をご説明しました。
記事内でお伝えした通り、兄弟が相続した土地をめぐってトラブルを起こさずに済む方法としては、土地の分割や差額分の支払い、土地の売却益の分配などの方法があります。
共有名義で相続してしまった場合でも、不動産業者に依頼することで共有持分だけを売却することが可能です。
経験豊富な業者ほど、希望に沿う形での売却ができるでしょう。
アルバリンクは、共有持分の売却に強い買取業者です。
弁護士などとも連携し、トラブルが発生している物件であっても問題なく買い取っています。
また、物件価値の査定についても強みがあるため、相続した不動産の鑑定を依頼してもよいでしょう。
トラブルを避けつつ、不動産を円滑に相続・売却したい方は、ぜひ一度、アルバリンクに相談してみてはいかがでしょうか。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!









