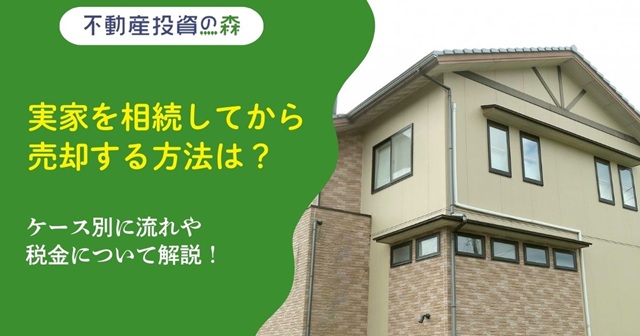亡くなった親の家を売るときの流れと、税金・節税について解説!


「親が亡くなったときに実家はどのように売ればよいのか?」
「家を売るときの税金や節税方法があれば知りたい」
核家族化が進んだ現代では実家を受け継ぐケースは少なく、親が亡くなったあとの不動産について悩みを持つ人は多いのではないでしょうか?
実際、亡くなった家を売却すると譲渡所得税等の税負担がありますが、状況によっては大きく節税できるケースがあります。
本記事では、亡くなった親の家を売るときの流れと税負担、譲渡所得が出たときの節税方法について解説します。
最後までお読みいただくと、親の家の処分で悩むことがなくなり売却を迅速に行えるようになるでしょう。
目次
亡くなった親の家を売る流れ10ステップ
本章では、亡くなった親の家を売る流れについて解説します。
遺言書の有無を確認する
はじめに、被相続人の遺言書の有無を確認します。
仮に遺言書があれば、原則記載内容に従って遺産相続を行います。
遺言書がなければ、相続人間での遺産分割協議が必要です。
相続人・相続財産を確定する
法定相続人の確定と相続財産を確定します。
相続財産の確定には、被相続人の財産と債務のリストアップが必要です。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合に遺産分割協議を行います。
相続人間で話し合いを行い遺産分割協議書を作成します。
ここまで、相続開始後にすみやかに行う手続きです。
相続税の申告・納税をする
相続税の申告と納税を行います。
相続税は、相続開始の日から原則10か月以内に申告と現金納付が必要です。
また、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
相続登記を行う
相続登記を行います。
相続登記とは相続後に不動産の所有権を相続人に移動することで、所有権移転登記とも言います。
相続登記は、2024年4月より義務化されており、仮に怠ると罰則があります。
不動産会社を選定する
売却を依頼する不動産会社を選定します。
不動産会社は3社程度選定し、査定を出すとよいでしょう。
査定額は不動産会社により若干異なることや売却活動で提供されるサービス等を比較しながら、不動産会社を選びます。
売却活動を開始する
不動産会社が売却活動を開始します。
売却活動とは、主に不動産の宣伝、問い合わせ対応、内見予約の取得、住戸案内等です。
不動産会社は、買主が決まるまでこれらを繰り返し行います。
売買契約を締結する
売却活動で買主が決まれば、売買契約の締結です。
売買契約前には、買主より所定の手付金を受領します。
売買契約が終われば、引き渡しに向けた準備を始めます。
決済・物件引渡しを行う
買主より最終金を受領し、決済が終われば物件の引渡しです。
引渡しが完了すると、買主側の司法書士が所有権の移転登記を行います。
また、不動産会社へは成功報酬として仲介手数料を支払います。
確定申告を行う
最後に、確定申告を行います。
売却益があれば譲渡所得税、売却損であれば損益通算と繰り越し控除ができる可能性があります。
特に、譲渡所得税は納税の義務があるので、怠らないように注意します。
相続した不動産の分割方法
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が納得する形で話し合いを済ませることが必要です。
本章では、不動産を相続した場合の分割方法について解説します。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
1.現物分割
現物分割とは、相続した財産をそのままの状態でわける方法です。
たとえば、相続不動産が実家と収益不動産(アパート)で相続人が二人の場合、Aさんが実家、Bさんが収益不動産を相続します。
なお、土地のように分筆ができれば切り分けられるので現物分割が可能ですが、土地の上に建物がある不動産を複数人で分けることは不可能です。
また、分割する不動産が必ずしも同程度の評価額とは限らないため、相続人間での公平性を保つことが難しいでしょう。
2.代償分割
代償分割とは、一人の相続人が不動産を相続した場合、ほかの相続人に対し代償金を支払って遺産を分割する方法です。
たとえば、2,000万円の価値がある実家を兄弟二人で分ける場合、長男が実家を相続すると弟には代償金として2,000万円を支払います。
代償分割は、現物分割と異なり公平性は高いのですが、上記の場合には長男が弟に2,000万円を支払える資力が必要です。
そのため、長男に資力がない場合には利用できない方法となります。
3.換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金化したものを相続人間で分ける方法です。
実際、不動産売却時には仲介手数料等の諸費用が発生するため、これらを売却金から差し引いたものが分割の対象となります。
換価分割の場合、不動産を現金化するので均等に分けやすく、相続人間で揉めるリスクは低いでしょう。
一方で、売却時に売り急いでしまうことで相場より安価になってしまうことや、売値に関して相続人間の話し合いが上手くいかず売却自体が進まない、もしくは頓挫する可能性があります。
また、相続人全員の売却意思も必要となり、一人でも反対する人がいれば換価分割ができないことも注意点です。
4.共有分割
共有分割とは、不動産を分けることなく共有持ち分に応じて各相続人が不動産を所有し続けることです。
相続人間での話し合いのなかで、どうしても決められない場合やそもそも話し合い自体ができていない場合に用いられます。
分割という記載がありますが、実質は不動産を複数の相続人で持ち続けることであり分割行為は行っていません。
亡くなった親の家を売る前の準備
亡くなった親の家をそのままの状態で売ることはできず、予め売却のための準備が必要です。
本章では、これら準備に関する一連の流れをご紹介します。
- 相続登記をする
- 家の物を片付ける
- 購入時の売買契約書を探す
- 隣の家との境界を確認しておく
相続登記をする
相続登記では、親の家の所有権を相続人に移転します。
不動産売却では、所有者本人の意思が必要だからです。
よって、親の家を売る前に相続登記(所有権移転登記)を司法書士に依頼しましょう。
家の物を片付ける
家の中にある家電や家具などの家財用品を撤去します。
仮に、家財用品が残置されていれば買主が処分費用を負担するなど不利益な部分があり、売却の進捗自体に大きな影響があります。
室内にソファーやタンス、テレビや冷蔵庫、日常生活で発生したゴミなどが残置されていれば、売却前に片づけておきます。
なお、自らで片付けが難しい場合には、不用品回収業者などに依頼し撤去することがおすすめです。
購入時の売買契約書を探す
購入当時の売買契約書を探します。
売却後の譲渡所得税の計算のときに取得費として計上でき、節税できるからです。
よって、購入当時の売買契約書や取得費を間接的に証明できる書類(購入代金が記載された通帳や不動産会社が作成した購入当時の価格が記載された書類など)を準備しておきましょう。
隣の家との境界を確認しておく
隣地境界についても確認しておきましょう。
なぜなら、土地境界が決まっていなければ取引自体に公平性を欠き、売却後にトラブルとなる可能性があるからです。
よって、敷地については境界杭の確認、法務局で取得できる地積測量図、境界画定図などがあるかを確認しておきましょう。
亡くなった親の家を売るときに生じる税金3選
本章では、亡くなった親の家を売るときに生じる税金について解説します。
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税
登録免許税
登録免許税は、相続登記のときにかかります。
所有権移転登記でかかる登録免許税は、以下のとおりです。
【建物と土地共通】固定資産税評価額(課税標準)×20/1000(税率)
印紙税
印紙税は、売買契約を締結するときにかかり売買金額により変わります。
| 記載された契約金額 | 税額 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
参照:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置【国税庁】
譲渡所得税
譲渡所得(売却益)が出た場合に譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税率は、毎年1月1日時点の所有期間により変わります。
| 所有期間 | 税率 |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 39.63% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 20.315% |
亡くなった親の家を売るときの節税方法4選
最後に亡くなった親の家を売るときの節税方法について解説します。
- 取得費がわかる資料を探す
- 「相続財産の取得費加算の特例」を利用する
- 「相続で取得した空き家の3,000万円特別控除」を利用する
- 「低未利用地を譲渡する場合の100万円特別控除」を利用する
取得費がわかる資料を探す
取得費がわかる資料を探します。
なぜなら、購入当時の資料などがあれば取得費として譲渡所得から差し引けるものが多くなり、節税につながるからです。
売却前に売買契約時の金額がわかるものを探しておきましょう。
「相続財産の取得費加算の特例」を利用する
取得費加算の特例とは、相続で負担した相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
この特例を利用すると、譲渡所得から差し引ける金額が多く節税になります。
「相続で取得した空き家の3,000万円特別控除」を利用する
譲渡所得から最大3,000万円(相続人2人以下)もしくは2,000万円(相続人3人以上)を差し引けることで、譲渡所得税を節税できます。
なお、空き家の定義や譲渡相手等に制限があるため、利用には税理士等専門家に相談するのがよいでしょう。
「低未利用地を譲渡する場合の100万円特別控除」を利用する
都市計画区域内に所在する一定の未利用地について、土地と建物を譲渡した金額が500万円以下の場合に適用できる制度です。
特例の適用要件を確認して利用します。
参照:低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について【国土交通省】
まとめ
本記事では、亡くなった親の家を売る流れと節税方法について解説しました。
親の家を売るには、相続登記を行い所有者になった時点で売却活動ができます。
また、譲渡所得があり特別控除が利用できれば節税できるので、効果的に利用したいところです。
売却や税金については専門的な部分も多いため、家の売却は不動産会社、税金は税理士など専門家への相談を早めに行うことがおすすめです。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!