一軒家をシェアハウスにしたい人向けの完全ガイド!収益化の秘訣を解説

一軒家を所有しているものの、活用方法が分からず空き家のまま放置していませんか?
一軒家は、シェアハウスにすることで、収益化できる可能性があります。
もちろん、ただ単に部屋を貸せばいいわけではありません。
建築基準法や消防法などの法規制、初期費用や改装コストなど、事前に確認すべき点はたくさんあります。
また、住民同士のトラブルや空室リスクといった、シェアハウスならではの課題も見逃せません。
この記事では、以下のようなポイントを詳しく解説します。
最後まで読むと、シェアハウスで起こりうるリスクに対する具体的な備え方や、収益化に向けた準備の進め方が分かります。
なお、弊社Albalink(アルバリンク)では、シェアハウス運営で高利回りを期待できる物件の情報を、LINEで配信しています。
弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。
物件に関する質問も受け付けているので、ぜひこの機会にご登録ください。
空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
目次
一軒家をシェアハウスにしたい!収益化と合法性は両立できる?
「シェアハウス」と聞くと、個室がたくさんある建物を活用することを想像する方もいるでしょう。
一軒家でも、シェアハウスの運営はできるのでしょうか?
ここでは一軒家を活用したシェアハウス運営について、以下のようなことを解説します。
結論:条件次第で収益化は可能!ただし法規制と初期コストに注意
結論から言うと、一軒家をシェアハウスにすることで、収益化は可能です。
ただし、法的な手続きや初期費用をしっかりと把握しておく必要があります。
特に「寄宿舎扱い」になるか、「用途変更」の手続きが必要かは、収益化の成否を分ける重要なポイントです。
既存の建築物の使いみちを、別の用途に変更すること。一定の条件を満たすと、建築確認が必要になる。
シェアハウスを運営するときは、用途変更に関する行政とのやり取りをしたり、リフォーム費用をはじめとした初期費用が数百万円単位でかかったりするケースもあります。
不動産投資として一軒家を活用する場合は、法律規制や初期コストをよく確認したうえで取り組みましょう。
「立地・物件の状態・管理体制」の設計が収益化のカギ
シェアハウスで収益を上げるには、「立地」「物件の状態」「管理体制」の3つがとても重要です。
いずれも、入居希望者にとっての安心感や、快適な共同生活を送れるかの判断基準になります。
たとえば、駅の近くにある戸建てを改装し、共用リビングやキッチンをおしゃれに整えれば、20〜30代の若年層や外国人からの人気を集められるでしょう。
管理会社に管理を委託して、トラブル対応やルール整備を行うことで、住人同士のトラブルや近隣への迷惑行為を防ぐ体制を整えることも大切です。
「立地」「物件の状態」「管理体制」を整えることで、家賃相場より高めの賃料設定でも満室を維持して、収益性の高い運用を実現できます。
「用途変更の可否」「概算費用」「賃料相場」は必須
シェアハウスの運営を成功させるには、「用途変更の可否」「初期コストの概算」「賃料相場の把握」の3点の確認が欠かせません。
もし用途変更の手続きを怠ると、行政からの指導を受け、営業を停止することになる可能性があります。
参照元:e-gov 法令検索「建築基準法 第八十七条・第九十八条」
また、賃料の相場を正確に把握しておかないと、家賃を高く設定しすぎて空室が続いたり、逆に安くしすぎて収益が出なくなったりするかもしれません。
事前調査で手を抜くと、想定外の費用や収益のズレが発生し、経営が立ち行かなくなるリスクがあります。
シェアハウスを運営するときは、不動産業者や専門家と連携して、しっかりとした計画と事前調査を行いましょう。
一軒家をシェアハウスにする3つのメリット
一軒家をシェアハウスとして活用することで得られるメリットは、主に以下の3つです。
- 空き家を収益物件に転用できる数少ない手段
- 初期投資を抑えながら始められる不動産投資として注目
- 賃料シミュレーションで高利回りが見込めるケースも
一軒家を活用したシェアハウスは、建物の構造や内装を整備し、必要な備品を揃えるだけで運用を開始できます。
建物を一から建てる必要はないため、初期費用を抑えながら不動産投資を始められるのもメリットです。
近年の日本では、空家数の増加が問題になっているため、社会問題に貢献しながら収益化を目指せるでしょう。
また、設定した賃料の金額によっては、高利回りが見込めるケースもあります。
空き家の有効利用や収益の最大化、地域社会への貢献など、一軒家のシェアハウス運営にはさまざまな魅力があります。
一軒家のシェアハウスが数百万円の利益に?【シミュレーションが重要】
一軒家のシェアハウス運営は、賃料や初期費用によっては年間の収益が数百万円になることもあります。
ここでは、一軒家のシェアハウス運営の利益について、次のようなことを紹介します。
【収益例】家賃5万円×4部屋=月20万円 (年間240万円)
一軒家をシェアハウスにすることで、月20万円、年間240万円もの家賃収入を得られる場合があります。
たとえば、戸建てを個室4部屋に分けた場合、1部屋あたり家賃5万円で賃貸すると、4人の入居者から合計で月20万円の収入が発生し、年間の収益は240万円になります。
戸建て賃貸は1つの家庭に建物をまるごと貸すため、賃料収入は限られていますが、シェアハウスの場合は部屋と入居者の数だけ賃料収入が見込めます。
都市近郊や駅の近くであれば、シェアハウスの需要が高いため、より安定した収入源になるでしょう。
「シェアハウスが儲かるのか」については、こちらの記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

実質利回りは初期投資やランニングコストを含めても「10~20%」も可能
一軒家をシェアハウスとして運用することで、初期費用や管理コストを考慮しても、実質利回りが10〜20%に達することがあります。
たとえば、リフォーム費用として300万円、備品に100万円を投資した場合、合計400万円の初期コストが発生します。
年間家賃収入が240万円であれば、単純計算で約2年以内に初期費用を回収することが可能です。
初期費用を回収した後は、管理費や修繕費などのランニングコストを差し引いても、実質利回り10%以上を維持できるケースもあります。
収益性を重視した運用を検討している方にとって、一軒家のシェアハウス運営は、とても魅力的な選択肢といえるでしょう。
収益化したいなら収益シミュレーションしてみるのが第一歩
一軒家のシェアハウス運営で収益化を目指すなら、まずは収益のシミュレーションを行うことをおすすめします。
なぜなら、費用や賃料、稼働率などの予測が曖昧なままだと、期待通りの利益が出ないリスクが高まるからです。
次のような費用を加味した計画を立てると、具体的な年間収益・実質利回り・投資回収期間を把握できます。
- リフォーム費用
- 家賃設定
- 入居率
- 管理コスト
- 修繕費
- 固定資産税
無料の収支シミュレーターや不動産ポータルサイトにあるツールを使えば、簡単に試算することも可能です。
本格的にシェアハウス運営を検討する段階になったら、経験のある業者や専門家に相談しながら、できるだけ現実的なシミュレーションを行いましょう。
こちらの記事では、不動産投資のときに役立つ「収支計画書」の作り方を解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
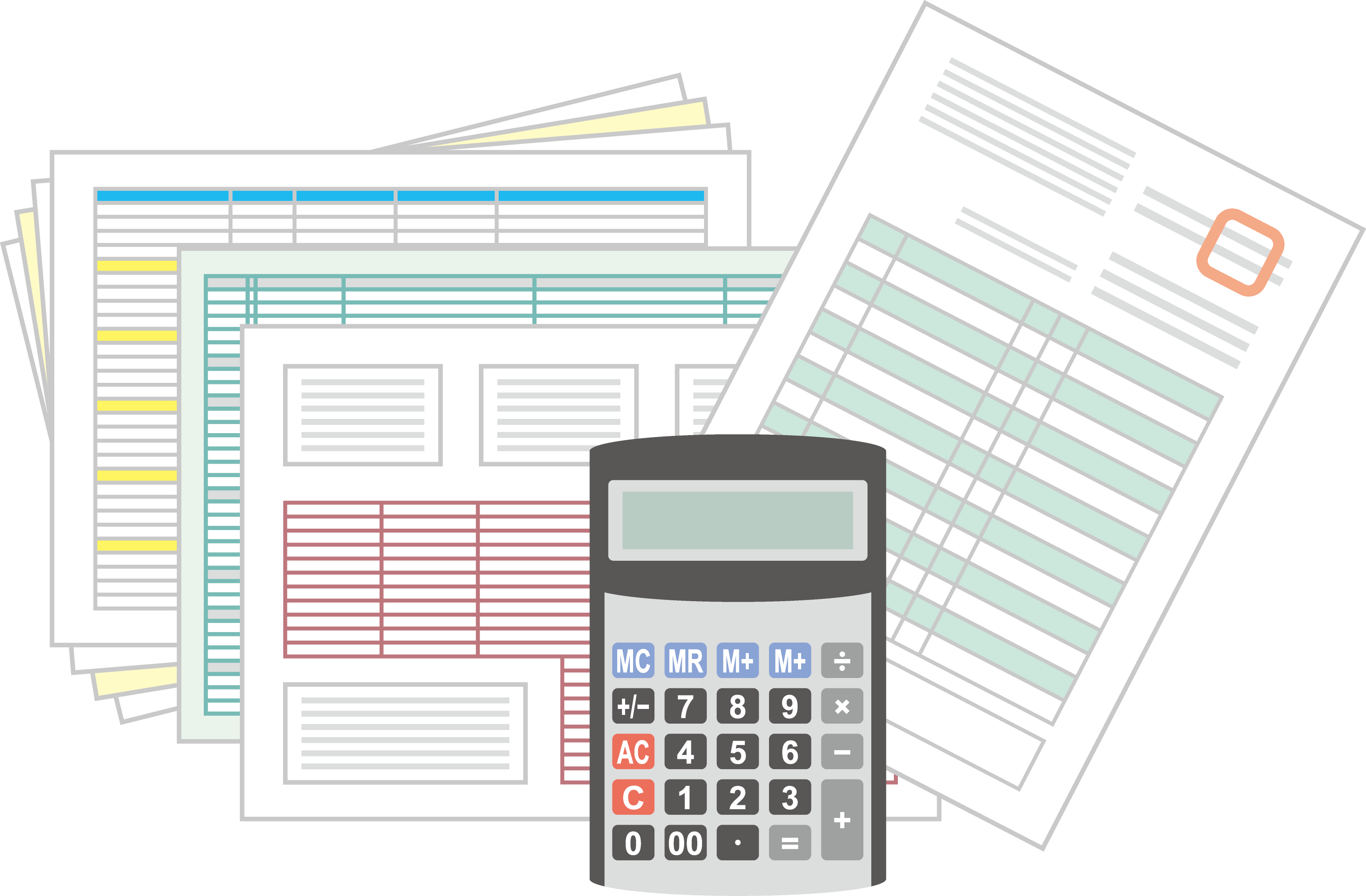
一軒家をシェアハウスにする際に知っておくべき法規制
シェアハウスの運営をする場合、建築基準法や消防法といった法律が関わってくる可能性があります。
一軒家をシェアハウスにする際に知っておくべき法規制は、以下のとおりです。
シェアハウスの運用に関する法的リスクについては、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

「建築基準法・消防法・用途変更」の要否を確認
一軒家をシェアハウスとして運用するときは、「建築基準法」「消防法」「用途変更の要否」を確認しましょう。
たとえば、戸建て住宅を複数人での共同生活用に転用する際、居住形態が「寄宿舎」と見なされることがあります。
参照元:e-gov 法令検索「建築基準法 第二条・第八十七条」
「寄宿舎」と見なされると、建築基準法上の「用途変更」が必要になり、消防設備の設置を義務付けられるケースもあります。
法律による規制を無視すると、行政指導や営業停止のリスクがあるため、必ず守るようにしましょう。
物件を選ぶ段階で「建物の構造」「間取り」「改修の可否」などを専門家に相談し、法規制に適合する計画を立てることが重要です。
「旅館業法」に当たらないか所轄の保健所に確認
一軒家をシェアハウスとして貸し出す場合、「旅館業法」に抵触しないかを、所轄の保健所に確認する必要があります。
なぜなら、用途によっては、旅館業の許可が必要になる可能性があるためです。
たとえば、「1泊単位」で不特定多数に部屋を貸す場合、「宿泊施設」と見なされ、旅館業の営業許可が必要になります。
旅館業法への抵触を防ぐには、「居住目的」で「長期的な賃貸契約」を交わすことが一般的です。
基本的には、1ヶ月以上の定期賃貸契約で、住人が生活の拠点として使用する場合には、旅館業法の対象外になります。
契約期間が定められており、期間満了で契約が自動更新されずに終了する賃貸借契約のこと
ただし、判断基準が曖昧なケースもあるため、必ず地域の保健所や専門家への事前確認を行うようにしましょう。
一軒家をシェアハウスにする際の初期費用【補助金や融資も使える】
一軒家をシェアハウスにするとき、初期費用はいくらかかるのでしょうか。
ここでは補助金や融資の活用も含め、一軒家をシェアハウスにする際の初期費用について、次のようなことを解説します。
改装やリフォーム費用は「100〜500万円」
一軒家をシェアハウスにするには、改装やリフォームなどの初期費用が発生します。
初期費用の金額の目安は、一般的に100万円〜500万円程度です。
たとえば、築年数が経過している戸建てをシェアハウスにリノベーションする場合、個室を増設しつつ共用キッチンやリビングも整備しなければなりません。
間取りの変更、内装の修繕、水回りの交換などを行えば、費用は一気に300万円を超えることもあるでしょう。
また、シェアハウスを運営するときに使う備品の購入費も考慮する必要があります。
地域や物件の状態によって価格は大きく異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、初期費用の相場を比較することが重要です。
「エアコン・鍵付きドア・水回り」にコストがかさむ
シェアハウスの初期工事で特にコストがかかるのは、エアコンの設置、鍵付きドアの導入、水回り(トイレ・浴室・キッチン)の整備です。
たとえば、各部屋にエアコンを設置する場合、1台あたり約8万〜15万円、4部屋で40万円以上の負担が見込まれます。
また、個室ごとに鍵を取り付ける工事費や、老朽化した浴室・トイレ・キッチンの交換工事も必要となれば、それぞれ数十万円単位の出費が発生するでしょう。
快適さとプライバシーの確保を両立することで、入居者が集まりやすくなります。
安心して長く住んでもらうため、必要な設備投資を惜しまないことを心掛けましょう。
「空き家活用補助金」や「賃貸住宅向けローン」を検討しよう
初期費用をすべて自己資金でカバーするのが難しい場合は、「空き家活用補助金」や「賃貸住宅向けローン」の活用を検討すると良いでしょう。
たとえば、大阪府大阪市では「空家利活用改修補助制度」を用意しており、最大で300万円の補助を受けられます。
参照元:大阪市「空家利活用改修補助制度」
また、金融機関が提供する賃貸住宅向けローンでは、改修費や物件の購入費が対象になるプランがあります。
参照元:りそな銀行「アパート・マンションローン(個人のお客さま)」
制度の内容は、自治体や金融機関によって異なるため、窓口に問い合わせることをおすすめします。
一軒家をシェアハウスにした際の3つのリスクと注意点
うまく運用すると高利益を見込めるシェアハウス運営ですが、場合によっては運用に疲れたり失敗したりする可能性があります。
一軒家をシェアハウスにした際のリスクと注意点は、主に以下の3つです。
住民同士の人間関係トラブル
一軒家をシェアハウスにするとき、特に発生しやすいのが、住民同士の人間関係によるトラブルです。
共同生活の性質上、生活リズムや価値観の違いがストレスや摩擦につながることがあります。
入居者同士のトラブルを防ぐには、入居前にしっかりとルールを定めて共有し、入居者同士のコミュニケーションを促す工夫が求められます。
また、管理会社に委託し、トラブル発生時の対応窓口を明確にしておくことのも良いでしょう。
シェアハウスの魅力である「交流の場」を快適に保つには、トラブルの防止策を入念に計画する必要があります。
規約違反や行政指導の可能性(無届運営・違法改装など)
一軒家をシェアハウスとして運営するとき、無届での用途変更や違法な改装などにより、行政指導を受けるリスクがあります。
建築基準法に基づいた「用途変更」を行わずに寄宿舎として運営したり、消防法に反した構造変更をしたりすると、営業停止命令が出されるかもしれません。
ルール違反が発生すると、せっかくの収益性が一気に崩れてしまいます。
シェアハウスの運用を始める前に、必ず所轄の自治体や、建築士・行政書士など専門家に相談し、必要な手続きや申請を漏れなく行うことが重要です。
空室時の「収支悪化」と「再販しづらさ」
シェアハウスの経営リスクとして、空室が発生したときの「収支悪化」と「再販の難しさ」が挙げられます。
たとえば、4人入居する想定で家賃収入が月20万円になる計画のはずが、空室が2部屋あると収益が月10万円減少し、ローン返済や維持費で赤字になるかもしれません。
また、個室ごとにリフォームされたシェアハウス仕様の物件は、一般の戸建て住宅よりも「再販価値」が低く評価される傾向にあります。
不動産市場でも流通性が低いため、売却できるまで時間がかかるでしょう。
「収支悪化」と「再販しづらさ」を防ぐには、ニーズの高いエリアを選定したり、運用を始める前の段階で出口戦略を検討したりしておくことが大切です。
シェアハウスとして運用した物件の出口戦略については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

一軒家でシェアハウス運営を成功させる6つのコツ
一軒家のシェアハウス運営には、入居者同士のトラブルや収益悪化などのリスクがありますが、ポイントを抑えることでスムーズに運営できるようになります。
今回紹介する、一軒家でシェアハウス運営を成功させるコツは、以下の6つです。
1.「立地」と「ニーズ」をマッチさせる
シェアハウスの運営を成功せるには、物件の「立地」とターゲットとなる入居者の「ニーズ」を合致させることがとても重要です。
たとえば、大学や企業が集まる駅近のエリアにある一軒家を活用したシェアハウスは、学生や若手社会人のニーズと一致し、高い入居率を維持できるでしょう。
アクセスの良さや近隣環境が充実しており、家具付き・家電完備ですぐに住めるようにしておくと、さらに人気は高まります。
地域の傾向や需要をしっかりと分析したうえで物件を選び、安定した家賃収入につなげましょう。
2.シェアハウス専門の管理会社を選定する
シェアハウス運営では、通常の賃貸以上にトラブル対応や住人管理が重要になるため、専門の管理会社と提携することをおすすめします。
たとえば、入居者同士のトラブルや退去時の対応、共用部の清掃や設備の不具合などは、専門の管理会社に依頼した方がスムーズに処理できます。
ルールやマナーの周知、リビングやキッチンといった共用スペースの管理は、第三者の関与があることで安心感が高まるでしょう。
専門の管理会社に委託すれば、オーナー自身が現場対応する手間が省けるだけでなく、入居者との良好な関係も維持しやすくなります。
3.収支を事前にシミュレーションする
収益性を確保するには、事前の収支シミュレーションが欠かせません。
次のような項目を具体的に数値化し、実際の収益を見積もりましょう。
- 初期費用
- 運用コスト
- 家賃設定
- 稼働率
- ランニングコスト(固定資産税・修繕費など)
たとえば、「リフォーム費用が300万円、家具家電に100万円、家賃収入が月20万」のような仮定をすれば、何年で投資を回収できるかが明確になります。
計画的に収支を把握し、経営を安定させましょう。
4.運営ルールを明確に決める
シェアハウスでは複数人が共に生活するため、「運営ルール」を明確にしておくことがとても重要です。
具体的には、次のようなルールを決めておくと良いでしょう。
- 共用スペースの掃除当番
- ゴミ出しのルール
- 冷蔵庫や洗濯機の使用時間
日常生活に関わる項目を具体的に文書化して共有することで、入居者同士の摩擦を防げます。
加えて、入居時にルールへの同意書を取り交わすことで、トラブル発生時の対応もスムーズに進められるでしょう。
安心して暮らせる環境を作るため、ルールはしっかりと作っておくことが大切です。
5.運用代行サービスを活用する
オーナーが本業を持っていたり、遠方に住んでいたりする場合は、運用代行サービスの活用を検討すると良いでしょう。
運用代行サービスでは、シェアハウスの日常管理から入居者対応、清掃・設備点検までを一括して任せられます。
SNSやポータルサイトを活用した入居者募集をサポートする業者もあり、空室リスクの低減にも効果が期待できます。
参照元:株式会社イエノルール
運用代行はコストがかかりますが、効率的な運営体制を築きたいときは、ぜひ利用を検討してみてください。
6.シェアハウス運営の専門家に相談する
これから一軒家をシェアハウスにしたいと考えている場合、まずはシェアハウスに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
シェアハウス運営の専門家に相談すると、次のようなアドバイスがもらえます。
- 法規制の確認
- 用途変更の可否
- 物件の選定基準
- ターゲット設計
- 初期費用の見積もり
- 行政手続き
- 補助金制度
特に、行政手続きや補助金制度に関する最新情報は、自力で調べるには限界があります。
不動産投資としての成功を目指すなら、スタート時点から正しい方向性を持つことが重要です。
失敗を避けたい場合は、ぜひ専門家の意見を取り入れてみてください。
シェアハウス用の戸建てを探すなら弊社LINEで最新情報をチェックしよう!
シェアハウス運営に最適な一戸建て物件をお探しの方は、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)のLINEをご活用ください。
シェアハウスに向いている一戸建ての情報を、随時配信しています。
物件に関する質問や、運営の相談も受け付けているので、どのような物件があるか気になる方は、ぜひこの機会にご登録ください。
一軒家シェアハウスの成功事例と失敗事例【実例を紹介】
シェアハウスを始める前に、実際に一軒家シェアハウスを運営している人の体験談を知ることはとても大切です。
今回は、以下の2つの実例を紹介します。
成功例:家族や入居者と一緒にシェアハウスで楽しい生活を実現
まず紹介するのは、シェアハウスを自宅としても活用しているDさんの事例です。
Dさんは、自身もシェアハウスに入居していた時期があり、2024年6月に自分で運営するシェアハウスをオープンしました。
収益は副業程度で、部屋がすべて埋まっている場合は、家族の家賃分くらいは黒字になっているそうです。
現在は家族だけでなく、入居者と一緒にシェアハウスに住み、楽しく賑やかな生活を送っています。
参照元:note だいきち🏠シェアハウス大家「家族で住めるシェアハウスを立ち上げたので諸々書きます。」
失敗例:入居者トラブルへの対応が大変
続いて紹介するのは、入居者トラブルで大変な経験をしたKさんの事例です。
Kさんはシェアハウスの入居者を探すとき、入居条件に合わない人を入居させてしまい、クレーム対応に追われたそうです。
その入居者が住み始めてからは、備品に関するクレームが何度も寄せられたり、他の入居者とのトラブルを起こされたりしました。
加えて、入居を検討している人が内見に来ても、その入居者が原因で契約を見送られることもあったそうです。
最終的にはKさんが退去依頼を出し、その入居者は転居先に移り、問題は解決されました。
参照元:トチカム「シェアハウス運営の失敗談!入居者トラブルの実例を紹介(カワマン氏)」
一軒家をシェアハウスにする5つの流れ
一軒家をシェアハウスにするときは、以下の流れで手続きや作業を進めます。
1)コンセプトとターゲットを決める
シェアハウスの運営に取り組むことを決めたら、初めに「どんな住人に、どんな生活を提供するか」を明確にします。
物件の特徴と地域性を活かしてターゲットを絞ることで、魅力あるシェアハウスにすることができます。
具体的には、次のようにコンセプトやターゲットを決めると良いでしょう。
- 女性専用で防犯対策が万全
- 趣味でつながるコミュニティ型
- 外国人向けの国際交流コンセプト
コンセプトやターゲットが決まると、家具・家電の選定の方向性も定まりやすくなります。
入居希望者とのミスマッチを減らせるのもメリットです。
まずは明確なコンセプトやターゲットを描き、プランに基づいた物件探しと運営準備を進めましょう。
2)物件の用途変更や法的確認を行う
一軒家をシェアハウスにするときは、用途変更や法律面の確認を行いましょう。
シェアハウスでは、部屋数や共用スペースの構造によっては、防火扉や非常用照明などの追加工事が求められることがあります。
用途変更や法律面の確認を怠ると、行政指導を受けたり、営業を停止することになったりするかもしれません。
設計段階から専門家に依頼し、行政と連携しながら適法性のチェックを進めましょう。
3)改装・備品の準備をする
続いて、入居者にとって快適な空間を提供できるよう、内装の改装と生活に必要な備品の準備を進めます。
具体的な準備の内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 部屋ごとにエアコンを設置する
- ドアは鍵を取り付けてプライバシーを確保する
- 冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器などの家電を用意する
- 水回りをきれいにする
- 防音対策を施す
備品や内装にかかるコストを節約し過ぎると、入居者満足度が下がり、空室率の増加やトラブルにつながります。
快適な共同生活を支える空間設計を意識し、住まいとしての質を高めましょう。
4)賃料を設定し、入居者募集を開始
設備が整ったら、次は家賃を決定し、入居者の募集を開始します。
家賃は地域の相場や設備の充実度、コンセプトに応じて設定しましょう。
たとえば、駅が近くにあり、でインターネット・家具・家電付きのシェアハウスなら、相場よりやや高めでも需要が期待できます。
アクセスがやや不便なエリアでは、共用スペースの魅力や光熱費込みの料金設定など、差別化が求められます。
入居者募集は、ポータルサイトの活用やSNS、LINE公式アカウントの案内など、さまざまな方法を併用すると良いでしょう。
写真や間取りの見せ方も工夫し、理想のターゲット層に響く情報を発信することが大切です。
5)管理体制(自主管理or外注)を決める
最後に、運営は自主管理で進めるのか、管理会社や運用代行に委託するのかを明確にしましょう。
自主管理はコストを抑えられる反面、入居者対応・清掃・契約管理などに手間と時間がかかります。
一方、外注すれば手間は軽減されますが、その分費用が発生します。
管理費用の目安は、月額家賃の5~10%です。
管理体制の選択は、大家さん自身のライフスタイルや、保有物件の規模に応じて判断しましょう。
自分に合ったスタイルで、安定した経営を目指すことが重要です。
一軒家のシェアハウスは誰がターゲット層になる?【差別化しよう】
一軒家のシェアハウスは、具体的にはどのような人がターゲットになるのでしょうか。
ここでは、一軒家のシェアハウスのニーズが見込める層や、差別化のポイントを解説します。
「学生・外国人・地方転勤者・福祉系支援ニーズ」が高い
一軒家のシェアハウスは、特定のニーズを持つ層に対して非常に高い訴求力を持ちます。
とくにターゲットになりやすい層は、次のとおりです。
- 学生
- 外国人
- 地方からの転勤者
- 生活支援が必要な人
たとえば、都心部の大学周辺では、周辺の家賃相場より安く、家具・家電付きの個室を提供すると、学生向けのシェアハウスの需要が期待できます。
英語対応や国際交流の場を設けた物件は、外国人からの注目を集められるでしょう。
さらに、自治体の福祉政策と連携し、住宅確保要配慮者(高齢者・障がい者・ひとり親など)向けの支援付きシェアハウスを運営するのもひとつの方法です。
入居者の属性や状況を的確に見極めて、それに合わせた運営計画を立てましょう。
「菜園付き」「女性専用」「英会話」などコンセプトで差別化も効果的
競合と差別化を図るには、シェアハウスに「明確なコンセプト」を持たせることが重要です。
たとえば、敷地に菜園スペースを設けた自給自足型のシェアハウスは、自然志向の入居者に人気です。
また、防犯設備を強化した「女性専用」の一軒家や、英会話イベントを定期開催する「英語学習特化型」なども注目を集めやすいでしょう。
内装デザインや備品の選定も工夫することで、他の物件との差別化が可能です。
地域や物件の特徴を活かした個性的なプランで、ターゲット層に響くシェアハウスを目指しましょう。
ターゲット次第で設備投資やルール設計に変化を!
導入する設備を検討したり、入居ルールを作ったりするときは、ターゲットに合わせて柔軟に変化させることを心掛けましょう。
たとえば、外国人ターゲットであれば、多言語対応の案内資料やインターネット環境の充実化を優先して行うことをおすすめします。
学生をターゲットの中心にするなら、共用リビングを学習や交流の場として活用できるよう設計するのも良いでしょう。
共用スペースの使い方やゴミ出しの方法なども、住人の属性に合わせて調整することが求められます。
誰に住んでもらいたいかを明確にすることで、不要なコストの発生や運営方針の無駄を省き、効率的なシェアハウス経営が実現できます。
まとめ
一軒家を活用してシェアハウスを経営するときは、立地や物件の状態、管理体制をしっかり設計すれば、初期投資を抑えつつ、安定した家賃収入を得ることができます。
ただし、建築基準法や用途変更の確認、消防設備の設置など、法的な手続きを怠ると、トラブルが発生するかもしれません。
人間関係のトラブルや、空室による収支の悪化にも注意しましょう。
シェアハウス運営のリスクを抑えるには、高利回りが期待できる物件を選ぶことが大切です。
訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)では、高利回りを期待できる物件や、シェアハウスに向いている一軒家の情報をLINEで配信しています。
物件に関する相談や質問も受け付けているので、どのような物件があるか気になる方は、ぜひこの機会にご登録ください。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!








