定期借家契約とは?大家さんが知っておきたい注意点
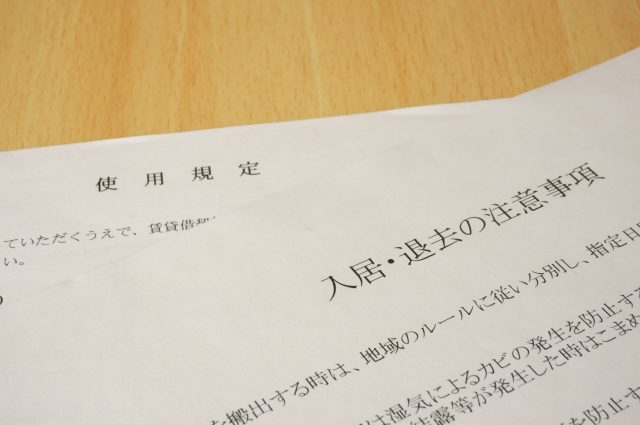
こんにちは。仙台で小さなアパートを経営しているhayasakaです。
前回記事「賃貸物件の立ち退き料の相場と交渉方法について」で、「立ち退き交渉」の難しさと、揉めた場合の経済的ダメージの大きさを解説しましたが、実はこれを回避できる有効な手段が存在します。
それは、2000年に施行された「定期借家契約」です。
定期借家契約は、あらかじめ入居期間を決めて契約を締結し、期間満了の時点で契約が終了する(更新しない)契約です。
定期借家契約を結んでおけば、厄介な立ち退き交渉に巻き込まれる心配はなくなります。
もちろん、入居者と大家さんが合意すれば、再度契約を締結して住み続けてもらうことも可能ですし、再契約の時点で家賃を改定することもできます。
定期借家契約は、大家さんにとってメリットが多い制度ですが注意点もあります。
今回は、大家さんにとっての定期借家契約のメリットや注意点などについて学んでいきましょう。
空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
目次
定期借家契約の基礎知識
定期借家契約と普通借家契約の違い
賃貸契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は、期間を定めずに契約を結ぶもので、入居者の立場を手厚く保護するものになっています。
これは、戦後の住宅不足の時代に作られた「借地借家法」に基づくもので、たとえ家賃の滞納など、入居者に落ち度があったとしても、簡単に契約を解除できません。
しかし、住宅不足が解消されるに従い弱者である借主保護という当初の意義は薄れ、むしろ借地借家法を逆手にとって、家賃を滞納する者や法外な立ち退き料を要求する者さえ生み出してしまいました。
また、土地や建物を貸すと半永久的に戻ってこない制度では、不動産の有効活用という観点から弊害が懸念されました。
そこで、大家さんの立場にも配慮した制度として、2000年の借地借家法改正で「定期借家契約」が創設されました(借地借家法第38条)。
参照元:e-GOV法令検索|借地借家法
普通借家契約と定期借家契約の違いは次の通りです。
| 普通建物賃貸借契約 | 定期建物賃貸借契約 | |
| 1. 契約方法 | 書面・口頭いずれも可 | 1.「更新がなく、期間の満了により終了する」旨を契約書案とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない 2.公正証書など書面での契約が必要 |
| 2. 更新の有無 | 有 ※更新には合意による更新と法定更新がある | 無 ※ただし、合意による再契約は可能 |
| 3. 契約期間の上限 | 1.2000年3月1日より前の契約は20年 2.2000年3月1日以降の契約は無制限 | 無制限 |
| 4. 1年未満の契約 | 「期間の定めのない賃貸借契約」とみなされる | 1年未満の契約も有効 |
| 5. 賃料の増減 | 第32条(賃料増減額請求権)の規定による。 ただし、一定の期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めにしたがう | 特約がある場合、特約の定めに従う ※第32条の規定は適用されない |
| 6. 借主の中途解約の可否 | 中途解約に関する特約がある場合には、その定めに従う | 1.床面積200㎡未満の居住用建物については、借家人が、転勤、療養、親族の介護等のやむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、借家人の方から中途解約の申入れをすることが可能(申入れ後1か月の経過により賃貸借契約が終了) 2.1以外の場合は途中解約に関する特約があればその定めにしたがう |
参照元:定期借家契約|国土交通省
定期借家契約は、賃貸人の立場に配慮し、賃借人を手厚く保護し過ぎた普通借家契約を修正した内容となっていることがわかります。
定期借家契約のメリットと注意点
定期借家契約のメリット
改めて定期借家契約のメリットをまとめてみましょう。
不良入居者との契約を解消できる
家賃の滞納やごみ出しのルールを守らない、夜中に騒いで近隣に迷惑をかけるなど、不良入居者がいる場合、期間満了をもって契約を終了できます。
契約時点でどのような入居者かを判断することは難しく、入居後に不良入居者だと気づいても普通借家契約だと契約解除は困難です。
この点、定期借家契約であれば、契約を更新しなければ賃貸借契約は終了します。面倒な立ち退き交渉や立ち退き料も発生しません。
また、更新のタイミングで優良な入居者だけ再契約できるため、アパート全体の風紀や環境が保たれるメリットも期待できます。
家賃の改定もスムーズ
普通借家契約では、家賃の値上げをしようとしても、入居者との合意が難しい傾向にあります。
一方、定期借家契約であれば、当初の契約満了時に「再契約に関する賃料等の条件」という形で家賃を改定することも可能です。
もし入居者が改定後の家賃に同意できなければ、契約を更新せず新たな入居希望者を募集することができます。
ただし。これからの人口減少・家余り時代を考えると、安易な家賃の値上げは難しくなると思われます。
とはいえ、最寄り駅周辺の再開発や近くに大型のショッピングセンターができるなど、生活利便性の向上や住環境の改善によって家賃相場が上昇する可能性もあります。
そういった状況でも、定期借家契約であれば家賃改定にも対応しやすいでしょう。
契約期間は自由
定期借家契約では、契約期間を自由に設定できます。
極端な話、1週間や1カ月という契約も可能な一方、5年、10年という長期間の契約でも問題ありません。
たとえば、まだ就職が決まっておらず収入が不安点な若者や外国人には1カ月の契約で様子を見て、就職が決まった後に1年契約を結ぶという方法もあり得ます。
また、5年後に建て替えを計画している場合は、5年契約を締結しておけば、立ち退き交渉の必要はなく、取り壊し間近まで家賃収入を得ることも可能です。
定期借家契約の注意点
一方、定期借家契約には注意点もあります。
重要事項説明書とは別の書面による契約
定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により契約が終了する旨を明記した書面で契約しなければなりません。
公正証書が望ましいですが、要件を満たせば通常の書面でも構いません。
なお、宅建業法で定める「重要事項説明」とは別の手続きであり、重要事項説明書とは別の書面で定期借家契約を交わす必要があります。
説明義務
書面の内容を賃借人に対し口頭で説明する義務もあります。
原則として、賃貸人である大家さん自身が説明すると規定されていますが、実務上は仲介する不動産会社が説明するケースが多いようです。
この場合、家主の代理人である旨を証明した書面を用意しておくことがポイントです。
これを怠ると、裁判上の争いになった場合、「説明がなされていないため普通借家契約」と判断される可能性があります。
あくまでも家主もしくはその代理人が、書面と口頭で定期借家契約であることを説明しなければ、普通借家契約と判断されるということです。
契約満了の予告
契約期間の満了が近づいてきたら、満了日の1年~6カ月前までに、賃貸借契約が満了することを通知する必要があります。
これは、賃者人が再契約や代替となる建物を探すための準備期間を確保できるようにするためです。
予告通知がない場合、契約が満了しても立ち退きを求めることはできません。
ただし、この規定は、契約期間が1年未満の定期借家契約では適用されません。通知なしでも期間満了で契約を終了できます。
とはいえ、入居者は次の物件の契約や引っ越し準備が必要なため、3カ月前ぐらいには通知してあげた方が余計な混乱を回避できるでしょう。
定期借家契約に切り替える方法
普通借家契約を結んでいる場合
賃借人にとって、普通借家契約を定期借家契約に切り替えるメリットは基本的にありません。
特に、借地借家法によって賃借人の権利が守られていることを知っている入居者にしてみれば、手厚く保護されている権利を自ら手放すことはないでしょう。
ただし、このような場合でも、契約時期によっては定期借家契約への切り替えを求めることが可能です。
この点、法律上、「定期借家契約が施行される前(2000年2月末日まで)に締結された普通借家契約は、定期借家契約に契約し直すことはできない」ことになっています。
いわゆる「法の不遡及の原則(新しい法律は、改正前に遡って適用されないという原則)」です。
反対に、2000年3月以降に締結された普通借家契約であれば定期借家契約への切り替えを求めることは可能ということになります。
ほとんどの入居者は、ルールを守らず住環境を悪化させる不良入居者には出て行ってもらいたいと考えるでしょう。
不良入居者がいつまでも居つくのを阻止し、良質で快適な環境を保つことを目的に定期借家契約に切り替えることを説明すれば、理解してくれる入居者は少なくないはずです。
新規契約の場合
新規契約の場合は、定期借家契約で進めるべきです。
ルールを守らない入居者が居つくのを阻止するための契約方法である旨を説明し、より良い住環境を維持する姿勢を示すことで、物件の付加価値として役立てることも可能です。
まとめ
大家さんにとって、極めて厄介な「立ち退き交渉」を回避する切り札となるのが定期借家契約です。
立ち退き料を支払うことなく、スムーズに契約を終了できます。
また、不良入居者に悩んでいる大家さんはもちろん、建て替えや他の土地活用を考えている場合にもおすすめの契約形態です。
注意点としては、重要事項説明書とは別に、定期借家契約の内容を明記した書面を用意し、大家さん自身もしくは代理人(代理権を証明する書面も必要)が、口頭で説明することです。
また、契約満了の1年~6カ月前までに契約満了の通知を行う必要があります(契約期間が1年以上の場合)。
既に普通借家契約を結んでいる場合でも、契約締結時期が2000年3月以降であれば定期借家契約への切り替えを求めることができます。
その場合、入居者に対して、あくまでもルールを守らない入居者が居つくのを阻止するための施策で、より良い住環境を維持していく狙いを説明することがポイントです。
大家さんにとってメリットが多い定期借家契約ですが、国土交通省の調査によると、驚くことに定期借家契約の利用割合はわずかに2.1%に過ぎません。
実にいまだに98%は普通借家契約で行われており、まだまだこの制度を知らない・活用していない大家さんが多いというのが実態です。
これから大家さんを目指す皆さんは、定期借家契約を上手に活用して、退去にまつわる不毛なトラブルを賢く回避していくべきでしょう。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!








