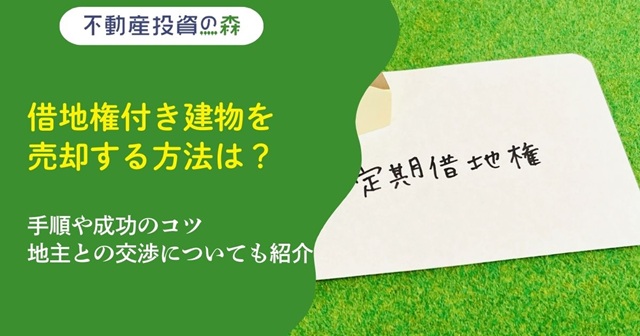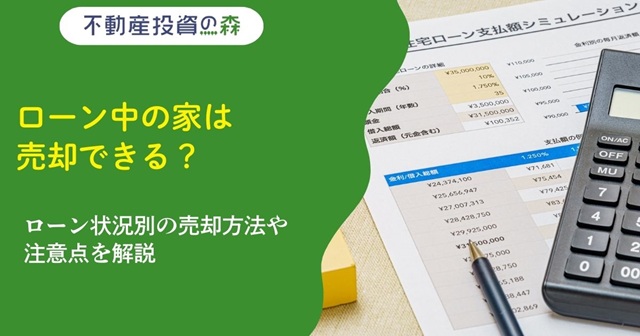親の死後の家、売れない本当の原因と最適な処分法とは?
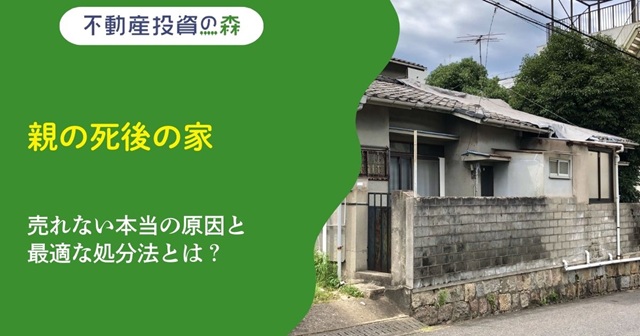
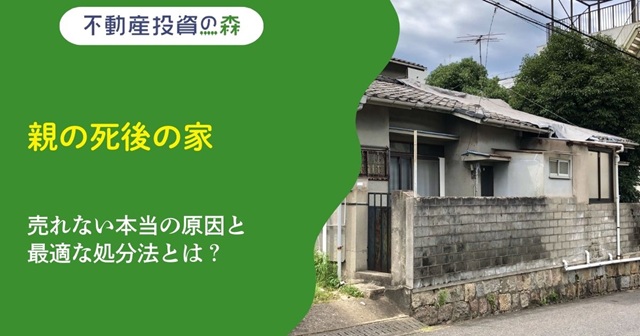
「親が亡くなり実家を相続したものの、使う予定はない。早く処分したいが、思うように売れない」。こんなケースで悩んでいる人も少なくありません。
本記事では、実家が売れない理由やそのリスク、具体的な処分方法を詳しく解説します。早期に解決したい方はぜひ参考にしてください。
目次
親の死後の家を処分するまでの流れ
親が亡くなってから、相続した家を処分するまでの一般的な流れを紹介します。
| 1. 死亡届を提出する | 死亡を知ってから7日以内。相続が開始する。 | |
| 2. 遺言書の有無を確認。相続人を確定し、 遺産分割の方針を決める | 遺言書がある場合は家庭裁判所に検認を申請(数週間から2ヶ月間必要) 相続放棄は3ヶ月以内。相続税申告は10ヶ月まで。(いずれも相続開始から) | |
| 3. 相続登記を行い、不動産の名義変更を行う | 相続して所有権を取得してから3年以内(2024年4月から義務化)※ | |
| 4. 相続した家を売却する方法を決める | 仲介業者に委託または買取業者に売却 | |
| 5. 仲介業者または買取業者を決める | 複数社を比較して決める | |
| 仲介 | 買取 | |
| 6. 不動産評価、査定 | 数日から1-2週間 | |
| 7. 売却活動 | 少なくとも1ヶ月 | 最短1週間から1ヶ月 |
| 8. 買主と売買契約を結ぶ | 少なくとも3ヶ月 | |
| 9. 不動産の名義を変更する | ||
| 10. 売却成立(家の処分完了) | ||
| 11. 不動産譲渡税払う | 翌年の3月16日まで | |
このように、相続から処分までにはさまざまなステップが必要です。
また、相続分割協議は法定相続人全員が揃い、合意に至る必要があります。
分割協議自体のタイムリミットは定められていませんが、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
相続税の申告が遅れたり、過小に申告すると延滞税や加算税が課されて大きなデメリットとなるので、できるだけ早く分割協議書を家庭裁判所に提出して相続手続きを進めましょう。
親の死後、処分したい実家が売れない原因5選
親の実家が戸建て住宅の場合、考えられる売れない理由は以下に挙げる5つが多いようです。
- 築年数が古くリフォーム費用が高額になる
- 立地や日当たりが悪い
- 内覧時の印象が悪い
- 売り出し価格が相場より高い
- 再建築不可物件で建て替えができない
築年数が古くリフォーム費用が高額になる
築古物件では老朽化した建物・設備がネックとなり、購入希望者がリフォーム費用を懸念して購入を避ける事例が発生します。
主な問題点としては、外壁や屋根の劣化が指摘できます。外壁塗装が剥がれたり、屋根が破損していたりすると、見た目の印象が悪くなります。また、水回りの設備の老朽化も問題です。キッチンや浴室、トイレなど使用する頻度の高い箇所が古いままだと、大幅なリフォームが前提となるため購入者から敬遠されがちです。
具体例として、一般的な広さの戸建て住宅リフォーム費用を概算してみます。
| 屋根 | スレート屋根の塗り替え(20-80万円) 金属屋根の重ね葺き(90-250万円) 瓦屋根の交換(70-120万円) | 20-250万円 |
| 外壁 | 外壁材の重ね塗り(50-150万円) サイディングの上貼り(80-200万円) | 50-200万円 |
| キッチン | キッチン全体のリフォーム(80-400万円) | 80-400万円 |
| 浴室 | システムバスの交換(60-150万円) | 60-150万円 |
| トイレ | トイレ全体の改装(20-100万円) | 20-100万円 |
| 壁・床 | 畳→フローリング(15-60万円) 壁クロスの貼り替え(6-30万円) | 1室 6-60万円×3室 18-180万円 |
| 合計 | 248-1280万円 | |
費用を抑える対策としては、最小限のリフォームを行って費用を抑えつつ、外観や主要設備を修繕して第一印象を改善する方法があります。また、他にアピールポイントがあれば、現状のままリフォーム費用分を値下げして売却する方法もあります。
立地や日当たりが悪い
不動産の価値は、立地や周辺環境によって大きく左右されます。よくあるケースとしては、交通の便が悪く、日常生活に必要な商業施設が遠い立地だと、なかなか売れない場合があります。
たとえば、最寄り駅から徒歩20分以上で駅からバス利用が必要だったり、商業施設に車で15分以上など、日常の通勤や買い物が不便な場合です。
日当たりなどの周辺環境のマイナス要因も影響します。
日当たりが良いと言われる南向き物件の価格を基準とすると、東、西、北の順に物件価格は安くなると言われています。
たとえば、南向き住居を5000万円とした場合、東向は185万円~480万円安く、西向きは200万円~480万円、北向きでは265万円~650万円安くなるという調査があります。※
引用:PR TIMES「新築マンション価格設定の法則~過去10年間を対象に階数と方位から算出~」
また、南向きであっても、周りを高い建物で囲まれていて、室内が暗いと購入希望者に敬遠されるでしょう。
工場や繁華街が近くにあり、騒音や治安の悪化が懸念されるケースもマイナスポイントになります。
他の物件にはない広い庭や駐車場などの長所があれば、購入希望者へのアピールになりますが、そうした長所がない場合は売却が難しくなるでしょう。
内覧時の印象を損なう3つの要因
購入希望者に物件を見せる「内覧」が売却の成否を左右します。
失敗例としては「散らかった室内」「臭気」「照明不足」の3つの要因があげられます。
散らかった室内
部屋が整理整頓されていない場合があります。家具や不要品が散乱していると、物件の印象が悪くなります。
購入希望者が、自分の生活するイメージをつかみやすいように、なるべく生活感が出ないような室内を演出するとよいでしょう。
内覧時だけでも、ファブリックの色を白で統一するのも一つの方法です。
臭気
ペットの匂い、カビ臭、タバコの臭いなど、自分は気にならなくても、他人には気になるものです。
掃除を徹底して、換気を心掛けるのはもちろんですが、空気清浄機を終日稼働させてみるとよいかもしれません。
間違っても、ルームコロンなどでごまかさないようにしましょう。
匂いに敏感な人にはかえって敬遠されます。
まずは、プロのハウスクリーニングを依頼し、室内を清潔で快適な状態に整えるのが第一でしょう。
照明不足
暗い室内は、それだけで印象が悪くなります。
見られたくない汚れや傷があるのだろうかと勘繰られるかもしれません。
昼の内覧の場合は、カーテンを開けて明るくすること。昼でも照明をつけましょう。
ちょっと明る過ぎるくらいに感じる照明に取り替えるのもよい方法です。
そのほか、不動産会社の内覧対応の悪さも問題になるケースがあります。内覧希望者とのスケジュール調整がうまくいかないと、見送りになる可能性が高まります。
内覧希望者への配慮として、柔軟なスケジュール調整を心がけることも大切です。
売り出し価格が相場より高い理由と適正価格の見つけ方
物件価格が地域の相場に比べて高すぎると、買主が敬遠します。失敗例として、周辺相場が2,000万円台の地域で3,000万円以上の価格を設定してしまう場合などがあります。
対策としては、不動産会社に査定を依頼し、適正価格を確認することが重要です。適正価格を大きく下回る必要はありませんが、価格を見直すことで売却がスムーズになる場合があります。
中古一戸建ての査定のポイントは以下の6つです
- 土地、建物の権利状況
- 土地の状況
- 建物の状況
- 周辺の状況
- インフラ状況
- 特別なアピールポイント
土地、建物の権利状況
土地、建物の所有権の状況、たとえば、売主の所有なのか、共有名義者がいるのか、土地に借地権が設定されていないかなどの聞き取り調査や、不明の場合は登記簿にあたって調べます。
ローンの抵当権が設定されている場合は、ローンの滞納がないかなどもチェックされます。
土地の状況
面積や形状のほか、接道や隣地との境界、建ぺい率や容積率の制限の有無などをチェックされます。
後述しますが、この中でも接道については不動産の価格を左右する重要なポイントとなります。
建物の状況
建物の築年数、間取りなどの構造のほか、屋根や外壁、基礎の状態から使用している材質、劣化の状態をチェックします。
周辺の状況
最寄り駅からの距離、スーパーやコンビニなどが物件の近隣にあるかどうかもチェックポイントです。
一方では、騒音や排煙のある工場、墓地など嫌悪施設がある場合は査定額が下がる可能性もあります。
インフラ状況
電気、電話、水道、ガス、下水道設備、最近では、インターネット回線設備についてのチェックもあります。
地方では地域によって公共下水道設備ではない一戸建てもありますが、査定額への影響が大きいかもしれません。
特別なアピールポイント
物件によっては査定額を引き上げるのに有利なアピールポイントがある場合もあるでしょう。
たとえば、窓から富士山が一望できる、
リビングが広い、床暖房、家に暖炉がある、薪ストーブがある、
スウエーデンハウスなどの機能性の高い住宅である、などです。
周辺の相場価格よりも高い価格で売り出すならば、以上の査定のチェックポイントで平均以上の物件でなければ、買主は納得しないでしょう。
特に特徴のない物件である場合は、相場価格よりも若干低めが適正価格と判断するのが消費者心理です。
再建築不可物件とは?建て替えができないケースを解説
法的な制約により建て替えができず、解体して更地にすると、新しく建物が建てられない土地に立っている物件を「再建築不可物件」といいます。
都市計画区域と準都市計画区域内で家を建てる場合は、建築基準法に定められた接道義務を満たす必要があります。
ところが、建築基準法(1950年制定)や都市計画法(1968年制定)の制定以前に建築された古い家には、この「接道義務」を満たしていないケースが数多くあり、「再建築不可物件」となっているのです。
接道義務とは、建築基準法上で「道路」と認められている道に、建物の敷地が2m以上接していることです。
また、建築基準法で「道路」と認められている道も、道幅が4m以上なければなりません。
この基準は、火災などの災害時の避難経路や緊急車両の通行を確保するために定められています。
再建築不可物件を購入しても新たな建物を建てることができないので、一般的に売却は難しくなります。
再建築不可物件に該当するのは、以下のようなケースです。
- 建築基準法で規定された道路に接していない
- 道路に敷地が接していない
- 道路に接している間口が2m未満
- 路地部分の長さが規定外である
建築基準法で規定された道路に接していない
建築基準法で「道路」とされるのは幅員4m以上の道路です。4m未満であると、緊急車両の通行が難しくなるのがその理由です。
いわゆる、車の入れない路地に面している家は再建築不可物件である可能性があります。
ただし、これには例外規定が設けられていて、特定行政庁の指定を受ければ、建築基準法上の道路としてみなされる場合があります。
このようなケースでは、再建築する場合、道路の幅員を4mに広げるために敷地を後退させる(セットバック)必要があります。
また、接している道が「私道」の場合も、建築基準法の「道路」ではありません。
道路に敷地が接していない
周囲を他の家の敷地などに囲まれていて、家の敷地から道路に直接出ることができない家も再建築不可となります。
このような土地は「袋地」と言われます。
また、海や川や水路、崖などがあって道路に家の敷地が接していない場合も「準袋地」とされ、再建築不可となる場合が多いので注意が必要です。
道路に接している間口が2m未満
道路に家の敷地が接していても、間口が2m未満の場合も接道義務を満たしていないので再建築不可となってしまいます。
このケースが一番多いと言われています。
路地部分の長さが規定外である
接道部分から路地がある、いわゆる旗竿地では、道路の幅員や間口の基準を満たしていても、路地部分の長さによっては再建築不可になる場合もあります。
この路地部分の長さの規定は自治体によって異なります。
例えば、東京都の建築安全条例では、路地部分の長さが20mを超える場合、路地部分の幅員は3m必要です。
これらの再建築不可物件も、セットバックを行う、周辺の敷地を購入して接道条件を満たすことで新築できる可能性もあります。
また、リフォームを行うことは可能です。
ですが、再建築不可物件は査定額が低くなり、なかなか売却も進まないのが現実です。
親の死後、売れない家を放置するリスク4選
親の死後、相続した家を売却せずに放置していると、以下のような問題が発生します。
管理コストが増大する
固定資産税(と都市計画税)や維持費・修繕費が大きな負担となります。
| 固定資産税・都市計画税 | 固定資産税:評価額のおよそ1.4% 都市計画税:評価額のおよそ0.3% 小規模住宅用地の特例 一般受託用地の特例あり | 例(評価額1000万円の土地) 小規模住宅用地の特例適用後、固定資産税は約2.4万円、都市計画税は1万円で、合計3.4万円 |
| 維持費 | 光熱水費 火災保険・地震保険 自治会費・町内会費 | 例(東京23区) 水道:1170円×12ヵ月=約14000円 電気:約935×12ヵ月=約11220円(30A契約の場合。全く使わない場合は基本料金が半額になる場合もある)火災保険:年額1万円自治会費・町内会費:年額4000円 |
| 管理・修繕費 | 草刈り(年3回) 見回り管理を委託 | 例(60㎡の庭) 3万円×3=9万円 管理費:月額5000円×12=6万円 |
| 合計 | 約22.3万円 | |
人が住んでいなくても、家の維持費として水光熱費はかかります。
ときどき空気の入れ替えをしたり、掃除をしたり、防犯のために防犯カメラを設置する場合に、少なくとも水道と電気は契約しておくべきでしょう。
また、いざという場合に備えて、火災保険や地震保険にも入っておくべきでしょう。
火災保険だけのリーズナブルなものから地震保険も含めた保障が充実したものまでさまざまですが、年間3500円程度から約36000円程度かかります。
その他、近隣との関係を良好に保つために、自治会や町内会にも参加しておいた方がよい場合もあります。
戸建ての場合、庭の草刈りや植木のメンテナンスは不可欠。年に2、3回は草刈りが必要です。
雑草が生い茂った庭は、衛生面でも防犯面でも近隣の迷惑になります。
草刈り費用は平米単価か、作業者1人の時間単価によって決まります。植木の船体は1本当たりで価格を設定する場合が多いようです。
ケースバイケースですが、たとえば60㎡の庭の草刈りを依頼した場合、1㎡あたり約500円として3万円ほどかかります。
最近では、所有者に代わって空き家を定期的に見回り、簡単な清掃や建物のチェック、防犯確認などをしてくれます。
このようなサービスを依頼する場合の費用は、月額5000円から15000円程度です。
そのほかにも、空き家の様子を見に帰省する際の交通費もかかります。
防犯上の問題が発生する
空き家は防犯上のリスクが非常に高まります。放火や不法侵入のリスクが増加し、近隣住民にも多大な迷惑をかけます。
よくあるケースは庭への粗大ゴミ等の不法投棄です。
放火や、空き家内に侵入して占拠するケースもあります。
昨今では、特殊詐欺の被害金の送付先や、不正薬物の送付先に空き家の住所が利用されるというケースが目立ち、警察庁も注意喚起を促しています。
参照:警察庁特殊詐欺対策ページ
防犯上の問題を防ぐためには、定期的な巡回やセキュリティシステムの導入が考えられますが、これにはさらなる費用がかかります。空き家を放置することで、被害が拡大し、修繕費や防犯対策費用がかさむリスクを避けるためにも、できるだけ早期の適切な対応が求められます。
建物の劣化が進行
人が住んでいない家は、急速に劣化が進みます。
国土交通省によると、住む予定のない空き家の約23%に「腐朽、破損」があるそうです。
ひとくちに「雨漏り」と言っても、屋根の破損、外壁の破損、窓からの吹き込みによる雨漏りなどさまざまです。
もし人が住んでいる家なら、これらの不具合は比較的早く発見されて、それなりの対応を行うでしょう。
ところが人が住んでいない空き家では、天井にシミが大きく広がってから、ようやく雨漏りが発見されます。
そのため、修理箇所が多くなり、最悪の場合は屋根の葺き替えや外壁の全面塗装が必要になるかもしれません。
雨漏りを例にとると、30坪程度の戸建ての修繕費用は以下のようになります。
| 屋根に原因がある場合 | 部分的 | 1〜40万円 |
| 広範囲 :葺き替えが必要 | 30〜200万円 | |
| 塗装のひび割れが原因 | 部分的 | 約6万円 |
| 広範囲 :外壁全面塗装が必要 | 60〜100万円 |
また、シロアリなどの害虫の発生も心配です。
シロアリ駆除の費用は坪単価で計算しますが、相場価格は6000円から1万円です。
建坪30坪の家であれば、18万円から30万円かかることになります。
シロアリも早期に気づけば駆除の費用だけで済みますが、被害が大きくなってしまうと、家の解体しか解決方法がなくなる場合もあります。
家族間で深刻なトラブルが発生する
複数の相続人がいる場合、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。
よくあるケースでは、
- 固定資産税や都市計画税の負担の割合
- 修繕費、管理費の負担の割合
- 将来空き家をどうするかについて意見がまとまらない
費用の負担は空き家を所有している限り続くので、早期の売却や処分が家族関係を円滑に保つために重要です。
相続税の支払いが必要な場合、財務管理も重要となり、相続人間での協力が不可欠です。
家族間でのトラブルを避けるためには、事前に遺産分割協議を行い、明確な合意を得なければなりません。専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることも有効です。
相続人間のトラブルを回避し、家族関係や財産管理を円滑にするめには、早期の売却という判断が賢明といえるでしょう。家の放置で発生するさまざまな問題を未然に防ぐためにも、早めに対策が大切です。
親の死後、売れない家の処分をする方法5選
親の死後、売れない家を処分するための方法にはいくつかの選択肢があります。
- 仲介会社を利用して売却する
- 不動産買取業者に売却する
- 相続放棄する
- 家屋を解体して更地にする
- 収益物件として運用する
以下に、具体的な方法とその詳細を紹介します。
仲介会社を活用した売却のメリットとデメリット
仲介会社を利用して住宅購入希望者に売却する方法は、もっとも一般的な処分方法です。
以下にそのメリットとデメリットをまとめてみました。
| メリット | ・相場価格に近い適正価格で売却できる可能性がある ・売却のための営業活動をしてくれる ・必要な手続きを代行、紹介してくれる |
| デメリット | ・内覧などの手間がかかる ・売却成立まで時間がかかる ・仲介手数料がかかる(速算式 仲介手数料=取引価格×3%+6万円 税別) |
不動産仲介会社を通じて売却すれば、適正価格での売却が期待できます。不動産会社は市場の動向を把握しており、適切なアドバイスを提供してくれます。
また、広告や内覧の手配など、売却に必要な営業活動手もすべて代行してくれます。
買い手がつけば、契約に関わる手続きも代行、紹介してくれるので、必要な書類を揃えるだけで済みます。
ただし、一般的に売却成立までに時間がかかり、最短でも3ヶ月かかることは覚悟しなければなりません。
相続税の納税など早急に資金が必要な場合には別の方法を検討する必要があります。
また、物件の価格に応じて仲介手数料を払う必要があります。
不動産買取業者へ即日売却する方法
迅速な売却を目指すなら、不動産買取業者の利用がおすすめです。修繕やクリーニング不要でそのまま売却可能なため、手間がかからず迅速に現金化することができます。買取業者を利用することで、短期間で売却を完了し、早急に資金を手に入れることができます。
不動産買取業者に売却する場合の具体的な流れと所要日数は以下のようになります。
| 複数の買取業者から見積もりを取る | 数日〜 |
| 買取業者の決定 | |
| 査定 | 即日から数日 |
| 売却の契約を結ぶ | |
| 売却代金入金 | 〜1週間 |
ただし、市場価格よりも安価になる傾向がある点、条件の悪い物件は買取を拒否されることもある点は知っておきましょう。適切な買取業者を選ぶことが重要です。
買取業者を選ぶポイント
買取業者を選ぶ際には、複数の会社から見積もりを取って決定しましょう。
その際注意したいのは、買取価格が高い業者がベストとは限らないことです。
買取業者を選ぶポイントは以下の3つです。
- 該当物件の類似物件や所在地で実績がある
- 買取物件の活用用途を広く持っている
- 買取価格の根拠や契約条件をはっきり説明してくれる
高い査定額を提示していても、契約条件次第では査定額の金額で買取りできない場合もあります。
特に、買い取った不動産に不都合があった場合、売主に保障責任が課される契約不適合責任が免責であるかどうかは重要なポイントです。
相続放棄の手続きと期限について
負債が家の価値を上回る場合、相続放棄で負担を回避する選択肢があります。相続放棄を選択することで、相続人は遺産に対する一切の権利を放棄し、負債や維持管理費用の負担を避けることができます。
相続放棄の手続きの流れは以下のようになります。
| 1 書類を準備する | ・亡くなった人の戸籍謄本 ・相続放棄を希望する人の戸籍謄本 ・相続放棄の申述書必要書類は法定相続の相続順位によってさらに必要になる場合があります |
| 2 書類を家庭裁判所に提出する | ・亡くなった人の最後の住所地(住民票がある場所)管轄の家庭裁判所 ・手数料として800円(収入印紙)、切手代などが必要 ・司法書士などに依頼した場合は3〜5万円で全て代行してくれる |
| 3 家庭裁判所から照会書が届く | この間書類に不備がある場合は何度か問い合わせ、再提出がある。
|
| 4 回答して家庭裁判所に返送 | |
| 5 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く | 手続き完了 |
相続放棄を選択する場合は、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要です。
相続放棄を行うと、負債だけではなくプラスの資産も相続できなくなります。
そして、一旦相続放棄をしたら、後日取り消すことはできません。
また、他の相続人がその負担分を引き受けることになるため、事前に連絡を入れて説明をしましょう。
相続放棄の手続き自体は自分で行うことも可能ですが、相続人が複数いたり、事情が複雑な場合は専門家に依頼するのが良いかもしれません。
家屋を解体して更地にする
建物を解体して、更地として売却する方法です。
更地にする場合は、家屋の状態を気にすることなく売却可能で、買主も自分好みの家を建てられます。
家屋が築古で使い勝手が悪い場合や大規模な修繕を必要としている場合は、更地にするほうで売却がスムーズに進むことがあります。
解体費用は坪単価などで決まりますが、建坪30坪の一般的な住宅では、解体費用は150〜200万円ほどです。
更地にした後に売却せず、自分たちで利用する方法もあります。例えば、住宅を新築して相続人が使用したり、駐車場経営で新たな収入源を確保したりすることも考えられます。
ただ、再建築不可物件の場合、更地にするとそのままでは新たに家が建てられないので、かえって売れにくくなる場合もあるので注意しましょう。
また、住宅の立っていない土地は固定資産税等の軽減措置が受けられません。更地にした場合、固定資産税や都市計画税が最大6倍になってしまうことも忘れてはいけません。
収益物件として賃貸活用する
相続した家が住宅としてまだ使えるが、相続人の誰も必要としていないケースの解決策として、収益物件として運用する方法があります。第三者に賃貸して、毎月の家賃収入を得られます。
空き家を収益物件として賃貸活用する場合のメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | ・家賃収入が得られる ・家に住む人がいることで結果的に建物の寿命が伸びる |
| デメリット | ・リフォームに費用がかかる ・管理や修繕に手間と費用がかかる ・空室になる可能性もある |
たとえば、都市部の空き家を中規模改修して賃貸した場合、賃貸前の改修費用150万円で月額7万円で貸すと、賃貸運営に関する諸経費を差し引いた上で、5年目から累計収支が黒字になるというシュミレーションがあります。
日本政策投資グループ株式会社価値総合研究所:「空き家の賃貸流通促進に係る趣味レーション」
ですが、地域によっては入居者が途切れずにあるとは限らず、空室リスクや家賃滞納リスクも想定しなくてはならないでしょう。
以上の方法を検討することで、親の死後に実家を適切に処分し、無駄なコストを避けられるでしょう。各方法にはメリット・デメリットがあるため、自分たちの状況に最適な方法を選択する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、最適な選択肢を見つけてください。
親の死後、売れない家の処分方法まとめ
親の死後に相続した実家は、
・立地や日当たりが悪い
・内覧時の印象が悪い
・売り出し価格が相場より高い
・再建築不可物件である
などの理由でなかなか売れません。
だかといって、そのまま空き家を放置すると以下のようなデメリットがあります。
・防犯上の問題が発生する
・建物の劣化が進む
・家族間で深刻なトラブルが発生する
親の死後売れない家の処分におすすめする方法は以下の4つですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
| 処分の方法 | メリット | デメリット |
| 仲介会社で売却 | 相場価格に近い適正価格で売れる可能性 | 売却まで時間がかかる 仲介手数料がかかる 契約不適合責任を問われる可能性がある |
| 買取会社に売却 | 売却までに時間がかからない 契約不適合責任は免責である場合が多い 仲介手数料がかからない | 相場価格よりも安くなる |
| 相続放棄する | 負債がある場合、責任が問われない 面倒な相続問題に巻き込まれない | 亡くなって3ヶ月以内に手続きをしなければならない 負債がある場合、他の相続人に迷惑がかかる 後日取り消せない |
| 解体して更地にする | 古屋付きより売れやすい | 解体費用がかかる 再建築不可物件の場合、更地にできない すぐに売れなかった場合、翌年からの固定資産税が高くなる |
| 収益物件として賃貸運用 | 賃貸収入が入る 空き家より家の寿命が伸びる | リフォームや管理に費用がかかる 家賃滞納や空室対応が難しい |
以上、親の死後売れない家の原因や、その解決方法を解説しました。
最後の章で、売れない家の処分をする方法5選を紹介しましたが、もっとも確実で迅速に対応できる方法は、専門の買取業者を利用することです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、築古や悪立地物件の住宅も積極的に買い取っております。過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介されました。
売れない実家を手放したくてお困りの方は、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問と回答
Q 親から相続した家を処分したいのですが、処分にかかる期間はどれくらいかかりますか?
<回答>
処分方法によって必要な期間は違います。
最も早く処分できるのは、現状のまま買取業者に買い取ってもらう方法です。
買取にかかる期間は早くて数日、一週間程度で処分は終了します。
不動産仲介会社を通して売却する場合は、早くても3ヶ月はかかるでしょう。
また、相続を放棄する場合も、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出して受理される必要があります。
Q 親から相続した家の処分にかかる費用は?
<回答>
処分の方法によって費用は異なります。
一番費用がかからないのは、買取業者に買い取ってもらう方法です。
この場合、手数料等、一切かかりません。
次に費用がかからないのは、相続放棄する場合です。
相続放棄の場合は、手数料として800円の印紙、申述書に添えて提出する戸籍謄本などの発行費用、裁判所からの返信用の切手費用などがかかります。自分で手続きを行なった場合は3000円程度で済みます。
司法書士に依頼した場合は、3万円から6万円程度かかるでしょう。
最も費用がかかるのは、仲介業者に依頼して売却した場合です。
この場合、仲介手数料がかかります。(速算式 仲介手数料=取引価格×3%+6万円 税別)
Q 親から相続した家を処分したら税金はかかりますか?
<回答>
処分して得た譲渡所得に応じて所得税と住民税がかかります。
課税される譲渡所得は以下の計算式で求められます。
課税譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
この課税譲渡所得金額に不動産を所有していた年数に応じて異なる税率をかけて所得税が計算されます。
| 長期譲渡所得(5年以上の所有) | 課税長期譲渡所得金額×15% |
| 短期譲渡所得(5年未満の所有) | 課税短期所得金額×30% |
ただし、相続した居住用財産(空き家)を譲渡した場合は、2000万円または3000万円の特別控除が受けられます。
参照:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
譲渡所得税は譲渡があった翌年の3月16日までに確定申告をして納税しなければなりません。
確定申告で確定した全所得に応じてその年の住民税が決まります。
Q 相続放棄した空き家にはもう責任は問われませんか?
<回答>
2023年の改正民法以前は、たとえば相続人が一人だけの場合や、すべての相続人が相続放棄をした場合は最後に相続放棄をした人が、相続財産管理人(現 相続財産清算人)が選任されるまで空き家の管理をしなければなりませんでした。
ですが、改正後は相続放棄した家に住んでいる人が管理の責任を負うことになりました。
「空き家」である以上、住んでいる人はいないはずなので、「空き家を相続放棄した」場合は管理の責任を負うことはありません。
Q 空き家をそのままにしておくと罰せられますか?
<回答>
適切な管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観の面で近隣に著しく影響を与えていると判断された場合、「空き家対策特別措置法」によって行政の指導、勧告を受け、それでも改善されない場合は「管理不全空き家」、「特定空き家」に指定されてしまいます。
行政の勧告に従わず「管理不全空き家」、「特定空き家」に指定されると、過料(罰金)が科される上に、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性があります。
処分費用の具体例
一般的な戸建て住宅(30坪)を親から相続して、その後に処分した場合にかかる費用をまとめてみました。
仲介業者を通じで売却する
| 相続に関する費用 | 相続税 :不動産以外の資産も含めて計算。相続財産全体が基礎控除を上回る場合に課税される 基礎控除=3000万円+(600万円×相続人の数) 所有権移転登記にかかる費用:登録免許税 固定資産税評価額×税率 必要書類を取得する手数料 司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬 | 相続税、登録免許税はケースバイケース 司法書士の報酬相場:数万から5万円程度 |
| 仲介業者に支払う費用 | 仲介手数料:速算式 仲介手数料=取引価格×3%+6万円 税別 | 3000万円で売却できた場合、96万円(税別) |
| 譲渡所得税・住民税 | 課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 課税長期譲渡所得金額×15%、課税短期譲渡所得金額×30% | 3000万円で売却できた場合、「相続した居住用財産(空き家)を譲渡の特例」が3000万円適用されて課税譲渡所得額は0円となり、課税譲渡所得分の所得税は0円 |
買取業者に売却する
| 相続に関する費用 | 相続税 :不動産以外の資産も含めて計算。相続財産全体が基礎控除を上回る場合に課税される 基礎控除=3000万円+(600万円×相続人の数) 所有権移転登記にかかる費用:登録免許税 固定資産税評価額×税率 必要書類を取得する手数料 司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬 | 相続税、登録免許税はケースバイケース 司法書士の報酬相場:数万から5万円程度 |
| 買取業者に支払う費用 | 手数料等なし | 0円 |
| 譲渡所得税・住民税 | 課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 課税長期譲渡所得金額×15%、課税短期譲渡所得金額×30% | 2000万円で売却できた場合、「相続した居住用財産(空き家)を譲渡の特例」が3000万円適用されて課税譲渡所得額は0円となり、課税譲渡所得分の所得税は0円 |
更地に解体し仲介業者を活用して売却した場合
| 相続に関する費用 | 相続税 :不動産以外の資産も含めて計算。相続財産全体が基礎控除を上回る場合に課税される 基礎控除=3000万円+(600万円×相続人の数) 所有権移転登記にかかる費用:登録免許税 固定資産税評価額×税率 必要書類を取得する手数料 司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬 | 相続税、登録免許税はケースバイケース 司法書士の報酬相場:数万から5万円程度 |
| 解体・更地にする費用 | 30坪の場合(立地条件で増額あり) | 約150万円から200万円 |
| 仲介業者に支払う費用 | 仲介手数料:速算式 仲介手数料=取引価格×3%+6万円 税別 | 3000万円で売却できた場合、96万円(税別) |
| 譲渡所得税・住民税 | 課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 課税長期譲渡所得金額×15%、課税短期譲渡所得金額×30% | 3000万円で売却できた場合、住宅取得費を1000万円とした場合 課税譲渡所得は 3000万円-(1000万円+200万円+96万円)=万円 長期譲渡所得の場合、1704万円×15%=約256万円 短期譲渡所得の場合、1704万円×30%=約511万円 |
以上はあくまでも一般的な数字の計算例であり、実際は諸条件によって大きく異なってきます。
詳しく正確な数字を知りたい場合には、専門家に相談してみるのが一番です。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!