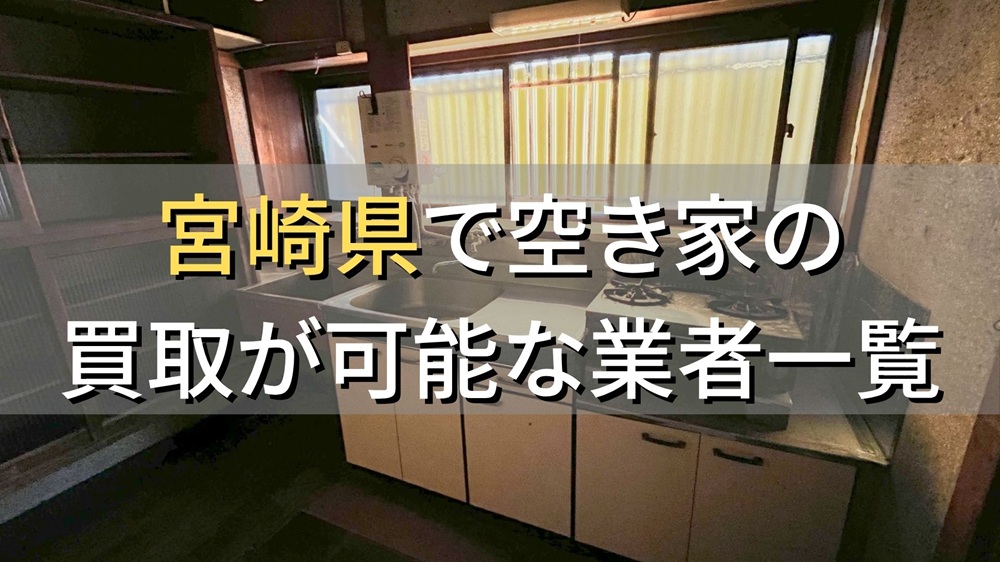再建築不可物件を再建築可能にする抜け道7選!手順や対処法も解説


再建築不可の土地を所有していて、「なんとか建て替えできないか」と悩んでいませんか?
接道義務を満たしていない、市街化調整区域にあるといった理由で、建て替えを断念せざるを得ないケースは少なくありません。
結論から言えば、再建築不可物件でも、一定の条件をクリアすれば再建築が可能になる「抜け道」は存在します。
例えば、隣地を購入したり、セットバックや但し書き申請を行ったりすれば、建築基準法上の制限をクリアできるケースがあります。
とはいえ、これらの方法は費用や交渉、行政手続きなど、相応の労力を要し、実現には高いハードルがあるのが実情です。
そこで本記事では、
- 再建築不可になる代表的な理由
- 再建築可能にするための具体的な抜け道・手順
- 再建築が難しい場合の現実的な選択肢(買取)
までを、わかりやすく整理してお伝えしていきます。
記事を読めば、あなたの土地が再建築可能になる可能性や、もし難しい場合にどう動くべきかが明確になります。
弊社AlbaLinkでも、再建築不可物件の買取を専門に行っており、どんな状態でも無料で査定を承っています。
「活用が難しそう…」と感じたときには、お気軽にご相談ください。
目次
再建築不可物件とは建て替えできない土地
再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊しても、新たな建築が認められない土地を指します。
これは、都市計画法や建築基準法といった法律に違反しているわけではなく、現行の法令基準を満たしていないことが原因です。
再建築不可と判断される主な要因は、以下の2つです。
- 接道義務を果たしていない
- 市街化調整区域内に所在している
それぞれ、具体的にどのような状況なのかを確認していきましょう。
接道義務を果たしていない
接道義務を満たしていない土地は、原則として新たな建物を建てることができません。
なぜなら、建築基準法では「敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と明確に規定されているからです。このルールは、火災や災害時に消防車や救急車がスムーズに現場へアクセスできるようにするために定められました。
具体的には、次のような土地が接道義務を満たしていない状態と見なされます。
| 前面道路の幅が4m未満 | 消防車・救急車の通行が困難 |
| 敷地が道路に2m以上接していない | 狭すぎて出入り不可 |
| 建築基準法上の「道路」と認められていない | 私道など扱いによっては対象外 |
| 道路に全く接していない | 孤立地 |
建築当時は合法だったものの、後から法改正によって再建築不可になった土地も少なくありません。これらは「既存不適格物件」と呼ばれ、特に昭和25年(1950年)以前に建てられた建物に多く見られます。
再建築不可物件を持ち続けると、資産価値が低下したり、売却が難航するリスクも高まるため、早めに買取専門の業者へ相談する選択肢も検討する必要があります。
市街化調整区域内に所在している
市街化調整区域にある土地は、原則として新たな建物を建てることができません。
なぜなら、市街化調整区域は「市街化を抑制すること」を目的としたエリアだからです。都市計画法によって定められており、開発行為や建築が厳しく制限されています。
具体的には、以下のような特徴があります。
| 区分 | 特徴 |
| 市街化区域 | 市街地として開発・整備される区域 |
| 市街化調整区域 | 開発を抑制し、原則建築が認められない区域 |
所有している土地が市街化調整区域に該当しているかどうかは、自治体の都市計画図で確認できます。
特に周囲に田畑や山林が広がっている場合は、市街化調整区域である可能性が高いでしょう。
市街化調整区域でも例外的に建築が認められるケース(許可申請)もありますが、許可基準は厳しく、個人でのクリアは困難です。
そのため、再建築不可物件を活用したり、売却を検討したりする場合には、この制約を踏まえた専門的な対応ができる不動産業者への相談が不可欠と言えます。
再建築不可を再建築可能にする6つの抜け道
再建築不可物件であっても、特定の条件を満たせば再建築可能にできるケースがあります。
ただし、そのためには土地の形状や法的条件を見極め、適切な対応を取る必要があります。
「どうにかして建て替えたい」と考えている方は、以下6つの方法がとれるかを一度確認してみましょう。
- 隣地の一部を購入する
- 隣地と等価交換する
- 隣地の一部を借りる
- セットバックする
- 但し書き申請をする
- 位置指定道路の申請をする
どの方法もハードルはありますが、うまく活用できれば建て替え可能な土地としての価値を回復させられます。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
隣地の一部を購入する
隣地を買い足して敷地の接道幅を広げれば、再建築できる可能性があります。
建築基準法では、建物を建てる土地が「幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」を求めています。
この条件を満たさないために再建築不可となっている場合、隣地を一部購入し、敷地の接道幅を2m以上に広げることで、再建築が認められるケースがあります。
ただし、隣地の所有者が売却に応じてくれるかどうかはわかりません。
いきなり交渉を持ちかけるとトラブルになる可能性もあるため、事前に不動産業者など第三者を通して話を進めるのが安心です。費用負担や登記手続きなどの準備も必要になります。
隣地の一部購入はハードルもありますが、接道義務を満たす有効な選択肢の一つです。
状況に応じて専門家と連携しながら進めることで、再建築可能な土地への道が開けるかもしれません。
隣地と等価交換する
再建築不可物件の敷地条件がわずかに足りない場合、隣地と土地を等価で交換すれば再建築が可能になるケースがあります。
特に、奥に敷地が広がる「旗竿地」のような形状では、接道部分の幅がわずかに足りないだけで建て替えができなくなることがあります。その場合、隣地と一部の土地を等価交換し、接道義務(道路に2m以上接している)を満たせば、再建築が可能になります。
この方法は、金銭のやり取りを伴わずに済むケースも多く、税制面でも「固定資産の交換の特例」が適用されれば譲渡所得税が発生しないのがメリットです。面積を調整して価値が等しくなるようにすれば、追加費用なしで成立する可能性もあります。
とはいえ、交換するには隣地所有者との協議が不可欠であり、相手の理解を得られなければ成立しません。また、税制優遇を受けるには、1年以上の所有や用途の継続といった条件をクリアする必要があります。
「等価交換」は費用を抑えて再建築の可能性を広げられる現実的な方法の一つです。
隣地の一部を借りる
隣地の土地を一時的に借りることで、接道義務をクリアし再建築可能にする方法もあります。
再建築不可の多くは「接道義務」を満たしていないことが原因ですが、この義務は所有権がなくても、借地契約によって一定の条件を満たせばクリアできる場合があります。
つまり、隣地の一部を「建築確認のためだけに一時的に借りる」ことで、建て替えが可能になることもあるのです。
この方法は、売買や等価交換よりも隣地所有者の心理的ハードルが低く、協力を得やすい傾向にあります。また、費用負担も比較的少なく済むケースが多いため、実現可能性の高い「抜け道」と言えるでしょう。
ただし、借りる条件や期間、費用は明確にしておかないと、あとで「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性もあります。地代や期間を明記した「賃貸借契約書」を必ず交わし、書面で残すことが大切です。
「借りる」選択肢は、コストや交渉のハードルを抑えながら、再建築の可能性を広げられる現実的なアプローチです。
それでも交渉が難航する場合には、不動産買取などの別の選択肢も視野に入れておくと良いでしょう。
セットバックする
道路の幅が狭く接道義務を満たしていない場合でも「セットバック」によって再建築可能になるケースがあります。
建築基準法では、原則として道路の幅員が4m以上あることが求められます。
しかし、古くからある住宅地などでは4m未満の道路に面した土地も多く、そうした土地ではそのままでは再建築が認められません。
そこで有効なのが「セットバック」の手法です。
道路の中心線から2m(または3m)後退したラインまで自分の敷地を下げることで、道路の幅を確保し、建築許可を得られるようにするというものです。自治体によっては補助金が出る場合もあり、費用を一部カバーできる可能性もあります。
一方で、セットバックを行うと、その部分の土地は「建築用地」として使えなくなり、建てられる建物の大きさが制限されてしまう点には注意が必要です。
施工費用として30〜80万円ほどかかることもあり、事前に費用対効果を検討しておくことが望ましいでしょう。
建物の大きさが多少制限されても再建築が可能になることで、不動産の価値そのものが大きく改善される場合もあります。
土地のポテンシャルを引き出す手段として、セットバックは有効な選択肢と言えるでしょう。
セットバックを実施する手順
建物を再建築可能にするためにセットバックが必要な場合、正しい手順を踏むことでスムーズに申請・施工を進めることができます。
再建築不可物件の中でも、前面道路の幅員が足りないケースでは「セットバック」が有効な対策となります。ただし、自治体との協議や建築確認など、複数のステップを踏む必要があるため、流れを事前に把握しておくことが大切です。
セットバック工事を実施する主な流れは、以下のとおりです。
| 1.必要性と範囲の調査 | 自治体の建築課などで、対象地がセットバックの対象か確認 |
| 2.事前協議書の提出・現地調査の依頼 | 自治体に書類を提出し、職員による現地調査・道路中心線の確認などを受ける |
| 3.測量と事前協議の実施 | 測量士などが関与し、敷地の後退幅・整備方法などを自治体と協議 完了後に協議書が交付 |
| 4.建築確認申請→許可取得→工事開始 | 交付された協議書を添えて建築確認申請を行い、許可が下りれば工事着手が可能 |
| 5.補助金・助成金の申請(該当自治体の場合) | 自治体によっては、セットバック工事に対して補助金制度があるため、必要に応じて申請 |
| 6.セットバック後の土地処理の確認 | 後退した土地部分を「私有地のまま」にするか、「自治体へ寄付または売却する」かを選択(自治体と要相談) |
セットバック工事は単なる工事ではなく、行政手続きとの連携が求められます。
土地の条件や自治体の基準によっても対応が異なるため、事前相談や専門家のサポートを受けながら進めることが、再建築可能な状態への近道と言えるでしょう。
但し書き申請をする
接道義務を満たしていない土地であっても、「但し書き申請」を通じて再建築が認められる可能性があります。
通常、建物を建てるには、建築基準法により「幅4m以上の道路に2m以上接していること」が求められます。
しかし、こうした要件を満たしていない無接道地でも、特定の条件をクリアすれば例外的に建築が許可される制度が存在します。それが「43条但し書き申請」です。
具体的には、敷地の周囲に一定の空間があり、避難や防災、衛生などの観点で支障がないと判断されれば、地方自治体と建築審査会の許可を得て再建築が可能になる仕組みです。
申請が認められれば、再建築不可だった土地でも新たに建物を建てることができます。
ただし、注意すべきなのはこの申請が「必ず通るものではない」点です。
審査の基準は自治体ごとに異なり、将来的に制度が変わってしまうリスクもあります。
また、許可を得るには専門的な図面や書類の提出、行政との綿密な協議が必要になるため、個人での対応はハードルが高いと感じるかもしれません。
そのため、但し書き申請を検討する場合は、不動産や建築の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
但し書き申請をする手順
但し書き申請とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件をクリアすれば建築を認めてもらえる特例制度です。
ただし、手続きには複数の工程と専門的な書類が必要となり、スムーズに進めるためには正しい流れを把握しておかなければなりません。
申請は以下のような手順で進められます。
| 1.自治体への相談 | 物件所在地の都市計画課などに相談し、該当の土地が但し書き許可の対象となり得るかを確認 |
| 2.書類の準備と提出 | 相談結果をもとに以下の必要書類を揃え、申請 ・ 43条許可申請書 ・ 現況図・見取図 ・ 登記事項証明書・公図の写し ・土地利用計画書 ・ 隣地所有者の同意書(通路確保の承諾) |
| 3.建築審査会による審査 | 提出された資料をもとに、自治体が開く建築審査会で審査。安全性や都市計画上の適合性などがチェックされる |
| 4.許可の通知と建築確認申請 | ・審査を通過すると但し書き許可が通知される ・ただし、建物を建てるには別途「建築確認申請」も必要 |
但し書き申請は一見シンプルに見えて、実務的にはハードルの高い手続きです。
特に隣地所有者からの同意が必要となる場面では、個人では対応が難しいケースもあります。書類の記載ミスや審査の不備で却下されることもあるため、早い段階で不動産や行政に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
弊社AlbaLinkでも、こうした再建築不可物件の確認や相談を無料で受け付けていますので、お困りの際はぜひご活用ください。
位置指定道路の申請をする
位置指定道路とは、特定行政庁から正式に道路と認められた私道のことです。
通常の私道では建築基準法上の「道路」と見なされないため、再建築ができませんが、位置指定を受けることで再建築が可能になります。
たとえ幅が4m以上ある私道でも、法律上の道路と認められなければ、再建築不可扱いになってしまいます。しかし、一定の条件を満たして自治体に申請し、承認を得れば「建築基準法上の道路」として正式に扱われ、建物の建て替えができるようになります。
位置指定道路として認められるためには、以下の基準をクリアする必要があります。
- 幅員4m以上あること
- 両端が公道などと接続していて通り抜けできること(35m以内が原則)
- 隅切り(交差点の角をカット)を設置していること
- 原則アスファルト舗装であること
- 勾配12%以下、かつ階段状でないこと
- 境界が明確になっていること(側溝など)
ただし、道路となる土地に権利を持つすべての人から同意を得る必要があるため、手続きは簡単ではありません。
位置指定道路の申請は、法的に建て替えできる土地にするための重要な方法ですが、クリアすべき条件や手続きのハードルが高いため、慎重な準備と確認が欠かせません。
位置指定道路の申請をする手順
位置指定道路の申請は、単に申請書を出すだけではなく、計画段階から完成後の検査まで、いくつものステップを踏む必要があります。
道路の位置指定を受けるには、公共性や安全性の確保が求められるため、自治体の厳格な基準をクリアしなければならないからです。
そのため、事前の相談から検査・認可まで、段階的な手続きが設けられています。
位置指定道路の申請手順は、以下の流れで進めます。
| 1.事前相談 | 計画内容について、あらかじめ自治体の窓口に相談 |
| 2.申請図書の作成 | 道路位置図、平面図、断面図など、必要な図面を作成 |
| 3.申請書提出と手数料納付 | 正副の申請書類と必要部数を提出し、指定にかかる手数料を納付 |
| 4.道路工事着手 | 申請内容に基づき、実際に道路工事を開始 |
| 5.工事完了後の完了報告提出 | 工事が完了したら、完了報告書を提出 |
| 6.完了検査 | 自治体による現地検査 |
| 7.位置指定の完了 | 完了検査を通過すると、正式に位置指定道路として認可 |
位置指定道路の申請は、事前相談から完了検査まで一貫した準備と手続きが必要です。スムーズな進行のためには、早めに自治体と相談しながら進めるていくことが大切です。
市街化調整区域内で再建築可能にする抜け道
市街化調整区域にある土地でも、特定の条件を満たして開発許可を取得できれば、建物を建てることが可能になります。
市街化調整区域は、原則として新たな建築が制限されていますが、一定の基準をクリアすれば、個別審査のうえ例外的に建築が認められる場合があります。
例えば、既存の住宅が建っていた土地や、周囲に住宅が建ち並ぶ地域などでは、許可が下りる可能性も高まるでしょう。
市街化調整区域内で建て替えを目指す場合は、まず自治体に開発許可の申請を行い、基準を満たしているかどうかを審査してもらう必要があります。
許可取得には時間やコストがかかることもありますが、成功すれば再建築不可の制約を解消できるチャンスです。
ハードルはありますが、適切な手続きを踏めば、市街化調整区域でも建築の可能性は十分に開けます。
まずは現在の土地状況と自治体の基準を正しく把握してから検討しましょう。
開発許可を受ける手順
市街化調整区域内で再建築を目指すには、まず自治体から「開発許可」を取得する必要があります。これは通常の建築許可とは異なり、より厳しい審査を通過しなければなりません。
市街化調整区域はそもそも開発を抑制するエリアのため、建物を建てるには特別な許可が必要です。開発許可を得るには、地域ごとに定められた細かな基準をクリアしなければならず、手続きも煩雑です。
開発許可を取得する主な流れは、以下のようになります。
| 事前届の提出 | 計画を自治体に届け出て、必要条件を確認 |
| 開発予定標識の設置 | 現地に標識を設置し、周囲に周知 |
| 近隣住民への説明 | 影響がある近隣住民に計画内容を説明 |
| 事前協議・開発事前協議 | 自治体と具体的な開発内容について協議 |
| 協議の締結 | 協議をまとめ、許可に向けた準備を完了 |
| 開発許可申請 | 正式な書類を整えて申請 |
| 許可取得後、工事完了届提出と建築確認申請 | 建築工事の準備 |
プロセスの中では、膨大な書類作成や近隣への対応が求められるため、個人で進めるにはかなりハードルが高いのが実情です。
開発許可の取得は手間と時間がかかるため、まずは自治体に相談して、自分の土地が対象になり得るかを早めに確認しておきましょう。
再建築不可を再建築可能にする抜け道はハードルが高い
再建築不可物件を再建築可能にするための抜け道は、存在するものの、いずれもハードルが高いのが現実です。
隣地との交渉や、自治体への申請、細かな条件のクリアなど、クリアしなければならない課題が多く、簡単には進められないケースがほとんどだからです。
特に、隣地所有者の理解を得ることや、法的な審査を通す作業は、想像以上に労力と時間を要します。
例えば、隣地の一部を買い取る場合でも、売却に応じてもらえなかったり、価格交渉でもめたりするリスクがあります。
但し書き申請や位置指定道路の申請も、自治体ごとに厳しい基準が設けられており、必ず許可が下りるわけではありません。
再建築可能にする抜け道は確かに存在しますが「思ったよりも難易度が高い」と心構えしておく必要があります。
焦らず、まずは状況を整理しながら、現実的な選択肢を考えていきましょう。
再建築不可物件を活用するのも難しい
結論から言うと、再建築不可物件を活用するのは簡単ではありません。
なぜなら、建て替えができない制約に加えて、リフォームや土地活用にも多くのリスクが伴うからです。
再建築不可物件を活用する選択肢は「建て替えずにリフォームする」「更地にして土地活用をする」の2つに大別されます。
さらに、それぞれ「自分で活用する」「他人に貸す」の2つのパターンに分かれます。
しかし、いずれのパターンでもリスクを伴う点には注意が必要です。
| リフォームして自分で住む場合 | 通勤や生活環境に問題があれば、住み続けることが難しくなる可能性がある |
| リフォームして賃貸する場合 | 立地が悪いと空室リスクが高く、収益が安定しない恐れがある |
| 更地にして自分で活用する場合 | 太陽光発電や農園経営などには初期費用がかかり、採算が取れないリスクがある |
| 更地にして貸し出す場合 | 地代収入だけでは固定資産税や維持費を賄えず、赤字になるケースもある |
どの選択肢をとっても簡単にはいかないため、専門知識がない場合やリスクを避けたい場合は、売却して資産整理を図るほうが現実的な解決策となるでしょう。
再建築不可の抜け道が難しいなら専門の不動産買取業者に売却する
再建築不可物件を再建築可能にする方法にはいくつかの選択肢がありますが、現実的にはハードルが高いケースがほとんどです。
そのため、条件に合致しない・手続きが煩雑といった理由で実現が難しい場合は、専門の不動産買取業者に売却する選択肢がもっとも確実で、現実的です。
実際、再建築不可物件は需要が限られており、通常の不動産会社では取り扱いを断られるケースも少なくありません。
しかし、再建築不可物件の取り扱いに慣れた専門業者であれば、再活用や再販のノウハウをもとにスムーズに買い取ってもらえる可能性があります。
「できれば活用したいけれど、調整区域だったり接道義務が難しい…」と感じている方は、無理に活用にこだわらず、一度専門業者に相談してみることをおすすめします。
弊社AlbaLinkでも、全国対応・無料査定にて再建築不可物件の買取を行っていますので、お気軽にご相談ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
そのままの状態で売却できる
再建築不可物件は、ボロボロでも壊れていても、そのままの状態で売却可能です。
なぜなら、専門の買取業者は、古家付きや傷んだ物件でも「再販できる商品」として見ており、現状のまま買い取ってくれるからです。
例えば、築50年以上の空き家や、雨漏り・傾きがある家でも、実際に買取された実例は多数あります。
売主側で高額なリフォーム費や解体費用をかける必要がなく、あくまで「いまの状態」でそのまま現金化できるのが大きな魅力です。
特に、親の代から引き継いだ物件などで「何も手を加えられずに年数だけが経ってしまった…」などのケースでも、再建築不可に強い業者ならスムーズに話が進みます。
建て替えも難しく、リフォームも手を出しにくい物件は、そのままの状態で買い取ってもらうと良いでしょう。
短期間で売却できる
再建築不可物件でも、専門の不動産買取業者に依頼すれば「最短3日」で売却・現金化が可能です。
通常の不動産売却は「買い手探し」から始まるため、販売期間が半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
一方で、専門業者は自社で直接買い取るため、仲介のような販売活動が不要です。
そのぶん契約から決済までが圧倒的に早いのが特長です。
例えば、「遠方の空き家をすぐに処分したい」「管理できないから今月中に手放したい」などのご相談でも、現地調査〜査定〜契約まで1週間以内で完了した実例が多数あります。
築古で荒れていても、現状で問題なし。書類さえ揃えば、スムーズに現金化まで進められます。
特に、相続や税金の支払いなど「時間的な制約があるケース」では、このスピード感が大きな安心材料になります。
「いつ売れるか分からない」不安から解放されたい方は、短期間で売却完了できる専門業者への依頼を検討しましょう。
契約不適合責任ナシで売却できる
専門の不動産買取業者に売却すれば、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免除してもらえるケースがほとんどです。
契約不適合責任とは、「売ったあとに欠陥や不具合が見つかったら、売主が責任を負う」ルールのことです。
再建築不可物件のように老朽化していたり構造に問題があったりする場合、一般の買い手からは責任を問われるリスクが高くなります。
一方、買取業者は「その物件の状態を理解したうえで」購入するプロなので、事前に契約不適合責任を免責にする条件での売却が成立するのです。
例えば、雨漏り・シロアリ被害・図面と現況のズレがある物件でも、業者側が了承すればそのまま引き渡しOKです。
「あとでクレームが来たらどうしよう…」とビクビクせずに済みます。
特に相続した物件など、自分では状況を把握しきれない場合には大きな安心材料になるでしょう。
売却後のトラブルを未然に防ぎたいなら、「契約不適合責任の免除」がある買取業者への依頼がおすすめです。
まとめ
この記事では、再建築不可物件を再建築可能にする抜け道や、その手順について詳しく解説してきました。
紹介したとおり、再建築不可物件には「隣地購入」や「セットバック」「但し書き申請」など、法的・技術的に建て替え可能にするための裏ワザが存在します。
しかし、これらはいずれも交渉や申請、費用負担などが伴い、必ず成功するとは限らないハードルがあります。
そんなときに有効なのが、専門の不動産買取業者への売却の選択肢です。
再建築不可物件の取り扱いに慣れている業者であれば、現状のままでも適正価格で買い取ってもらえる可能性があります。
実績豊富な買取業者を選べば、独自の活用ノウハウにより他社よりも高額での売却が期待できる点も魅力です。
実際に、弊社Albalinkではリフォームや再販を前提とした再建築不可物件の買取を多数行っており、多くのお客様に喜ばれています。
「自力での再建築や活用は難しそう…」と感じた方は、まずはお気軽に無料査定からご相談ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!