市街化調整区域とは?家の建て替えと売却の可能性をわかりやすく解説
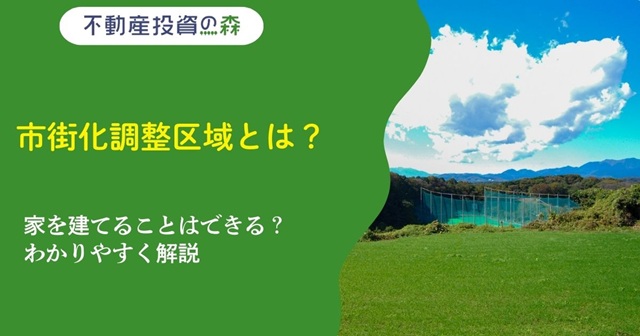
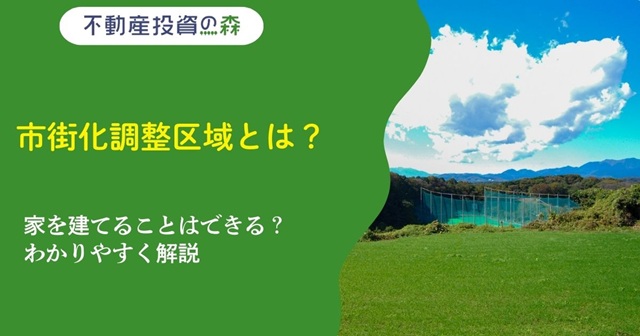
「市街化調整区域にマイホームは建てられるのだろうか…」
「市街化調整区域の土地を購入する際の注意点はあるのだろうか…」
そのようにお考えではないでしょうか?
結論を言えば、市街化調整区域に住宅などの建物を建てることはできません。
しかし、開発許可があれば住宅建設や建て替え、増改築などが可能です。
この記事を読むことで、市街化調整区域の意味や特徴について知ることができます。
また、市街化調整区域の土地を購入する際の注意点についても理解できるでしょう。
市街化調整区域にはマイホームは建てられる?購入する場合の注意点も解説
査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。
目次
市街化調整区域とは市街化を抑制する地域のこと
市街化調整区域とは、都市計画法により「市街化を抑制すべき区域」と定められた地域のことです。
出典:e-GOV「都市計画法 第七条第一項」
乱開発から緑地や農地を守るために設定されました。
そのため、市街化調整区域には住宅やビル、商業施設などの建物を建てることができません。
都市計画法とは
都市計画法とは、街づくりのルールを定めた法律です。
同法では、都市計画の内容や決定の手順をはじめ、都市開発に関する様々な事柄が定められています。
出典:国土交通省「都市計画制度」
都市計画法における3つの区域区分
都市計画法では、都市計画区域の土地を3つの区分に分けています。
| 市街化区域 | 優先的かつ計画的に市街化する区域 |
| 非線引き区域 | 市街化区域でも市街化調整区域でもない区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 |
住宅が建てられるのは市街化区域と非線引き区域です。
市街化区域との違い
市街化調整区域と市街化区域は、土地利用制限や開発許可、税制面などで違いがあります。
| 比較項目 | 市街化調整区域
| 市街化区域
|
| 土地利用の制限 | 原則として住宅・商業施設の建設が禁止(農業関連施設や公益施設は例外) | 用途地域(13種類)に基づき商業・住宅・工業など用途が明確に区分 |
| 開発許可の要件 | 原則として全ての開発行為に許可が必要 | 1,000m²以上(三大都市圏は500m²)の開発に許可が必要 |
| 税制面の違い | 固定資産税が低く設定 都市計画税非課税 | 市街化調整区域よりも固定資産税が比較的高い 都市計画税の課税対象 |
市街化調整区域と市街化区域の区分は、都市の発展や人口動態、土地利用の変化に応じて将来的に見直されることがあります。
自治体による定期的な都市計画の見直しの際に変更が検討されます。
市街化調整区域の特徴
市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぎ、自然環境や農地を守るために指定された地域です。
一般的に土地の価格が安く、静かな環境である一方、生活インフラの整備が遅れていたり、生活利便性が低いといった側面も持ち合わせています。
農地や自然環境が多く残されている
市街化調整区域は、計画的に開発を抑え、緑豊かな空間を守るための区域です。
この地域では、田んぼや畑などの農業地が広く分布し、四季折々の作物が育つ風景が見られます。
また、森や小川といった自然が多く残され、さまざまな生き物の住みかとなっています。
土地の使い方に厳しい決まりがあり、簡単に畑を住宅地に変えることができないため、緑の景観が保たれているのです。
豊かな自然は、水を蓄え、空気をきれいにし、人々に安らぎを与える大切な役割を果たしているといえるでしょう。
土地の金額が安い傾向にある
市街化調整区域は住宅を含む建物が建てられない区域であるため、市場価値が低いです。
そのため、土地の価格が安くなります。
土地の価格が安ければ、当然、土地の地価を基準とする固定資産税の負担額も小さくなるのです。
ただし、固定資産税の評価額は3年に一度見直されるため、評価額が変動することを覚えておきましょう。
交通量が少なく静かな環境である
市街化調整区域は人が少ないため、交通量が少なく非常に静かです。
自然が豊かであるという点は非常に魅力的ですが、自然の音(鳥やカエル、虫などの音)は発生するため、そういった音が苦手な人には向いていません。
生活利便性が低い
開発が制限されている市街化調整区域は、市街化区域と異なり、インフラがあまり充実していません。
例えば、コンビニやスーパーが近くになかったり、公共施設や病院、学校から遠かったりすることがあるため、生活しやすいとは言いにくい環境です。
インフラが整備されていない可能性がある
市街化調整区域は、市街化区域に比べるとインフラが整っていない可能性があります。
ここでいうインフラとは、上下水道やガス、電気、道路の舗装といった設備のことです。
インフラを自分で整えなければならない場合、事前にどのくらい整備費用がかかるか確認する必要があるでしょう。
市街化調整区域にマイホームは建てられる?
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、新たな建築物の建設には厳しい制限が設けられています。
しかし、実際には一定の条件を満たせば、マイホームを建てることは可能です。
ここでは、市街化調整区域での住宅建設を実現するための主な方法や、建築が認められるケースについて詳しく解説していきます。
開発許可を取得する
1つ目は、開発許可を取得することです。
しかし、原則開発が禁止されている地域で開発許可を得るのはかなり困難です。
また、地域によって開発許可を出す基準に違いがあります。
市街化調整区域の開発許可は、都市計画法に基づく全国共通のルールがある一方、実際の運用や細則は各自治体が独自に条例や基準を設けているからです。
たとえば、東京都では「都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例」によって、開発許可を昔から土地を所有している人やその親族、既存集落内に住んでいる人などに限っています。
大阪府の場合「大阪府都市計画法施行条例」で開発許可や独自の基準を示していますが、府内の一部の市町村では独自の運営基準や細則が設けられています。
ただし、自治体の開発ニーズに合っている場合などは、例外的に認められるケースがあるため、市町村役場に問い合わせてみるとよいでしょう。
市街化調整区域内の宅地を購入する
2つ目は、市街化調整区域内にすでにある宅地を購入して住宅を建てることです。
この土地はすでに宅地として登録されているため、新たに開発許可を取得する必要はありません。
ただし、建築時には、自治体への建築確認申請と、承認が必須となります。
建築確認は、例えば自宅兼店舗の建設、既存住宅の建て替え、市街化調整区域内に住む方の本家の親族が分家として家を建てる場合などに認められます。
開発許可を取得済みの土地を購入する
3つ目は、開発許可をすでに得ている土地を購入して住宅を建てることです。
業者によって開発許可が得られ、分譲住宅地として開発されている場合は、自分で許可を得る必要がありません。
こうした土地はすでにインフラが整っているため、住宅を建てやすいといえます。
ただし、市街化調整区域で開発許可が得られている場所は少ないため、早めに完売する可能性があります。
入手できないケースも想定し、他の候補も検討したほうがよいでしょう。
開発許可の不要な人もいる
4つ目は、市街化調整区域内であっても開発許可がいらない人が家を建てることです。
農業や林業、漁業などに従事している人の場合、開発許可がなくても住宅を建てられます。
建築可能なケースと不可能なケースの具体例
市街化調整区域で建築可能なケースと不可能なケースをみてみましょう。
建築できるケース
- 農家の分家住宅
- 既存の宅地
市街化調整区域では、農家の子どもが独立する際の住まい(分家)や、昔から宅地だった場所も可能です。
建築できないケース
- 投資目的の物件
- 大規模な商業施設
一方、収益を目的とした建物、大きなショッピングモールなどは原則として認められません。
ただし、自治体の許可を得られれば新規の住宅建設が可能です。
市街化調整区域で土地を購入する場合の注意点
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定された土地であり、建築物の建設には厳しい規制が設けられています。
そのため、土地購入を考える際には、単に価格だけでなく、様々な制限や条件を理解しておく必要があります。
ここでは、市街化調整区域で土地を購入する際に、特に注意を払うべき重要なポイントについて詳しく解説していきます。
地目を確認する
市街化調整区域の土地を購入する際は、地目の確認が必要です。
※地目
土地の用途のことで、地目は宅地や農地など23種類に限定されている
市街化調整区域に指定される前から宅地であった場合は、建築許可が得られます。
また、農地である場合は一般の人が購入するのは困難です。
農地以外の用途に転用するには、申請が必要であり、申請が通らなかったときは宅地として利用できないため注意しましょう。
市街化調整区域の指定日を確認する
市街化調整区域に指定された日の確認も必要です。
建物の建築日によって、建築許可の要件が変わってきます。
建築年月日が不明である場合は、固定資産税課税台帳などで建築年月日を調べましょう。
条例を確認する
都道府県の条例の確認も行いましょう。
その理由は、市街化調整区域内でも条例によって建築ができる可能性があるからです。
建築可能な区域に指定されていると、利用価値が高まるため、売却時に有利になることがあります。
また、都市計画事業や土地区画整理事業などの開発エリアであっても、建物の建築は可能です。
ただし、建築には事前に許可を取得する必要があります。
インフラが整備されているか確認する
市街化調整区域はインフラが整備されていない可能性があるため、購入前にインフラの状況を確認しましょう。
インフラが整っていない場合は自分で整備しなければならないため、購入前に費用の見積もりを行う必要があります。
主なインフラ整備費用は、以下の通りです。
| 項目 | 費用目安 |
| 上下水道の新規引き込み | 50~150万円 |
| 受水槽の設置 | 40~50万円 |
| 下水道の新規引き込み | 0~100万円 |
| 下水道未整備地域の浄化槽の設置 | 50~100万円 |
| 都市ガスの引き込み | 0~50万円 |
| 電柱の移設費用 | 0~20万円 |
購入後に住宅を建てる場合は、インフラ整備費用を上乗せして予算を建てたほうがよいでしょう。
住宅ローンが通りにくい
利便性が低い市街化調整区域は、住宅ローンが通りにくいため注意が必要です。
多くの銀行が融資対象外としている一方で、一定の条件を満たせば融資可能な場合もあります。
市街化調整区域での土地購入を検討されている方は、住宅ローンに精通した不動産アドバイザーに相談したほうがよいでしょう。
建て替えや増改築にも自治体の許可が必要になる
既存の住宅であっても、建て替えや増改築を行う際には、自治体の許可が必要です。
たとえば、平屋の住宅を3階建ての住宅に改築してしまうと、周辺の景観に大きな影響を与える可能性があります。
市街化調整区域における開発・建築許可は、厳格な審査基準が設けられています。
住宅の規模拡大や用途変更を計画する場合、詳細な計画書の提出が求められますので、事前の慎重な検討が重要です。
将来の売却可能性を考慮する
市街化調整区域の土地は開発が制限されたエリアのため、住宅地として指定された地域と比べて取引が少なく、売りにくい特徴があります。
一般の居住区域では数か月で買い手が見つかることが多いのに対し、制限区域では1年以上かかることも珍しくありません。
価格も通常より安い傾向にありますが、将来的に売る際には更に値下げが必要になることもあります。
これは建物の新築や用途変更の制約があり、農業関係者など特定の方しか購入対象にならないためです。
金融機関からの借入も難しく、インフラ整備も不十分な場合があります。
以上のことから、将来の売却が容易ではないことを認識したうえで市街化調整区域を購入するべきでしょう。
市街化調整区域の建物の建て替えと売却について
市街化調整区域にある建物の建て替えや売却は、一般の宅地とは異なる制限があるため注意が必要です。
ここでは具体的な条件や対策を解説します。
既存建物の建て替え条件と制限
市街化調整区域における既存建物の建て替えや増改築、リノベーションには、原則として自治体の許可が必要です。
建て替えの際は、建蔽率や容積率の制限が適用され、建蔽率は30%から70%、容積率は50%から400%の範囲になることが多く、具体的な数値は特定行政庁が定めます。
また、既存建物と比べて著しく規模を拡大することは認められない場合が多く、建て替え後の延床面積が従前と同程度であることが条件となることもあります。
自治体ごとに基準が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
また、建て替えや増改築の際には、既存建物の規模を大幅に拡大することは認められず、延床面積が従前の1.5倍以内などといった条件が設けられる自治体もあります。
買い手が見つかりにくい理由とは?
市街化調整区域の土地は買い手が付きにくい傾向にあります。
住宅ローンの面では、多くの金融機関がこうした区域の物件に対して審査を厳しくしているからです。
担保価値が低く評価されがちで、融資条件が厳しくなるため、購入希望者の選択肢が狭まってしまうのです。
将来の資産価値においても不安要素があります。
市街化を抑制する地域のため開発が制限され、周辺環境の発展が見込みにくく、将来的な価値上昇が期待できません。
生活面では、商業施設や病院などが少なく、公共交通機関の便も悪いことが多いです。
上下水道などのインフラ整備も十分でない場合があり、日常生活に不便を感じることが少なくありません。
こうした複合的な理由から、市街化調整区域の不動産は買い手が限られてしまうのです。
売却を成功させるためのポイント
市街化調整区域の土地は建築規制があるため、販売が困難な場合があります。
成功させるためには適切な価格設定が重要であるため、実際の取引事例を参考に、現実的な金額を設定しましょう。
物件の魅力を最大限に伝えることも大切です。
広い敷地や自然環境など、この区域ならではの特徴をアピールしましょう。
また、農業用地や資材置き場など、特定用途に適した買い手を見つける工夫も効果的です。
売却前には、境界確認や権利関係の整理を行っておきましょう。
専門家(不動産会社や行政書士など)に相談し、開発許可の有無や建築条件を確認することで、購入検討者に正確な情報を提供できます。
相続した市街化調整区域の土地の活用法
市街化調整区域の土地を相続した場合、いくつかの活用方法があります。
たとえば、農業を続けるか、近くの農家に貸すことができます。
区画を分けて市民に貸し出す農園にする方法も有効です。
太陽光パネルの設置も可能ですが、大きな工事を伴う場合は許可が必要となります。
あるいは、駐車場や資材置き場としての活用も初期費用が少なく始めやすいでしょう。
また、相続した土地は、固定資産税の評価額に一定の数値をかけて相続税が計算されます。
市街化調整区域の土地は住宅地より評価が低いことが多く、税金が抑えられる可能性があります。
加えて、農地として使えば評価がさらに下がり税金が減るかもしれません。
詳しくは税の専門家への相談をお勧めします。
まとめ
今回は、市街化調整区域内に住宅を建てられるかをテーマとして解説してきました。
開発が制限されている地域であるため、許可なく住宅は建てられませんが、絶対に建てられないわけではないということがわかりました。
市街化区域や非線引き区域に比べると土地の価格が安く、税負担も軽いというメリットがある一方で、開発許可が得にくいというデメリットがあります。
そのため、よくわからずに市街化調整区域内の土地を買ってしまうと、後悔することになるかもしれません。
市街化調整区域の物件の売買について知りたい方に検討していただきたいのが、こうした物件のノウハウを持つ不動産会社の活用です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、訳あり物件の買取を数多く手がけてきた実績を持つ不動産会社であり、市街化調整区域の物件についても数多く取り扱ってきました。
査定や相談だけでも可能ですので、ぜひ一度気軽にご相談ください。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!











