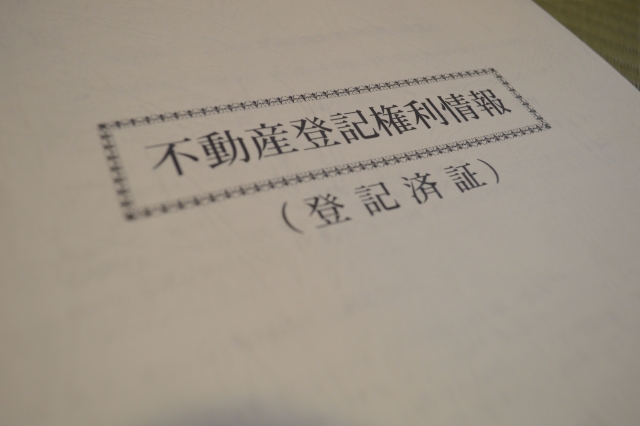銀行ローンを組むときに、虚偽の資料提出で詐欺になる?バレたらどうなるのか元弁護士が解説

不動産投資ローンなどの融資を受けるとき、契約者の年収や資産に関する資料が必要となります。
このとき、年収や預貯金の金額が高いほうが、返済能力や貸し倒れのリスクが少ないと判断され、有利になります。
そのため不動産業者によっては、虚偽の年収や資産の資料を金融機関に提出させて、不正に融資を受けさせようとするケースがあるため注意が必要です。
不動産投資を行うにあたって、こうした不正に巻き込まれた場合、どのようになるのでしょうか?
数年前、いわゆる「かぼちゃの馬車事件」が話題になりましたが、スルガ銀行の融資審査の際に虚偽資料が使われたとも。
今回は、ローンを組む際に、虚偽の資料を提出すると詐欺になるのか、金融機関にバレるとどうなるのか解説します。
空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
目次
ローン審査と必要書類について
自宅を購入するときや不動産投資を行うときには、多くの場合、銀行でローンを組む必要があります。
これは不動産は高額であり、自己資金だけで購入代金を支払うのは現実的に難しいためです。
特に不動産投資の場合、2億円、3億円とった億単位の資金が必要になるケースも珍しくありません。そのため、ローンの利用はほぼ必須といえるでしょう。
ただし、銀行ローンを利用するには必ず「審査」があり、審査に通過しなければ希望金額を借り入れることはできません。
そして、融資審査の際に重視されるのが、年収や預貯金額などを示す資料です。
本来であれば、正確かつ真正な資料を提出し、その内容をもとに融資の可否を判断してもらう必要があります。
しかし近年、特に不動産投資ローンの分野では、債務者の年収や預貯金額を偽造した資料で審査を受けるケースが相次いでいるようです。
一体、なぜこのような事態が起きているのでしょうか?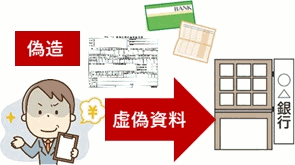
スマートデイズがシェアハウス融資で書類を偽造?
今回取り上げる不動産会社は、「スマートデイズ」という会社です。
同社は、「かぼちゃの馬車」というシェアハウスシリーズを展開していた企業で、かつては多くの不動産投資家を呼び込み、自社がサブリース(家賃保証)契約の管理会社として関与することで利益を上げていました。
しかし、その後経営が破綻し、オーナーに約束していた賃料(家賃保証分)支払われなくなったことで大きな問題となりました。
そして、その後新たに「融資書類の改ざん」という不正が明らかになりました。
同社の顧客である不動産投資家が金融機関から融資を受ける際、年収や預貯金の資料を改ざんした虚偽書類が多数提出されていたのです。
たとえば、預金額や年収額を大幅に水増しし、投資家(債務者)の信用力を実際より高く見せかけ、多額の融資を引き出していたケースが典型例です。
これらの融資の多くは、静岡県に本店を置く「スルガ銀行」で実行されたとされています。
「かぼちゃの馬車」事件では、不動産投資家が一棟のシェアハウスを購入し、スマートデイズにサブリースで貸し出す仕組みを採用していました。
1棟単位の購入となるため借入金額も高額になり、多くの投資家が1億円を超える融資を受けていました。
このような高額な融資を通すために、スマートデイズ、または不動産仲介業者などが常態的に融資関連書類を偽造していた可能性が高いと考えられます。
どのような人が不正融資を受けていたのか
今回の件では、多くの「かぼちゃの馬車」投資家が不正な形で融資を受けていたことが判明しています。
では、この「不動産投資家」とは一体どのような人たちなのでしょうか。
1億円を超える融資を受けていると聞くと、資産家や富裕層を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。
シェアハウス投資に関わっていた人の多くは、一般的なサラリーマンやOLでした。
年収が数百万円の普通の会社員が、副業としてシェアハウス投資を行っていたケースが大半です。
本来であれば高額融資を受けられない層が多かったため、年収や資産を水増しした偽造書類が使われていたというのが実情です。
また、不動産投資ローンを扱う金融機関は多数ありますが、当時のスルガ銀行は比較的審査が緩く、融資を受けやすい銀行として知られていました。
そのため、年収がそれほど高くない一般の会社員でも融資を受けられる可能性があり、スマートデイズはスルガ銀行を好んで利用していたと考えられます。
投資家本人や家族も驚きの声
今回、スマートデイズが書類を改ざんし、不正に多額の融資を受けさせていたことが明らかになりましたが、融資を受けた本人がその事実を知らされていなかったケースが多く見られます。
事件が発覚した経緯も、スマートデイズが投資家に家賃保証分の賃料を支払わなくなったことに端を発しています。
その結果、投資家(多くは一般のサラリーマン)がスルガ銀行への返済を続けられなくなり、返済猶予を求めた際に不正が発覚しました。
つまり、スマートデイズが家賃保証の約束を破ったことでローン返済が困難になり、銀行に相談したところ、提出されていた虚偽の年収・預貯金資料が明るみに出たのです。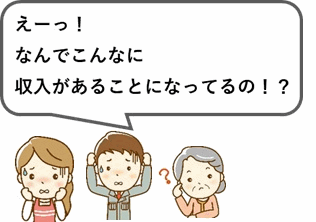
このことで、驚いてツイッターに書き込みをしている方もおられます。
【速報】旦那の年収は実は1,000万で、預金も6,000万近くあることが判明!
もう、めちゃくちゃすぎて、心臓がドキドキしています…。
— 悟子 (@uSpebGNvhje1O17) 2018年2月17日
この投稿者の夫が不動産投資をしていたようですが、本人達も知らないうち不動産業者が虚偽の年収、預貯金額を記載した書類を提出していたことを知り、強い衝撃を受けておられます。
さらに、ご自身でも調査されたようです。
役所の書類は正しいままで、年収600万を1,000万にする手法。それは、確定申告で虚偽の申告をすることでした。
・まず、申告日時点で倒産している企業を探す
・その企業からの給与を確定申告で申告する
・2年前のは、修正申告する以上です。主人は、これを知らない間にされていました。
— 悟子 (@uSpebGNvhje1O17) 2018年2月19日
その手口を整理すると、以下の通りです。
- 申告日において倒産状態の会社を探す
- その企業から給与を受けとっていたとして虚偽の確定申告をする
- 過去の収入も修正申告で書き換える
かなり手が込んでいて悪質な方法です。このようなことを、契約者本人が知らないまま業者が行っていたというのです。
この事件からわかるのは、不動産投資の融資において、自分の知らない間に勝手に不動産業者が資料を偽造して不正に融資を受けさせようとすることがあるということです。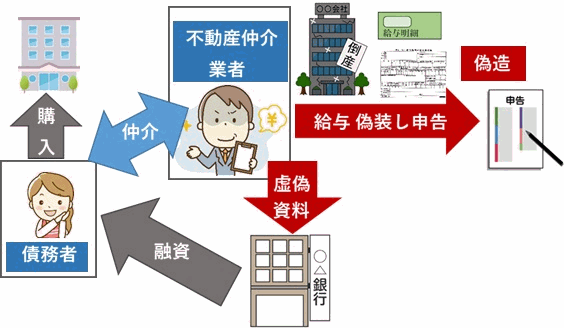
なぜ、書類改ざんが可能なのか
今回、スマートデイズはシェアハウス投資において、債務者の信用力を示す資料を偽造して融資を受けたとされています。
では、なぜこのような不正が可能だったのでしょうか。
業者に手続きを一任する仕組み
まず、このような大規模なサブリース型の不動産投資では、サブリース業者と提携する複数の不動産仲介業者が窓口となっていることが一般的です。
投資家は融資を申し込む際、これらの仲介業者に預金通帳の写しや収入証明などを預け、手続きを一任するケースが多く見られます。
つまり、債務者本人が直接手続きを行わない点が、不正が介入しやすい構造となっていたといえます。
不動産業者による偽装手口
一部の不動産業者は、営業成績を上げるために、本来なら審査に通らない融資を強引に通そうとする場合があります。
その手段として、以下のような手口が確認されています。
- 預金残高のコピーを加工し、実際より10倍以上多く見せかける
- 投資家が不動産会社に高額な頭金を振り込んだように偽装する
- 休眠会社や倒産企業を利用し、虚偽の確定申告書を作成する
このような行為により、実際には存在しない資金や支払い能力を装って融資を受けるケースが発生していたのです。
一部の仲介業者が不正を認めた
前述のとおり、今回の件に関与した不動産仲介業者の一部は、不正行為を行った事実を認めています。
ただし、誰がどのような手口で不正を行ったのか、その詳細は明らかにされていません。
また、スマートデイズ自身も本件について公式なコメントを出さず、沈黙を続けています。
まさか、この図が新築シェアハウスのみで行われてるなんて思ったら大間違い。賃料の水増しや預金改竄はスルガの殆どの貸出で行われてるんだから圧倒的な改竄率と貸出額を占める中古市場にもメスを入れるべきよ
— 電卓ん(元電話くん) (@denwa_oniden) 2018年2月20日
この方が指摘するように、今回のスマートデイズの件は、氷山の一角かも知れません。
不動産投資ローンの業界では、こうした書類の偽造が常態化しているとの意見もあるのです。
なお、「かぼちゃの馬車」事件で販売していた不動産仲介業者2社が朝日新聞社の取材に応じていますが、両社とも自社の関与を否定しています。
これらの状況を見ると、問題の全容解明には依然として時間がかかる段階にあるといえるでしょう。
スルガ銀行の対応について
一方、今回の不正融資問題に関して、渦中のスルガ銀行はどのように対応しているのでしょうか?
まず、同行は「なぜシェアハウス投資への融資を積極的に行っていたのか」という質問に対して、次ののように説明しています。
「シェアハウスは、新しい形の収益性不動産投資であり、将来有望と考えたから」
「総額でどのくらい融資をしたのか?」という質問に対しては、「具体的な融資額は答えられない」としています。
さらに、預金残高の水増しなど書類の不正については、次のように説明しています。
「融資の実行後に、一部でそういった不正があることが判明した」
現時点において、同行の職員不正に関与した形跡は見られないとのことです。
さらに、スルガ銀行は次のような声明を発表しています。
「(当行の手続きの不備に起因するかどうかに関わらず)、本件のようなことは許されることではない」
同行は、今回の件を重く受け止めて、自社で独自に調査を開始したとも明らかにしています。
現時点で得られている情報から判断すると、スルガ銀行が直接不正に関与していたわけではなさそうです。
ただし、同行の調査により、融資審査や監査体制の問題点が明らかになる可能性があります。
虚偽の書類で融資を受けると詐欺になるのか?
今回、スマートデイズや不動産仲介業者が虚偽の資料を提出して不正に融資を受けていたとされています。
それでは、このような行為は法律上どのような問題を生じるのでしょうか。まずは、「詐欺罪」になるのかどうか、見てみましょう。
不正融資は詐欺にあたるのか
虚偽の資料を使って金融機関から融資を受けた場合、刑法上の「詐欺罪」に該当する可能性が高いです。
詐欺罪は、「欺罔行為によって」「相手を錯誤に陥らせて」「財産を処分させることにより」「財物や利益を得た」ときに成立する犯罪です。
具体的な要件を見ていきましょう。
欺罔行為(ぎもうこうい)
欺罔行為とは、相手を騙す行為です。
書類を偽造して金融機関に提出することは、年収や資金力を偽り、金融機関を騙す行為と言えます。
錯誤
相手が事実を「誤認」することです。
金融機関は、提出された虚偽の資料によって、申込者に実際より高い収入や資金力があると思うわけで、錯誤があったと言えます。
処分行為
処分行為とは、財産や利益を相手に交付することです。
銀行融資のケースでは、融資を実行して相手の口座に融資金が振り込まれることが処分行為といえます。
財物や利益の取得
だました側が利益を得ることです。
今回の事案で、不動産仲介業者やスマートデイズは、直接お金を受けとるわけではありませんが、契約者が不動産の購入契約を締結することで利益を受けることになります。その限度で財物や利益を得たと評価できる余地があります。
損害発生
被害者側に経済的損失が生じることです。
金融機関は、本来なら融資を行わなかったはずの相手に資金を渡してしまったため、錯誤に基づく財産的損害が発生しています。
故意
故意は、だました側が「わざと」行ったことです。
虚偽の資料を意図的に作成・提出していれば、故意が認められます。逆に、本人がその偽造を知らなかった場合には、故意がなく、詐欺罪は成立しません。
不動産仲介業者の責任
不動産仲介業者は、今回の詐欺行為の中心的な役割を果たしていた可能性が高いと考えられます。
彼らは実際に虚偽の書類を作成・提出し、金融機関を誤信させる欺罔行為を行っていました。
さらに、書類を意図的に偽造して融資を通そうとしていたことから、明確な故意(わざと行った意思)も認められます。
そのため、不動産仲介業者には詐欺罪が成立する可能性が極めて高いといえるでしょう。
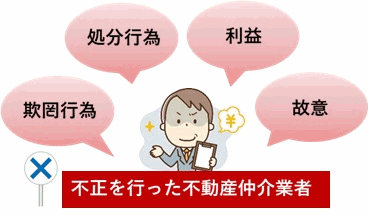
スマートデイズの責任
次に、スマートデイズの責任を見てみましょう。
現時点で明らかになっているのは、書類の改ざんを実際に行ったのは不動産仲介業者であるという点までです。
そのため、スマートデイズがどの程度関与していたかによって、責任の有無や刑事的評価が大きく変わります。
たとえば、スマートデイズが仲介業者に対して書類の偽造を指示・黙認していた場合には、詐欺の共犯または教唆犯として刑事責任を問われる可能性があります。
一方で、書類の偽造を仲介業者が独断で行い、スマートデイズが一切関与していなかった場合は、同社に刑事責任が及ばない可能性もあります。
最終的な判断は、今後の調査や関係者の供述内容によって明らかになるでしょう。
投資家(債務者)の責任
それでは、融資を受けた投資家本人の責任について見ていきましょう。
今回のケースでは、書類の偽造やその他の欺罔行為を行ったのは不動産仲介業者側であり、投資家自身が関与していない事例が大半です。
また、多くの投資家は、不正が行われていたことすら知らされていなかったため、詐欺罪の成立に必要な「故意(わざと行った意思)」がありません。
したがって、投資家本人に詐欺罪が成立する可能性は低いと考えられます。
ただし、投資家が不動産業者と共謀して虚偽の書類を提出し、不正に融資を受けていた場合には、詐欺罪が成立する余地があります。

銀行員の責任
最後に、銀行員の責任を見てみましょう。
今回の件で、「銀行」そのものは被害者の立場ですが、「銀行員」は詐欺の共犯になる可能性があります。
なぜなら、銀行と銀行員は、法的に別人格だからです。
したがって、銀行員が、事情を知ったうえで不動産業者と結託し、意図的に融資を実行していた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
さらに、銀行員は勤務先である銀行の利益を損なう行為をしているため、刑法の背任罪に問われる可能性もあります。
これらの行為が発覚した場合、懲戒処分や解雇などの処分を受ける可能性が高いでしょう。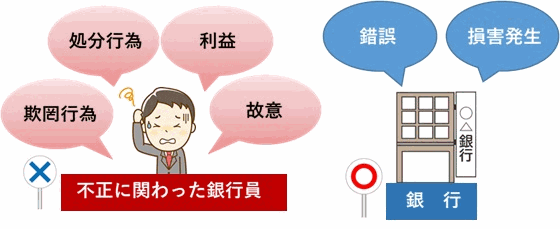
実際に詐欺罪で逮捕される事例はあるのか
銀行から不正な形で融資を受けた場合、実際に詐欺罪で逮捕されることはあるのでしょうか?
答えはイエスです。実際に逮捕されたケースがあります。
たとえば、旅行会社「てるみくらぶ」の事例があります。
同社の代表者は、複数の銀行から総額5億円以上の融資を受けていたものの、実際には会社の経営状態を偽装し、利益を水増しした虚偽の決算書を提出して融資を受けていました。
その結果、代表者は詐欺罪で逮捕・起訴されています。最終的には、実刑を含む厳しい刑罰が科される見通しとなりました。
この事例は、今回のスマートデイズの件と性質が近い融資詐欺です。「虚偽資料を提出して融資を受ける」という点で全く同じ構造といえるでしょう。
融資詐欺は、単なる「書類の誤り」ではなく、刑法上の重大な犯罪にあたり、場合によっては逮捕・懲役刑に処される可能性もあります。
投資家にはどのような影響が及ぶのか
これまで見てきたとおり、不動産投資ローンで虚偽の年収や資産資料が提出された場合でも、投資家本人に故意がなく、業者が独断で行った場合には詐欺罪が成立しない可能性が高いといえます。
しかし、刑事責任を免れたとしても、投資家側がまったく影響を受けないわけではありません。
ここからは、借り入れを行った投資家(債務者)にどのような影響が及ぶのかを見ていきましょう。
残金を一括請求される可能性
このようなケースで最も大きな問題となるのが、ローン残高の一括返済(期限の利益喪失)を求められる可能性です。
不動産投資ローンを組む際には、通常、金融機関との間で「金銭消費貸借契約書」を締結します。
この契約書には、債務者に不正行為があった場合や、契約条件と異なる事実が発覚した場合には、次のような条項が定められていることが一般的です。
- 金融機関が契約を解除できる
- その時点の残債を一括請求できる(期限の利益を喪失させる)
したがって、虚偽の資料によって融資が実行されていたことが発覚した場合、銀行は契約条項に基づき融資金の回収に着手することが可能となります。
ここで注意すべき点は、債務者に「故意」がなくても一括請求が行われる場合があることです。
これは、残金一括請求や契約解除は刑罰ではなく、契約上の効果として行われる措置だからです。
つまり、融資条件に虚偽があった以上、債務者が知っていたかどうかにかかわらず、金融機関に契約解除権や期限の利益喪失を認めることは、法的にも妥当とされています。
融資を受ける際には、必ず金銭消費貸借契約書の内容を確認し、リスク条項を理解しておくことが重要です。
住宅ローンでも、残ローンの一括請求されることはある
このような契約違反に基づく残金一括請求は、不動産投資ローンだけではなく、住宅ローンでも発生する可能性があります。
住宅ローンと不動産投資ローンを比較すると、一般的に住宅ローンは金利が低く、審査が比較的緩い点が特徴です。
そのため、本来は自己居住用として借り入れた住宅ローンを、実際には投資目的(賃貸用物件の購入など)に流用するケースが見受けられます。
しかし、これは明らかな契約違反です。
金融機関が事実を把握した場合、契約違反条項に基づいて残りの住宅ローンを一括返済請求されることになります。
一括請求された場合の対処方法
もし現在利用している金融機関からローンの一括返済を求められた場合、まず考えられる対応策は、他の金融機関に借入を申し込み、その融資を返済資金に充てることです。
たとえば、所有している不動産の収益性が高く、運用実績や将来性が認められる場合には、他行から新たな融資を受けられる可能性があります。
しかし、今回のような不正が関係しているケースでは、信用情報機関に「事故情報」として登録されるリスクがあります。この場合、他行への借入申請自体が難しくなります。
最悪のケースでは、新たな融資を受けられず、自己破産を選ばざるを得なくなる可能性もあります。
一括請求を受けた場合は、早期に専門家(弁護士・司法書士など)へ相談することが重要です。
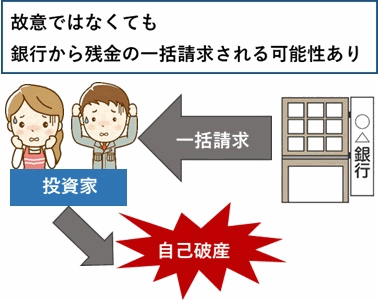
なお、債務整理や自己破産に関する情報は「債務急済」というサイトが参考になります。
「債務急済」は株式会社WEBYが運営する、弁護士・司法書士の検索サイトです。
自己破産、個人再生、任意整理、代表者の破産/倒産、銀行借入の返済が難しく破産を検討されている事業主様など、様々な状況に応じた地域の専門家を探すことができます。
>>債務整理についてはこちらのサイトを参考にしてみてください
必ず一括請求されるのか?
「かぼちゃの馬車」のように、不動産業者が大規模な不正を行い、債務者本人には一切知らされていなかったケースでは、債務者はむしろ「被害者」といえる立場です。
このような場合でも、金融機関は債務者に対して残債の一括返済を求めてくるのでしょうか。
結論としては、金融機関の判断次第です。
銀行は社会的責任を負う存在であり、契約上は一括請求が可能でも、必ずしも強制的に実行するとは限りません。
被害者の数が多く、かつ債務者が不正に関与していない場合には、銀行側も事情を考慮し、一括返済を求めない判断を取ることもあります。
実際、現時点(報道当時)では、スルガ銀行が投資家に対して一括請求を行ったという情報は確認されておらず、自主調査を進めている段階です。
ただし、銀行も営利企業である以上、返済能力の低い借り手に高額融資を続けることにはリスクがあります。
そのため、一括請求をしない場合でも、融資条件の見直しや金利の引き上げといった対応を取る可能性もあります。
まとめ
今回は、シェアハウスのサブリース事業「かぼちゃの馬車」に関連する、不動産投資ローンの不正融資問題を取り上げました。
虚偽の資料を提出して不正に融資を受ける行為は、刑法上の詐欺罪に該当し、逮捕・起訴される可能性があります。
たとえ刑事事件に発展しなくても、金融機関に発覚すれば、ローン残高の一括返済を求められるなどの重大なリスクを負うことになります。
したがって、不動産投資や住宅ローンを利用する際には、決して不正を行わず、誠実に手続きを進めることが何より重要です。
また、書類の改ざんや虚偽申告を勧めるような悪質な不動産業者には関わらないよう、十分に注意しましょう。
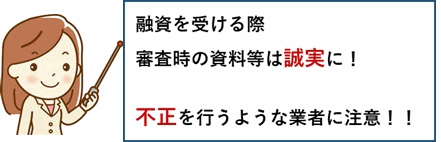
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!