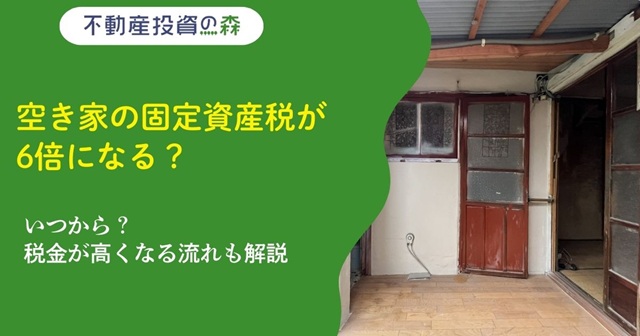実家じまいを決断するタイミングは?費用や手順についても解説


「親しか住まいない実家を将来的にどうするのか?」
核家族化が進んだ現代では、このような実家に関する悩みを誰でも持っているでしょう。
実際、実家を相続後に処分せず所有を続けることで、維持管理の手間や負担に悩まされ、なかには放置してしまうケースもあります。
よって、住まいない実家は早めに処分するがおすすめです。
本記事では、実家じまいについて詳しく解説します。
最後までお読みいただくと、実家じまいの方法や流れ、費用や注意点がわかり円滑に行えるようになるでしょう。
また、将来的に実家の所有に悩むこともなくなります。
目次
実家じまいとは親が住む家を処分すること
実家じまいとは、親が住んでいる家を独立した子が整理して処分することを言います。
似たような言葉に「家じまい」があります。
これは、親自身が家を処分することです。
子が実家を処分すれば「実家じまい」、親が自ら行えば「家じまい」と区別しておきましょう。
実家じまいをする人が増えている背景
今、実家じまいをする人が増えています。
その理由は、相続登記が義務化されたからです。
相続人が明確になることで、所有者には固定資産税等の税負担や維持管理の費用負担や手間をかけることが必要となりました。
今まで曖昧であった相続後の不動産の扱いが明確になったので、将来的に維持管理できない不動産については早めに手放す傾向があります。
実家じまいを決断できない心理
実家じまいの必要性を理解していても、なかなか行動に移せない場合が多いものです。
その理由のひとつとして「片付けたり処分が必要な物が多くてどこから手をつけたら良いかわからない」という声があります。
自分の仕事や家事のかたわら、実家の片付けをする時間はなかなか取れません。業者に依頼するとなると、費用も安くはありません。
経済的な事情から、なかなか実家じまいが進まないというケースはよくあります。
また、「実家が無事に売却できるだろうか?」という不安もあります。特に相続した実家の場合は、相続人の意見がまとまっていないと売却することもできません。まずは実家をこれからどうするのか、相続人同士でよく話し合うことから始めましょう。
「いつまでも売れなかったらどうするのか」など気がかりなことは、相続に強い不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
意外に多いケースとして、「思い出の詰まった実家を処分するのは寂しい、気が咎める」という心理もあります。
このような心理の背景には「親に申し訳ない」という思いもあるかもしれませんが、多くの場合は取り越し苦労です。
中心になって動く人へ配慮して、心理的にも金銭的にも負担が一人に集中しないようにしたいものです。
実家じまいをするタイミング
本章では、実家住まいをする主なタイミングについて解説します。
相続が発生した時
最も多いのが、実家の相続が発生したときです。
なぜなら、実家を所有するだけで固定資産税等の税負担や、日常的な維持管理に手間がかかってしまうからです。
また、早めに処分しなければ建物の価値が下がり、放置すれば近隣からの苦情やトラブルが起きるリスクもあるでしょう。
よって、一般的に実家じまいをするタイミングは相続時と言えます。
親が老人ホームや施設へ入居する時
親が老人ホームなどの介護施設に入居するときです。
なぜなら、実家に誰も住まなくなり、日常的に清掃等の維持管理をする人がいなくなるからです。
また、症状によっては今後家が不要になることや、介護施設の入所にかかる費用を家の売却資金で賄うこともあるでしょう。
よって、親が介護施設に入所するタイミングで実家じまいをするケースがあります。
実家での暮らしが不便になった時
実家での暮らしが不便になったときです。
たとえば、家が広すぎて不便に思う時があります。
子が独立して部屋が余っていることや、足腰を悪くして階段が登れずに家の二階部分を全く使っていないことがあるでしょう。
また、田舎など立地が悪ければ、公共交通機関が少ないことで通院や買物がしづらく、不便に思います。
よって、このような実家での暮らしに不便さを思い始めたときが、実家しまいをするタイミングです。
実家を空き家のままにしておく問題点
実家じまいは時間やお金も労力もかかり、精神的な負担が大きく、ついつい先伸ばしにしたまま、手がつけられないケースが多いものです。
ですが、だからといって、実家を空き家のまま放置しておくと、維持のための費用面や税制面での損失、近隣への迷惑など、さまざまな問題が発生します。
税金・維持費などの費用が余分に発生する
人が住んでいなくても、住宅や土地には固定資産税などの税金がかかります。
また、空き家の適切な維持管理のためには費用がかかります。
自分たちで維持管理する場合、定期的な草刈りや植木の剪定、建物の補修に費用がかかり続けます。
実家が遠方であれば、交通費も軽視できないでしょう。
最近では、空き家の日頃の見回りや清掃などを請け負う空き家管理会社もありますが、プランによっては月に1万円以上かかります。
これを怠り、管理が行き届かなければ「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、自治体に「特定空き家」に指定されてしまう場合があります。
「特定空き家」とされる状態は以下の4つです。
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
このような状態にある空き家を、建築物そのものの傷み具合と、周囲に及ぼす影響、その危険度や切迫度を総合的に判断して「特定空き家」と指定されます。
特定空き家に指定された場合は、固定資産税などの住宅用地としての特別控除が受けられなくなり、税額が最大6倍になる可能性があります。
参照:国土交通省:「空家等対策の推進に関する特別措置法」
3年以上放置すると税金の特別控除を受けられない
空き家になってから3年以内に売却した場合、売却額から最高で3,000万円が非課税となり、大幅な節税となります。
3年以上経った場合や、空き家を解体して更地にしてしまった場合にはこの控除が受けられないので、節税対策の面でも空き家を売却すると決めたら1日も早く売るべきでしょう。
国税庁:マイホームを売ったときの特例
物件の価値が大幅に下がる
日常的に人が住んでいない家は老朽化が早く進みます。
同じ築年数でも、人住み続けている家と空き家では傷み具合が異なります。
なぜなら、人の住んでいる家では、雨漏りや虫害などに気づくのが早く、それだけ早めに修理や補修が可能です。
空き家の場合は発見が遅れ、気づいたときにはかなり被害が大きくなっている場合が多いものです。
そのため「空き家」である期間が長いほど物件の価値は下がります。
犯罪リスクの高まりと近隣への悪影響
「どうせ空き家だから、泥棒が入っても盗むものはない」と思っている人もいるかもしれません。
ですが、近年は、窃盗以外で空き家が狙われるケースが増えています。
たとえば、違法薬物や特殊詐欺の取引のために空き家の住所を悪用する例です。
そのほかにも、敷地内へのゴミの不法投棄や、放火などの危険もあります。
このように空き家があることで犯罪リスクが高まり、近隣住民へ多大な迷惑を及ぼす可能性があります。
隣家が空き家であるとか、空き家の多い地区は防犯上、購入希望者に敬遠されがちで、地域全体での相場価格を下げてしまう可能性があります。
実家じまいの手順と方法
実家じまいにかかる期間は、実家の処分の方法や家の規模によってさまざまですが、実際に「実家じまいを決断」してから行うべきことの手順とおよその期間をまとめました。
家の規模は標準的な30坪一戸建てを想定しています。
| 行うこと | 期間 | 依頼先など | |
| 1 | 家族で方向性を話し合う | 相続の場合は相続開始後3ヶ月以内 | 相続人、家族(必要なら弁護士、司法書士) |
| 2 | 親の転居先を決める | できるだけ早く | ケアマネージャーなど |
| 3 | 不動産業者など必要な業者に相談する | 平均3〜6ヶ月(仲介売却の場合) 1ヶ月以内(買取会社の場合) | 不動産会社、不動産買取会社、不用品回収業者、遺品整理業者、ゴミ屋敷片付け業者など |
| 4 | 不用品や残置物を処分する | 1〜3日(業者委託の場合) 家族で行う場合はさらに長期間かかる場合もある | 不用品回収業者、遺品整理業者、ゴミ屋敷片付け業者など |
※ 3と4は、並行して行うことが望ましい。仲介売却を検討する場合は、不動産会社が売却営業を始める前に家を空けておく必要があります。(買取業者の場合は現状買取も可能な場合があります)
家族で方向性を話し合う
はじめに、今後の方向性を話し合うことから始めます。
なぜなら、方向性が一致しなければ、今後の親族間の人間関係に大きな影響があるからです。
たとえば、相続開始後であれば相続人間、親が存命中であれば親と兄弟間での話し合いとなります。
実家の処分、解体後の土地活用など、立地や周辺需要などを鑑みて決めていきます。
親の転居先を決める
親が存命中の場合には、転居先を決めます。
転居先がなければ、実家じまいはできないため、迅速に候補物件を絞っておきます。
転居先は民間賃貸住宅、公営住宅、高齢者施設等がありますが、最も重視すべきは親が安心して暮らせることです。
親の転居先は、話し合いや物件見学などを行いながら慎重に決めていきましょう。
不動産業者など必要な業者に相談する
実家じまいに向けて、必要な業者に相談します。
実家の売却であれば、不動産仲介会社、あるいは不動産買取業者です。
仲介売却の場合、築年が浅い、立地がよい場合は、相場価格に近い価格で売却できることもあります。
ただし、売却までには早くても3ヶ月はかかります。
買取業者であれば、買取価格は相場価格より安くなりますが、早期に売却可能です。
家の中にある家財道具など、不用品の処分は不用品回収業者、場合によっては、遺品整理業者、ゴミ屋敷片付け業者に相談するとよいでしょう。
不用品回収業者は、中古家電製品や古物商に売却して利益が出るもの以外は廃棄物として処理してしまいます。
市場的に価値がなくても、思い出のある品や写真など捨ててしまいたくないものがあるとき、あるいはコレクションなど素人では価値の判断が難しいものがある場合は、遺品整理業者や「家じまいアドバイザー©︎」の資格を持つ業者に相談することをおすすめします。その場合は、料金が割高になることや、作業に時間がかかる場合もあるので注意しましょう。
実家がゴミ屋敷で、衛生的な問題がある場合は、通常の業者ではなくゴミ屋敷専門の片付け業者に相談しましょう。
実家じまいは専門家の助言がなければできないため、売却に先立って早めに相談しておきましょう。
不用品や残置物を処分する
実家じまいの最初は、家財等の不用品を処分することです。
たとえば、衣装ケースや本棚など粗大ゴミとして処分できるものは、自治体が運営する処分場への持ち込み等で処分できます。
また、家電製品については家電リサイクル法に基づき、適切な処分が必要です。
なお、大型家具等は個人での搬出が難しいケースが多いため、不用品回収業者等に処分を依頼しましょう。
実家じまいには、室内や敷地内にある粗大ゴミや不用品等の処分が必要です。
実家を処分する
最後に、実家を処分します。
処分方法は、売却が良いでしょう。
なお、売却するにも建物を残すか解体して更地にするかで、費用負担が変わります。
よって、建物の状態や周辺需要などを鑑み、どちらの売却方法が良いかを不動産仲介業者から提案してもらいましょう。
実家じまいにかかる費用
本章では、実家じまいにかかる費用について解説します。
不用品などの処分にかかる費用
不用品などの処分にかかる費用は、間取りや処分品の量など、総じて手間がどの程度かかるかで決まります。
また、大型の処分品が多いと搬出用のトラックを大型にする必要があり、費用負担が増えます。
以下は、間取りごとの不用品処分にかかる一般的な金額です。
| 間取り | 金額 |
| 1R~1LDK | 50,000~90,000円 |
| 2DK~2LDK | 100,000円~250,000円 |
| 3DK~3LDK | 150,000円~200,000円 |
| 4DK~4LDK | 200,000円~300,000円 |
上記は目安の金額であるため、不用品の処分費用については複数社に見積もり依頼しましょう。
家の解体費用
家の解体費用は、家の規模感や構造により変わります。
下記は、構造ごとの解体費用の目安です。
| 構造 | 解体費用(1坪あたり) |
| 木造 | 30,000~50,000円 |
| 鉄骨造 | 50,000~70,000円 |
| 鉄筋コンクリート造り | 70,000~100,000円 |
解体費用が決まる要素には、構造以外に解体工事のしやすさもあります。
たとえば、接面道路と段差がなく間口が広い角地であれば、解体工事用の重機が敷地内に入りやすく解体物の搬出もしやすいので手間はかかりません。
よって、この場合は相場並みで納まる可能性があります。
一方で、旗竿地のような奥まった土地や崖地のように接面道路と段差がある場合には、重機が入りにくく手作業に頼る部分が多いため、手間が掛かり費用が高くなる傾向があるでしょう。
よって、家の解体費用についても複数社に見積もりを取るのがおすすめです。
家の売却にかかる諸費用
家の売却にかかる諸費用は、以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登記費用
- 譲渡所得税・住民税
仲介手数料とは、取引を仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。
一般的には、400万円以上の成約の場合、「成約価格×3%+6万円+消費税」で計算できます。
印紙代は、売買契約を交わすときに使用し記載金額により変わります。
登記費用には、家にローンがあった場合の抵当権抹消費用、所有権移転登記費用と司法書士の報酬も含みます。
家の売却には諸費用がかかるため、手元に残る金額は諸費用を差し引いたものと考えておきましょう。
実家の売却益は、売却した年の所得として課税され、譲渡所得を申告し納税しなければなりません。
また、その分増えた所得に応じて住民税も課税されます。
譲渡所得税(復興特別所得税を含む)は以下のように計算されます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費+ 譲渡費用) − 特別控除
課税譲渡所得税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
譲渡収入金額とは、不動産の売却代金と固定資産税。都市計画税の精算金です。取得費は不動産を購入した当時の金額、譲渡費用は不動産会社に支払った手数料、相続の場合は一定期間のうちであれば相続税の一部も含まれます。
特別控除は空き家になってから3年以内の売却の場合、居住用住宅を売却した場合と同様3000万円の控除が適用されます。
譲渡所得税、住民税の税率は以下のようになります。
| 所得税(復興特別税含む) | 住民税 | 合計 | |
| 長期譲渡所得(5年を超えている) | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30.63% | 9% | 39.63% |
参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
実家じまいにおける税金についての注意点
本章で、実家じまいにおける税金についての注意点をご紹介します。
購入時の書類がないと譲渡所得税が高額になる
購入時の契約書等がないと譲渡所得税が高額となります。
なぜなら、購入時の書類がないと取得費計算において概算法を選ぶことになり、譲渡所得から差し引ける金額が少なくなるからです。
譲渡所得税が増えることで、手元に残る金銭が少なくなることに注意しましょう。
家を売却するタイミングに注意する
家を売却するタイミングは、相続開始後にします。
なぜなら、相続開始前に売却が完了し現金化していると相続税が高くなるからです。
不動産の相続税は、路線価をもとに決められますが、その評価額は実際の流通価格比80%に抑えられています。
したがって、現金で相続するよりも不動産で相続したほうが相続税を抑制できます。
よって、相続財産に不動産があったら、相続後の売却がおすすめです。
相続した空き家の売却では3,000万円控除の特例が利用できる
3,000万円控除の特例とは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けることで税負担を軽減できる制度です。
特例の利用には、マンションは不可、被相続人が直前まで居住していたなど多くの条件があります。
よって利用可否については、税務署への相談や国税庁のホームページなどを確認しましょう。
実家じまいでよくあるトラブル事例
本章で、実家じまいでよくあるトラブル事例をご紹介します。
登記識別情報が見つからない
相続で取得した家の登記識別情報(もしくは権利証)が見つからないことがあります。
登記識別情報は再発行ができず、これがなければ売却ができません。
よって、紛失であれば司法書士に本人確認情報を作成(5万円~10万円の費用がかかる)してもらいます。
売却ができずに相続資産がマイナスになる
売却ができずに相続資産がマイナスになることがあります。
たとえば、家が再建築不可物件の場合です。
一般的には流通しにくい不動産であるため、売却に苦慮することが多く、仮に売却できたとしても大幅にマイナスとなる可能性が高いでしょう。
これにより解体費を売却資金で捻出できず、預貯金等のプラスの資産も少なければ相続資産がマイナスとなってしまいます。
よって、このようなときには売却や解体をせずに既存建物を活用しましょう。
リフォーム等で初期費用はかかりますが、賃貸物件として収益を得られればマイナスを回避できる可能性があります。
売却ができずに相続税が払えない
家の売却ができずに、相続税が払えないことです。
相続税の支払いは、原則相続開始日から10か月以内の現金納付となるため、自己資金か相続した家を売却して賄います。
自己資金がない場合は家を売却するしかありませんが、立地により10か月以内の売却及び現金化が困難なケースもあるでしょう。
よって、売却するのであれば相続人全員の同意を早めに取り、迅速に着手できるように努めなければなりません。
まとめ
本記事では、実家じまいにかかる費用や流れ、注意点やトラブル事例を紹介しました。
実家じまいをするタイミングは、相続時や親が介護施設に入所するタイミングが多いです。
また、実家じまいには相続人間での話し合いや実際に処分を行う不動産会社等への相談も必要です。
実家じまいの大まかな流れを掴むことで、そのなかで決めなければいけないことや費用負担、注意点をケアして実家じまいを円滑に行えるようになるでしょう。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!