立ち退き合意書の雛形と記載例を紹介!必須項目や作成のポイントを解説
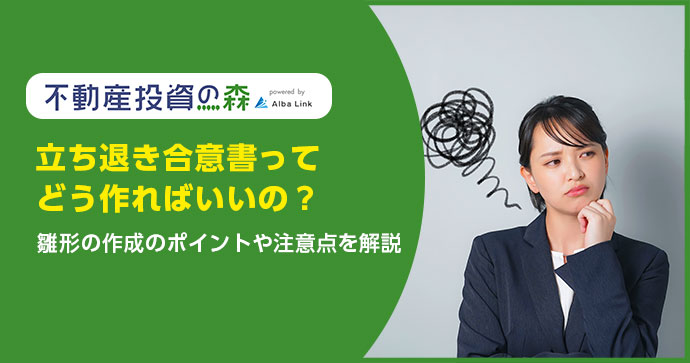
立ち退き交渉を進めたいけれど、「合意書って何を書けばいいの?」「ネットの雛形で本当に大丈夫?」と不安に感じていませんか?
実は、立ち退き合意書には法的な効力があり、内容次第で思わぬトラブルを防ぐことができます。
ただし、不備がある雛形をそのまま使うと、余分な費用負担や明け渡しの遅延を招くリスクもあるため、注意が必要です。
この記事では、立ち退き合意書を作成するときに役立つ、以下のようなポイントを解説します。
この記事を読むことで、雛形を利用するときの注意点や、抜け漏れを防ぐための実践的な知識が身につきます。
弊社Albalink(アルバリンク)では、高利回り物件の情報をLINEで配信中です。
弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。
まずはお気軽にLINE登録して、非公開物件の情報をチェックしてみてください。
空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
目次
立ち退き合意書の雛形を探す前に知っておきたい基本情報
ある程度書式が決まっている雛形は、立ち退き合意書を作成するときにとても役立ちます。
雛形を使って立ち退き合意書を作成する前に、以下のような基本情報を抑えておきましょう。
立ち退き合意書とは何か
立ち退き合意書とは、賃貸物件の貸主と借主が、契約終了や物件の明け渡しについて合意した内容を明文化した書面のことです。
立ち退きに関する条件や金額、期日などを明記することで、後のトラブルを防ぐ役割を果たします。
特に賃借人にとっては、退去時の条件や敷金の返還請求、残置物の取り扱いなどを明確にできるのがメリットです。
立ち退きが発生する可能性がある場合は、必ず立ち退き合意書を作成し、契約内容を明文化しておきましょう。
立ち退き合意書の法的な効力とは
立ち退き合意書には、一定の法的な効力があります。
書面で双方が署名・押印し、具体的な合意内容が記載されていれば、契約として成立し、裁判でも証拠として認められるのです。
合意書に署名があることで、退去期限が過ぎた後に強制退去を申し立てる根拠にもなり、裁判では貸主側に有利に手続きを進めやすくなります。
立ち退き合意書に退去条件や費用負担、明渡し期日などを明記することで、当事者の義務と権利を明確にし、トラブルの回避や迅速な解決に繋げることも可能です。
雛形利用のメリットと限界とは
立ち退き合意書の雛形を利用するメリットは、手軽に必要事項を記載できる点です。
インターネット上には無料テンプレートも多く、記載項目の抜け漏れを防ぐのに役立ちます。
一方で、雛形には限界があります。
個別の事情に即した記載が難しく、たとえば入居者が高齢で引越し先の確保に猶予が必要な場合や、立退料の金額が相場を超える場合など、雛形のままでは適切に対応できないケースがあるのです。
雛形はあくまで参考資料として使い、最終的には当事者の具体的な合意内容に応じて、内容の修正や追加を行うことが求められます。
場合によっては、弁護士をはじめとした専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。
立ち退き合意書の雛形に盛り込むべき8つの必須項目
立ち退き合意書に記載する項目は、ある程度決まっています。
ここでは、立ち退き合意書の雛形に盛り込むべき必須項目を8つ紹介します。
賃貸借契約解約の合意
立ち退き合意書において、まず明記すべきなのが「賃貸借契約の解約に関する合意」です。
次のような項目を明確に記載して、契約内容が双方の合意に基づくものであることを示しましょう。
- 契約の解除理由
- 解約の合意日
- 終了期日
賃貸借契約の解約の合意について記載されていないと、書面での合意がないことを根拠に借主が「強制的に退去させられた」と主張し、裁判での争いになる可能性があります。
立退の合意があっても、書類として残っていなければ後の証拠にはならないと考えて良いでしょう。
契約解除については、まず最初に書面で明確に記載しておくことが大切です。
解約後明け渡しまでの猶予期間
賃貸借契約の解約後、貸主に明け渡すまでの「猶予期間」を設定することは、現実的かつ円満な退去に繋がります。
実際に立ち退きの作業が始まると、引越し先の確保や残置物の処分などに時間がかかります。
明け渡し期限と猶予期間を話し合い、具体的な期日を合意書に明記して、借主に配慮した内容にしましょう。
加えて、猶予期間中の賃料や使用損害金の取り扱いについても記載しておくことで、後々のトラブルの回避にも繋がります。
賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人が物件を明け渡さない場合に、貸主が不法占拠されている期間の損害として賃借人に請求できる金銭
残存物の取り扱い
退去後に、借主の持ち物が室内に残されるケースは少なくありません。
そのため、立ち退き合意書には「残置物の処分方法」について明記することも大切です。
物件を退去したり、解体・リフォームしたりするときに、前の入居者や所有者が何も告げず、そのまま残していった家財や物品のこと。
貸主や不動産管理会社が、借主の残置物を勝手に処分した場合、裁判で損害賠償が命じられる可能性があります。
立ち退き合意書の雛形を作成する際は、「残置物の所有権を放棄する旨」や「一定期間後に貸主が処分しても異議を唱えない旨」を明記し、明確に取り決めを行うと良いでしょう。
立退料の金額と支払い条件
立退料は、借主が物件を明け渡す対価として支払われるお金です。
合意書には、立退料の金額や支払い条件を明確に記載しておきましょう。
立退料の支払い時期や支払い方法が不明確だと、立退料の支払いを巡って交渉が決裂し、訴訟に発展するリスクがあります。
立ち退き合意書には、立退料について、次のような条件を詳細に記載しましょう。
- 支払い金額
- 支払方法(現金・振込等)
- 支払い期限
- 前金の有無
契約終了後の使用損害金
賃貸借契約が終了した後も借主が物件を明け渡さなかったときに備えて、「使用損害金(賃料相当額)」の発生を認める条項も設けておきましょう。
退去日を過ぎても借主が居住し続けても、使用損害金の規定がないことが原因で、貸主側は賃料の請求ができなくなる可能性があります。
損害を回避するため、「退去期限を超えても明け渡しがない場合は、通常の賃料に相当する使用損害金を請求する」という旨を明記しておきましょう。
使用損害金の項目を設けることで、借主の早期退去を促す効果もあるため、貸主にとってリスク管理の手段にもなり得ます。
敷金の返還
敷金の返還に関しては、原状回復や未払い賃料との相殺を踏まえて、具体的な「返還時期」と「返還額の算定方法」を明記しておきましょう。
建物や部屋を借りる人が、持主に預けておく保証金のこと。退去するときに、家賃の滞納分や原状回復費用を差し引いた金額が、借りた人に変換される。
具体的には、次のような項目を記載しておくと良いでしょう。
- 返還額
- 返還期日(例:明け渡し後◯日以内)
- 相殺対象(例:滞納賃料・修繕費等)
敷金トラブルは非常に多いため、立ち退き合意書に敷金の返還について記載されていないと、借主側が「敷金を全額返還してほしい」と主張してトラブルに発展する可能性があります。
不動産契約では、敷金返還のトラブルはとても多いため、合意書のなかでも特に丁寧に取り扱うべき項目といえるでしょう。
原状回復義務の範囲
賃貸借契約終了時の原状回復については、「借主が負担する範囲」を明確に定めるのがポイントです。
借主が負担する範囲が曖昧だと、どこまで借主が負担するのか、後で大きな問題に発展することがあります。
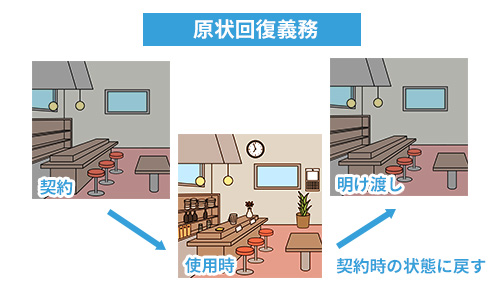
原状回復では 「通常損耗」 と 「特別損耗」 を区別します。
- 通常損耗(借主負担ではない)
例)日焼け、家電の熱による壁紙変色、家具跡 - 特別損耗(借主負担)
例)タバコ汚れ、ペット損壊、手入れ不足によるカビ
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常の使用による劣化は借主の負担にはならず、特別な損傷や改造にのみ負担が生じるとされています。
参照元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
立ち退き合意書には「通常損耗については貸主負担とする」「借主が設置した設備の撤去は借主が行う」など、範囲を具体的に記載しましょう。
原状回復の内容を明文化しておくことで、後日のトラブルや費用請求の争いを回避しやすくなります。
清算条項(その他請求をしない旨)
最後に忘れてはならないのが、「清算条項」です。
合意書に記載された内容以外には、貸主・借主双方が追加の請求を行わないという合意のこと。
清算条項を設けていないと、借主側から「退去後にクリーニング代を追加請求された」「追加の補償を求められた」等と主張され、貸主の負担が増加する可能性があります。
後々のトラブルを防ぐには、清算条項を設けて、「本合意書に記載された内容をもって、賃貸借契約に関するすべての債権債務関係は完全に終了する」という旨を明記しておくことで双方のリスクが大幅に減ります。
清算条項があることで、退去後の不要なトラブルを防ぎ、スムーズに契約を終結できる環境を整えることができます。
立ち退き合意書を作成するときの7つのポイント
立ち退き合意書を作成するときは、必須項目を記載する以外にも、スムーズに手続きを進めるために大切なことがあります。
ここでは、立ち退き合意書を作成するときのポイントとして、以下の7つを紹介します。
物件明け渡しまでのスケジュールを具体的に記載する
立ち退き合意書では、物件明け渡しまでのスケジュールを具体的に記載することがとても重要です。
スケジュールを具体的にすることで、双方の都合に基づいた計画的な対応を実施しやすくなります。
「〇月〇日までに退去」と曖昧に記載するだけでは、解釈の違いでトラブルが発生する可能性があります。
立ち退き合意書を作成するときは、物件明け渡しまでのスケジュールについて、次のような項目を記載しましょう。
- 契約解除の合意日
- 猶予期間
- 明け渡し期日
- 鍵返却方法
- 電気ガス水道の閉栓確認の責任者など
特に、契約解除日=明け渡し期日ではないことが多く、書面で明確化しないとトラブルになる可能性があります。
明け渡しの具体的な期日が決まっていれば、貸主・借主双方が落ち着いて手続きを進められるでしょう。
支払い条件と期日を明確にする
立退料の支払いに関しては、金額だけでなく「支払い条件と期日」も明確に定めましょう。
支払い条件と期日を明確にすることで、支払いの遅延や未払いによるトラブルを回避しやすくなります。
明確な合意が書面で残されていないと、立退料を支払うタイミングや支払い方法を巡って話し合いがまとまらなくなる可能性があります。
立ち退き合意書を作成するときは、「〇月〇日までに一括支払い」「契約成立時に半額、明け渡し時に残額支払い」など、支払いの方法・期日を明記しておきましょう。
双方署名・捺印の2部作成を徹底する
立ち退き合意書は、貸主・借主の双方が「署名・捺印」し、それぞれ1部ずつ保管する「2部作成」が基本です。
2部作成をすることで、契約の成立を証明できます。
署名が片方だけだと、借主側が「合意していない」と主張し、合意書の効力が争点になる可能性があります。
合意書には必ず当事者の署名・捺印を行い、2部を作成・保管しましょう。
収入印紙の貼付が求められる場合がある点にも要注意です。
印紙税などの租税や手数料を納付した証明として、国が発行する証票のこと。契約書や領収書のような、経済取引が伴う文書に貼付する。
法務チェックを受ける
合意書の法的効力を確保するためには、弁護士や法律事務所などの専門家による「法務チェック」が有効です。
専門家によるチェックでは、記載の不備、条項の矛盾、契約法上のリスクを事前に洗い出すことができます。
特に家賃滞納や損害賠償に関わる条項は、法的な観点からの精査が必要です。
法律の知識がない人が、インターネット上のテンプレートを用いて立ち退き合意書を作成すると、不備だらけで、訴訟時に証拠能力が低いと判断される可能性があります。
合意書の信頼性を高め、トラブルを回避するためにも、専門家による法務チェックを受けるようにしましょう。
専門家に立ち退き合意書の雛形を作ってもらう
立ち退き合意書の雛形は、インターネット上に多数ありますが、可能であれば専門家に依頼して「オーダーメイドの雛形」を作ってもらうのが理想です。
インターネット上に落ちている雛形は一般的な事例を記載したにすぎず、多様な取引に対応できない場合があります。
具体的には以下のリスクがあります。
- 最新の法律に適していない場合がある(古い法律を前提としていて契約条項が現在の取引形態に適合しなくなっている)
- 当事者のいずれか一方に有利に作成されている場合が多くその選択を誤ると自社に不利益な契約書を知らぬ間に交わしてしまう
- 原状回復・残置物処理・敷金精算が抽象的(後のトラブルに発展する可能性)
専門家による雛形は、個別の物件の事情や当事者の状況に応じて柔軟にカスタマイズできるため、テンプレートでは対応が難しい複雑な合意内容にも対応できます。
雛形はあくまで「枠」であり、個別事情に合わせた修正が不可欠です。
専門家に依頼するには費用がかかりますが、法的リスクへの対策も盛り込まれるため、費用はかかっても長期的にはトラブル回避に繋がるメリットがあります。
交渉の経過を記録として残す
立ち退きに至るまでの交渉の経過を記録しておくことは、将来的なトラブル防止にとても有効です。
たとえば、借主が「立ち退きに関する合意が強制的に押し付けられた」と主張しても、メールや録音の記録があることで、交渉が任意であったと裁判所に認定されやすくなります。
記録には、次のようなことを残しましょう。
- 交渉の日時
- 出席者
- 発言内容
- 合意に至る理由
記録方法としては、議事録、メール、録音などが挙げられます。
交渉の経過を残すことで、立ち退きに至る流れの透明性が確保されるため、貸主・借主双方の信頼関係の構築にも効果が期待できます。
必要に応じて高齢者・生活困窮者への配慮を追加する
借主が高齢者や生活困窮者である場合、立ち退きの合意書には「特別な配慮の条項」を追加することが望ましいです。
たとえば、高齢の入居者に立ち退きを依頼する場合、引越し先の紹介や引越し費用の一部負担を合意書に明記することで、スムーズな明け渡しを実現しやすくなります。
必要に応じて、行政や福祉機関と連携するのも良いでしょう。
社会的に弱い立場の人への配慮は、貸主側の誠実さを示すだけでなく、後の紛争リスクを大幅に軽減するためにも効果的です。
立ち退き合意書の作成で雛形を使用する3つのリスク
立ち退き合意書を作成する際に雛形を使うと、ある程度合意書が完成しているためとても便利です。
しかし、雛形には以下の3つのようなリスクがある点にも注意しましょう。
印紙税が課税される場合がある
雛形をもとに立ち退き合意書を作成するときに見落とされやすいのが、「収入印紙の貼付が必要なケースがある」という点です。
印紙税の課税対象になるか否かは、契約内容や金額の記載によって異なるため、注意が必要です。
日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など に課税される税金
たとえば、立退料の金額を合意書に明記し、契約書として締結した結果、その合意書は「金銭の受け渡しに関する契約」とみなされ、印紙税が課税対象になる場合があります。
雛形には印紙税に関する注意喚起がされていない場合が多いため、リスクを回避するには、文書の種類を正確に把握したうえで、専門家に確認することが不可欠です。
印紙の貼付漏れは、契約の効力には影響しないものの、費用負担の増加やトラブルの原因になりかねないため注意しましょう。
立退料の支払時期によるトラブルが発生する可能性がある
雛形の利用において、立退料の「支払時期」が曖昧なまま契約書が作成されると、後にトラブルを招く可能性があります。
支払うタイミングが明記されていなければ、貸主・借主間での解釈にズレが生じるためです。
たとえば、借主は退去前の支払いを想定していたのに対し、貸主は明け渡し完了後と理解していると、立退料の支払いをめぐって意見が衝突する可能性があります。
場合によっては、退去が遅れ、家賃の二重支払いが発生するなど、損害が広がるかもしれません。
雛形では一般的な文言しか記載されていないことが多いため、合意内容に沿って「前金で支払うのか」「分割払いか」「退去完了後か」など、具体的な条件と期日を明記する必要があります。
原状回復や修繕費用の負担が曖昧になりやすい
雛形では、「原状回復」や「修繕費用の負担」について十分な記載がない場合が多く、契約後にその範囲を巡るトラブルが発生するリスクがあります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常損耗と特別損耗は負担者が異なると明示されていますが、雛形にはこの区別が反映されていないことが多く見られます。
- 通常損耗
- 賃貸物件の入居者が通常の生活を続けた結果、避けられずに生じる傷みや汚れ(例:家具を設置したことによる床の凹み、冷蔵庫による壁紙の電気ヤケ(黒ずみ)等)
- 特別損耗
- 入居者の故意や過失などによって発生した、通常の使用範囲を超える損耗のこと(例:タバコによる壁紙の変色、手入れ不足による水回りのカビ等)
たとえば、貸主が「経年劣化による壁紙の張替え費用」を借主に請求しても、借主が「それは通常使用によるもので負担義務はない」と主張すれば、立ち退き交渉が停滞するかもしれません。
裁判に発展した結果、合意書に詳細な規定がないことを理由に、裁判所は借主に有利な判断を下す可能性も考えられます。
雛形に頼るだけでなく、個別の物件や契約内容に応じて記載内容を調整することが重要です。
立ち退き合意書の作成で起こりやすい3つのトラブル
立ち退き合意書を作成するときに発生しやすいトラブルとしては、以下の3つが挙げられます。
明け渡し日の認識のズレ
立ち退き合意書で多く見られるトラブルのひとつが、「明け渡し日の認識のズレ」です。
明確に記載されていないと、借主と貸主の間で退去時期に食い違いが生じ、トラブルの原因となります。
たとえば、借主が「猶予期間中の退去」で良いと解釈していた一方で、貸主が「契約解除日が明け渡し日」と理解していると、明け渡しが遅延したことで使用損害金を請求することになるかもしれません。
明け渡し日の認識のズレによるトラブルを防ぐためには、次のような項目を具体的に記載し、双方が内容を理解したうえで署名・捺印することが必要です。
- 明け渡し期日
- 猶予期間
- 立退完了日
契約内容を明確にしないと、後で裁判や損害請求に発展する可能性もあるため、合意内容は書面で正確に取り決めておきましょう。
残置物処理のため追加費用が発生する
退去後に残された家具や家電などの「残置物」が原因で、貸主側に追加費用が発生するトラブルもよく起こります。
特に処分方法の合意が曖昧な場合、費用負担を巡る争いに発展しやすいです。
合意書に処分条件の記載がないと、借主が室内に残置物を放置して退去しても、借主に処分費用を請求できず、追加費用が発生する場合があります。
追加費用の発生を回避するには、「退去時点で残置物があれば貸主が自由に処分でき、費用は借主負担とする」といった条件を明記しておくことが求められます。
敷金の返還額を巡る紛争が起こる
立ち退き時のトラブルとしてよくあるのが、「敷金の返還額を巡る紛争」です。
特に、原状回復費用や未払い家賃の精算方法が曖昧だと、後で揉める可能性が高くなります。
合意書に具体的な条件を書いていなかったことが原因で、貸主が「修繕費用や家賃滞納分を差し引く」として全額返還を拒否しても、借主が「全額返還されるはず」と主張して、裁判に発展する場合があるのです。
敷金に関するリスクを避けるためには、次のような項目を明記し、双方が理解・納得の上で契約を締結する必要があります。
- 敷金から相殺する項目
- 返還期限
- 算定方法
敷金に関するトラブルは感情的な対立に発展しやすいため、書式や雛形だけに頼らず、具体的な数値や対応方法まで記載しましょう。
立ち退きに合意した後の明け渡し・立ち合い確認の流れ
立ち退きに合意した後は、「明け渡し」と「立ち合い確認」の手続きがスムーズに進むよう、具体的な流れを理解しておくことが重要です。
立ち退きに合意した後の明け渡し・立ち合い確認の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 退去期日までに借主が室内を整理・原状回復をして、残置物がない状態で明け渡す
- 貸主または不動産管理会社と借主が現地で「立ち合い確認」を行う
- 損傷箇所や未処理事項をチェックして合意書に基づいた対応を確認する
立ち合い確認を省略すると、退去後に破損が見つかり、修繕費の請求をめぐってトラブルに発展する可能性があります。
立ち合い確認は、立ち退き合意書の内容や履行状況を確かめる機会のため、実施するようにしましょう。
まとめ
立ち退き合意書の作成においては、雛形の活用が手軽な反面、記載漏れや曖昧な表現によるトラブルのリスクも存在します。
特に、立退料の支払い時期や原状回復費用の負担、明け渡し日の認識違いといった点は、後々の大きな紛争の火種になりかねません。
合意書を作成する際は、雛形を参考にしつつも、専門家によるチェックを受けるなど、慎重な対応が求められます。
雛形を使用するリスクを避けつつ、スムーズに物件の明け渡し交渉を進めたい場合は、交渉が不要な高利回り物件へ乗り換えるのもひとつの方法です。
訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)では、法的な不安を抑えつつ、利回りの高い投資物件の紹介も行っています。
公式LINEでは、非公開物件情報や収益性の高い不動産情報を無料で配信しているので、ぜひ登録してみてください。
空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ
「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!
【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!








